H30卒業文集「風は吹いている」【原稿】 ― 2019/03/01

『風は吹いている』
新婚旅行でフランスへ行った。
(地球は巨大だよ)なんて思っていたが、飛行機で半日で行けてしまって、(案外小さいのかも)なんて思い直したことがあった。
ちなみに東京→パリ間は12・5時間、パリ→東京間は12時間で、少し速くなる。
地球が自転しているから?いいや、この差は偏西風によるものだ。
風はどうして吹くのだろう。
地球は自転しているので、昼間の地表は太陽に照らされて暖まり、温度差を作り出す。
温度差は気圧の差となり、その差を埋めようと空気が動き出し、風が生じるのだ。
海はどうして波があるのだろう。
風も原因の一つである。地球のどこかでいつも風が吹いていて、海水を動かしている。
もう一つは月の引力だ。それで海水を引き上げて満潮になる。
地球は自転しているので反対側も遠心力で満潮になる。
その中間が干潮になり、その差で波が生じるのだ。
地球は巨大である。
空気も海水も重力によって大地に押し付けられている。
さらに地球は自転している。
動いている空気にも、動いている海水にも、それとは逆向きの摩擦力が生じている。
つまり風も止んでしまうし、波も収まってしまうはずだ。
地球が自転しているから動くのに、地球が自転しているから止まってしまう。
地球とは矛盾に満ちた星なのかもしれない。
動き出そうとする者がいると、それを止めようとする者が現れる。
平和の大切さを学んだ人類が、それでもまだ戦争を起こそうとする。
原発事故を経験した日本人が、それでもまだ原発を再稼働しようとする。
明日を夢見て、希望を語る者がいると、昨日を悔やみ、絶望を嘆く者がいる。
人間とは矛盾に満ちた生き物なのかもしれない。
しかし、地球の自転は止まらない。
宇宙がほぼ真空で、地球との間には摩擦が働かないからだ。
人類の歩みは止まらない。
人間の想像力がほぼ無限で、他者との間には摩擦が働かないからだ。
それならば、私たちはどうだろうか。あなたはどうだろうか。
求められるのは、想像力である。
戦争を求める者の心には何があるのか。
原発再稼働派の人たちの目的は何なのか。
もしかしたら方法論が違うだけで、希求する目的は同じなのかもしれない。
ならば、想像力というハンマーで、その間の壁を壊すことはできないだろうか。
溝を埋めることはできないだろうか。橋を作ることはできないだろうか。
風も波も、私たちを脅かす災害になる時もあれば、私たちを癒すやさしさにもなる。
言葉も刃も、私たちを傷つける時もあれば、私たちを笑顔にするときもある。
方法も目的も、私たちの想像力ひとつで、全然違った未来をもたらしてくれるはずだ。
向い風が吹いているのか、私たちが走り続けているのか。
足を止めてはならない。いつだって風は吹いているのだから。
卒業おめでとう。
新婚旅行でフランスへ行った。
(地球は巨大だよ)なんて思っていたが、飛行機で半日で行けてしまって、(案外小さいのかも)なんて思い直したことがあった。
ちなみに東京→パリ間は12・5時間、パリ→東京間は12時間で、少し速くなる。
地球が自転しているから?いいや、この差は偏西風によるものだ。
風はどうして吹くのだろう。
地球は自転しているので、昼間の地表は太陽に照らされて暖まり、温度差を作り出す。
温度差は気圧の差となり、その差を埋めようと空気が動き出し、風が生じるのだ。
海はどうして波があるのだろう。
風も原因の一つである。地球のどこかでいつも風が吹いていて、海水を動かしている。
もう一つは月の引力だ。それで海水を引き上げて満潮になる。
地球は自転しているので反対側も遠心力で満潮になる。
その中間が干潮になり、その差で波が生じるのだ。
地球は巨大である。
空気も海水も重力によって大地に押し付けられている。
さらに地球は自転している。
動いている空気にも、動いている海水にも、それとは逆向きの摩擦力が生じている。
つまり風も止んでしまうし、波も収まってしまうはずだ。
地球が自転しているから動くのに、地球が自転しているから止まってしまう。
地球とは矛盾に満ちた星なのかもしれない。
動き出そうとする者がいると、それを止めようとする者が現れる。
平和の大切さを学んだ人類が、それでもまだ戦争を起こそうとする。
原発事故を経験した日本人が、それでもまだ原発を再稼働しようとする。
明日を夢見て、希望を語る者がいると、昨日を悔やみ、絶望を嘆く者がいる。
人間とは矛盾に満ちた生き物なのかもしれない。
しかし、地球の自転は止まらない。
宇宙がほぼ真空で、地球との間には摩擦が働かないからだ。
人類の歩みは止まらない。
人間の想像力がほぼ無限で、他者との間には摩擦が働かないからだ。
それならば、私たちはどうだろうか。あなたはどうだろうか。
求められるのは、想像力である。
戦争を求める者の心には何があるのか。
原発再稼働派の人たちの目的は何なのか。
もしかしたら方法論が違うだけで、希求する目的は同じなのかもしれない。
ならば、想像力というハンマーで、その間の壁を壊すことはできないだろうか。
溝を埋めることはできないだろうか。橋を作ることはできないだろうか。
風も波も、私たちを脅かす災害になる時もあれば、私たちを癒すやさしさにもなる。
言葉も刃も、私たちを傷つける時もあれば、私たちを笑顔にするときもある。
方法も目的も、私たちの想像力ひとつで、全然違った未来をもたらしてくれるはずだ。
向い風が吹いているのか、私たちが走り続けているのか。
足を止めてはならない。いつだって風は吹いているのだから。
卒業おめでとう。
生徒との関係を作るためには、生徒と一緒にいることだ。 ― 2018/07/05

クラスでも、生徒会でも、部活動でも、生徒に好かれる先生は、生徒と一緒にいる先生だ。
部活動で一緒に汗をかいてくれる先生、練習を見守ってくれる先生、大きな声で励ましてくれる先生、そういうことが先生として大事なのだ。
いつもよりキツいメニューなら、生徒と一緒に練習してみる。
外の部活で雨が降ったら、傘さしてもささなくても練習を見に行って一緒に濡れる。
生徒の願いをくみ取って精一杯に情報を集めたり、練習試合を組んだり、熱い話をしたりする。
三十代になってもやっている。今の若い先生なら、もっとやってもいいはずなのに。
先生の三十代の姿を見て学んだことだ。
「お前はラッキーだ。脂がのった三十代の俺を見ることができて。」と言われた。
あのときの先生のように、俺にできるだろうか。
後輩達にどうやって伝えたらいいのだろうか。
講師時代にお世話になった先生に教えられたことでした。
(Evernoteを漁っていたら見つけました。)
仕事も勉強も、80点を3回取ればOK ― 2018/03/05
かつて、「3割できれば」という記事を書きました。
http://kani.asablo.jp/blog/2012/04/04/6548660
今回は8割の話をします。
宿題を完璧に終わらせないと気が済まないという生徒がいて、完璧にできていないために、「学校を休みたい」と言い出したことがありました。
その生徒を意識して、80点を3回取ろうという話を、授業の中でしました。
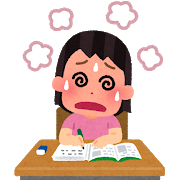
自分のレベルで100点の仕事をしたと思って、上司に提出したとします。
しかし、上司は「自分の仕事として」、必ずどこかに赤を入れます。
そうしなければ、自分の仕事がなくなってしまうと思っている上司が多いからです。
だから、初めから100点を取るのではなく、80点を取って上司に見てもらって、100点にするのです。
その方が、結果的にみんながハッピーになり、しかも多くの成果を挙げることができます。
それが組織というものです。
もしも、一人で100点を取り続けられるならば、独立したほうがいいと思います。
社長になれる素質があります。
今回さらに思ったことは、100点を1回取るよりも、80点を3回取ればいいのだということです。
どういうことかというと、点数をパーセンテージにして考えてください。
1回目、100点の80パーセントは80点です。これで上司に報告します。
赤が入って戻ってきます。次は、のこり20点取ればいいのです。
2回目、その20点の80パーセントをとって、16点を上乗せします。
これで96点です。これで報告すれば、まぁOKなはずですよね。
でもまた赤が入って戻ってきます。のこり4点を取りに行きます。
3回目、のこり4点の80パーセントで3.2点が上乗せされます。
合わせて、99.2点となります。もうこれ以上はいいでしょう。
重箱の隅をつつかれることがなければ、十分です。

100点にこだわって遅くなるよりも、3回チャレンジして80点を取り続けた方が、いいのです。
上司も仕事ができてハッピーだし、上司の意見も取り入れてあるので文句ありません。
学校でいえば、教務、教頭、校長という3段階で起案の承認を得るので、これと同じことが言えます。
最後の1パーセントは、大丈夫、校長先生がきっと責任を取ってくれますから。
そんな風に思いました。少し、気が楽になりましたか?
H29卒業文集「風に立つライオン」【原稿】 ― 2018/03/01

風に立つライオン
「担任の先生がよく言っていることは何ですか?」
面接で生徒が質問されたときに困らないように、自分の決め台詞を考えないと…、なんて思って数年。
私が行きついたのは「プラスアルファ」だった。
「いつもの掃除にプラスアルファしないときれいにならないよ。」
「自主勉にプラスアルファしないと点数伸びないよ。」
「部活でプラスアルファの練習をしないと人より上手になれないよ。」
そんなことを語ってきた(つもりです)。
プラスアルファ…日本語だと、「さらに加えて」だと思う。
他人の2倍も3倍も努力することはできないけれど、あと一割くらいなら頑張れそうだし、昨日の自分より1%増やすことはできる。
今回は前回よりもできるように、もう一歩前進できるように。
小学生のときは剣道をやって竹刀を構えていた。中学生になると野球部でキャッチャーミットを構えていた。高校の吹奏楽部ではトランペットを構えていた。大学生になるとカメラを構えるようになった。
いつも何かを構えて、あと一歩、何かに手を伸ばそうとしている自分がいた。
相手に向かって、相手の胸に、相手の耳に、相手の心に、何とか手を伸ばそうとしていた。
そして、剣道から心技体を常に鍛え、整えること、野球から恐怖を乗り越え、正しい判断をすることを学んだ。吹奏楽からは調和と主張、理想と現実、カメラから世界の見方と歩き方を学んだ。
大人になって、道具に頼って人と関わってきた自分に気づいてからは、カメラがなくても人に近づくために、何も持たない自分と向き合い、勇気をふりしぼる毎日だった。
頼れるものは、この、低くて、小さくて、聞き取りにくい、声しかなかったのだ。
何と声を掛けようか、何と言ったら傷つかないか、何を話せば自信がつくか、どんな言葉を使えば分かりやすいか。
あと一言何と言ったらいいか…、言葉と向き合う日々だった。
毎日にらめっこしている手帳には、そんな試行錯誤のメモがいくつも残っている。
小さな頃からの夢を思い出してみると、お寿司屋さん、大工さん、ゲームライター…、中学生のときは小説家、高校生で教師となり、大学ではカメラマン、大学院で「やっぱり教師」となって今に至っている。
幸運なことに、いつも自分には夢があって、それに向かって歩いていた。
夢の一つ一つは泡のように小さな点だけれど、その点が一日一日の点とつながって線となり、振り返ってみると、今の道につながっている。
大学教授に「点で線を書くくらい実験をしろ」と言われたが、それは人生も同じだと、大学を卒業して二十年経って気が付いた。
今でも夢がある。今でも寿司職人には憧れるし、大工さんは尊敬している。
そしていつかは(中二病と笑われそうだけれど)ゲームや本の世界ではなく現実で、世界を救いたいと思う。
まずは目の前の世界を何とかして、仲間を増やすステージにいる。
風に立つライオンになりなさい。
自分の判断に勇気を持ち、結果を謙虚に受け止め、次に向かって全力を尽くす。
そしてできれば、プラスアルファする。人生はその繰り返しです。
時間は有限でも、夢は連鎖しています。
エネルギーは有限でも、宇宙は循環しています。
涙は有限でも、笑顔は伝播しています。
自分の足で立ち、世界を見に行きなさい。
あなた方と一緒のクラスで過ごせたことを、本当に嬉しく思う。ありがとう。
【金言】はきものをそろえる ― 2017/04/28

『はきものをそろえる』
はきものをそろえると こころもそろう
こころがそろうと はきものもそろう
ぬぐときにそろえておくと
はくときに心がみだれない
だれかがみだしておいたら
だまってそろえておいてあげよう
そうすればきっと
世界中の人の心も そろうでしょう
藤本幸邦 和尚 (長野県篠ノ井町円福寺)
かつて勤務していた学校の体育館入り口に掲示されていました。
当時もいい詩だな~と思って写真を撮った記憶があります。
(その写真がどこにいったかは分かりません)
先日、またこの詩に出会うことができたので、今回は忘れないようにブログにアップしておきます。
学級通信のネタにも使いました。
うちの学校でも、はきものをそろえる習慣をつけさせようと頑張っています。
非常に素直な生徒たちなので、やろうというとすぐにやることはできます。
下駄箱のくつはきれいにそろっています。
しかし、大事なのはその次です。
『だれかがみだしておいたら だまってそろえておいてあげよう』
つい面倒がってやりません。
ついチクるように先生や友達に言ってしまいます。
つい恩着せがましくその子に言ってしまいます。
そうです。
誰かの靴が乱れていたら、直してあげて、そしてそのことを誰にもアピールしないのです。
自分も含めて、いいことをすると、ついついアピールしたくなりますよね。
そこを謙虚に。
誰にもほめられなくても、貢献感を味わって満足して終わるのです。
くつをそろえる。
単純なことですが、だからこそ一生続けていく修行ですね。
はきものをそろえると こころもそろう
こころがそろうと はきものもそろう
ぬぐときにそろえておくと
はくときに心がみだれない
だれかがみだしておいたら
だまってそろえておいてあげよう
そうすればきっと
世界中の人の心も そろうでしょう
藤本幸邦 和尚 (長野県篠ノ井町円福寺)
かつて勤務していた学校の体育館入り口に掲示されていました。
当時もいい詩だな~と思って写真を撮った記憶があります。
(その写真がどこにいったかは分かりません)
先日、またこの詩に出会うことができたので、今回は忘れないようにブログにアップしておきます。
学級通信のネタにも使いました。
うちの学校でも、はきものをそろえる習慣をつけさせようと頑張っています。
非常に素直な生徒たちなので、やろうというとすぐにやることはできます。
下駄箱のくつはきれいにそろっています。
しかし、大事なのはその次です。
『だれかがみだしておいたら だまってそろえておいてあげよう』
つい面倒がってやりません。
ついチクるように先生や友達に言ってしまいます。
つい恩着せがましくその子に言ってしまいます。
そうです。
誰かの靴が乱れていたら、直してあげて、そしてそのことを誰にもアピールしないのです。
自分も含めて、いいことをすると、ついついアピールしたくなりますよね。
そこを謙虚に。
誰にもほめられなくても、貢献感を味わって満足して終わるのです。
くつをそろえる。
単純なことですが、だからこそ一生続けていく修行ですね。
【卒業文集】Dancer in the Glare ― 2017/03/01

高校吹奏楽部では毎年夏に定期演奏会があった。
トランペットだった私も、大舞台でときどきソロ演奏をした。
ステージの真ん中に出てきて、トランペットを構える。
スポットライトがバッと当てられる。
みんなの演奏をバックに、自分だけの楽譜を吹く。
想像してもらうと、ものすごく緊張するけれど、ものすごく興奮する場面だと思う。
でも気が付いたことがあった。
眩しすぎるライトが当てられると、実は周りが見えなくなるのだ。
周りには大勢の人がいるはずだし、みんなの演奏も聞こえるのに、周りが全然気にならない。
強烈な光の下で、自分は一人、自分の演奏に無我夢中になっていた。
理科の先生になろうと思ったきっかけは、「光」の不思議さだった。
「真っ暗だから見えない」というのは分かる。でもどうして「明るくて見えない」のか。
考えても分からない。高校物理では説明できない。
実は生物学の知識も必要だと気付いたのは大学に入ってからだった。
大学に入ると分からないことだらけだと気付かされた。
ガスクロという実験装置から離れられず何日も研究室の床で寝る生活に嫌気がさした日もあれば、相対性理論を理解できて舞い上がった日もあった。
がむしゃらにもがいた日々だった。
たまの休日には映画を観ながら寝落ちしていた。
「ダンサー・イン・ザ・ダーク」という映画に出会ったのも、大学4年の夏だったと思う。
光と闇はいつも私のテーマだった。
今の自分に強烈なスポットライトを当てよ。
周りなんて気にしないで、自分の人生に光を当てよ。
自分の思い込みにすぎない過去なんてどうでもいい。
トラウマなんて存在しない。
自分の勝手な妄想にすぎない未来なんてどうでもいい。
占いなんて当てにならない。
ただ立ち止まっていては行けない。
歩き出すのが怖いなら、走り出すのが辛いなら、踊ればいい。
いま、ここで、全力のダンスを踊ればいい。
どこに行くかなんて気にしない。目的地なんて決めない。
今の一歩に全力を尽くし、次の一歩に集中する。
私はこの年になってアドラー心理学に出会った。
スティーブ・ジョブズの卒業式スピーチを聞いたのは数年前だ。
あなた方は私より若い。
今をがむしゃらに生きればそれでいい。
後先考えず、なりふり構わず、いま、ここを、全力で踊れ。
まぶしすぎる光の中で踊れ。
卒業おめでとう。みなさんが光とともにあることをご祈念申し上げます。
(野球部のみんな、楽しい野球をありがとう。)
トランペットだった私も、大舞台でときどきソロ演奏をした。
ステージの真ん中に出てきて、トランペットを構える。
スポットライトがバッと当てられる。
みんなの演奏をバックに、自分だけの楽譜を吹く。
想像してもらうと、ものすごく緊張するけれど、ものすごく興奮する場面だと思う。
でも気が付いたことがあった。
眩しすぎるライトが当てられると、実は周りが見えなくなるのだ。
周りには大勢の人がいるはずだし、みんなの演奏も聞こえるのに、周りが全然気にならない。
強烈な光の下で、自分は一人、自分の演奏に無我夢中になっていた。
理科の先生になろうと思ったきっかけは、「光」の不思議さだった。
「真っ暗だから見えない」というのは分かる。でもどうして「明るくて見えない」のか。
考えても分からない。高校物理では説明できない。
実は生物学の知識も必要だと気付いたのは大学に入ってからだった。
大学に入ると分からないことだらけだと気付かされた。
ガスクロという実験装置から離れられず何日も研究室の床で寝る生活に嫌気がさした日もあれば、相対性理論を理解できて舞い上がった日もあった。
がむしゃらにもがいた日々だった。
たまの休日には映画を観ながら寝落ちしていた。
「ダンサー・イン・ザ・ダーク」という映画に出会ったのも、大学4年の夏だったと思う。
光と闇はいつも私のテーマだった。
今の自分に強烈なスポットライトを当てよ。
周りなんて気にしないで、自分の人生に光を当てよ。
自分の思い込みにすぎない過去なんてどうでもいい。
トラウマなんて存在しない。
自分の勝手な妄想にすぎない未来なんてどうでもいい。
占いなんて当てにならない。
ただ立ち止まっていては行けない。
歩き出すのが怖いなら、走り出すのが辛いなら、踊ればいい。
いま、ここで、全力のダンスを踊ればいい。
どこに行くかなんて気にしない。目的地なんて決めない。
今の一歩に全力を尽くし、次の一歩に集中する。
私はこの年になってアドラー心理学に出会った。
スティーブ・ジョブズの卒業式スピーチを聞いたのは数年前だ。
あなた方は私より若い。
今をがむしゃらに生きればそれでいい。
後先考えず、なりふり構わず、いま、ここを、全力で踊れ。
まぶしすぎる光の中で踊れ。
卒業おめでとう。みなさんが光とともにあることをご祈念申し上げます。
(野球部のみんな、楽しい野球をありがとう。)
【卒業文集】誰がために鐘は鳴る ― 2016/03/01

「共鳴」という言葉を初めて聞いたのは、高校の吹奏楽部でのことだった。
「よく聴いてごらん。自分と周りの出している音のほかに、もう一つ上の音が聞こえるでしょう?」と言われ、トランペットを吹きながら耳を澄ませた。バンド全員の音程が揃ったとき、確かにその音が聴こえた。「それが倍音だよ。完璧に共鳴したんだ。」
「美しい音楽というのはその倍音がたくさん含まれていて、意識していなくても聴く人の心に響くんだ。」と教わった。
大学の物理化学の講義では、「同じ波長・振動数をもつものは共鳴する。音だけでなく、遠くのテレビも足元の放射線も同じだ。共鳴するとエネルギーになる。」と学んだ。
赤外線が水分子に共鳴して、物を温める。紫外線が皮ふ細胞に共鳴して、日焼けする。
電波がテレビに共鳴して、番組が切り替わる。放射線がDNAに共鳴して、傷をつける。
自然界はエネルギーを保存しているが、その間は共鳴という現象が繋いでいる。
人間はどうだろう? (あぁ、人間は共感できる。)
頑張っている人を見て、自分も頑張ろうと思う。悲しんでいる人を見て、涙が溢れる。
怒りの声を聴いて、拳を振り上げる。周囲を笑顔にする人につられて、笑みがこぼれる。
人は感動を生み出し続けているが、その間は共感という心が繋いでいる。
自分はどうだろう? (自分からは逃げられない。)
あなたの隣にいる人は笑顔でいるだろうか?どうしたら笑顔にできるだろうか?何と声を掛けたら笑顔になるだろうか?
その人の波長に合わせて、その人の心をふるわせるにはどうしたらいいのだろう?
昨日を後悔して泣く人の涙を振り払う波長…、明日を憂え恐れる人を奮わせる波長…、
遠く砂漠の地で飢えた幼な子を笑わせる波長、暗い病に伏す人を穏やかにする波長…。
そんな波長は分からない? いいや、そんなことはない。
人の努力は多様で無限であり、いくつもの可能性をもっている。
歌、ダンス、ピアノ、スポーツ、勉強、お笑い、恋愛…、あなたがどんなことに頑張っても、それに共感して感動する人がいる。
そして何よりもあなたの笑顔。あなたの笑顔はきっと人を笑顔にする。笑顔の光は誰もが放つことができ、そして誰もが受け止めることができるからだ。
辛いときはどうか耳を澄ませてほしい。遠くから何かが聞こえる。
誰かが誰かのために、鐘を鳴らしている。あなたの心はいつでもふるえられる。笑顔を見せに出てみよう。きっと誰かが笑顔で答えてくれる。
「よく聴いてごらん。自分と周りの出している音のほかに、もう一つ上の音が聞こえるでしょう?」と言われ、トランペットを吹きながら耳を澄ませた。バンド全員の音程が揃ったとき、確かにその音が聴こえた。「それが倍音だよ。完璧に共鳴したんだ。」
「美しい音楽というのはその倍音がたくさん含まれていて、意識していなくても聴く人の心に響くんだ。」と教わった。
大学の物理化学の講義では、「同じ波長・振動数をもつものは共鳴する。音だけでなく、遠くのテレビも足元の放射線も同じだ。共鳴するとエネルギーになる。」と学んだ。
赤外線が水分子に共鳴して、物を温める。紫外線が皮ふ細胞に共鳴して、日焼けする。
電波がテレビに共鳴して、番組が切り替わる。放射線がDNAに共鳴して、傷をつける。
自然界はエネルギーを保存しているが、その間は共鳴という現象が繋いでいる。
人間はどうだろう? (あぁ、人間は共感できる。)
頑張っている人を見て、自分も頑張ろうと思う。悲しんでいる人を見て、涙が溢れる。
怒りの声を聴いて、拳を振り上げる。周囲を笑顔にする人につられて、笑みがこぼれる。
人は感動を生み出し続けているが、その間は共感という心が繋いでいる。
自分はどうだろう? (自分からは逃げられない。)
あなたの隣にいる人は笑顔でいるだろうか?どうしたら笑顔にできるだろうか?何と声を掛けたら笑顔になるだろうか?
その人の波長に合わせて、その人の心をふるわせるにはどうしたらいいのだろう?
昨日を後悔して泣く人の涙を振り払う波長…、明日を憂え恐れる人を奮わせる波長…、
遠く砂漠の地で飢えた幼な子を笑わせる波長、暗い病に伏す人を穏やかにする波長…。
そんな波長は分からない? いいや、そんなことはない。
人の努力は多様で無限であり、いくつもの可能性をもっている。
歌、ダンス、ピアノ、スポーツ、勉強、お笑い、恋愛…、あなたがどんなことに頑張っても、それに共感して感動する人がいる。
そして何よりもあなたの笑顔。あなたの笑顔はきっと人を笑顔にする。笑顔の光は誰もが放つことができ、そして誰もが受け止めることができるからだ。
辛いときはどうか耳を澄ませてほしい。遠くから何かが聞こえる。
誰かが誰かのために、鐘を鳴らしている。あなたの心はいつでもふるえられる。笑顔を見せに出てみよう。きっと誰かが笑顔で答えてくれる。
協働学習とは何か調べてみた ― 2015/10/24

先日,研究授業を行い,その略案のなかで「協働学習」という言葉を使いました。
そしたら,他の先生に「協働」のところを「共同」へ直されました。
その先生が「協働学習」を知らないのか,自分が「協働学習」の使い方を間違っていたのか,判断はつかないです。
しかし,「じゃあ協働学習ってなに?」と聞かれても,字から想像する以上のきちんとした説明ができる自信がありません。
そこで,「協働学習」とは何か調べて,自分なりにまとめてみました。
【協働学習】
○文部科学省の定義
協働学習とは「子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び」でする。
学びのイノベーション事業の報告書では,具体的な活動として「タブレットPCや電子黒板等を活用し、教室内の授業や他地域・海外の学校との交流学習において子供同士による意見交換、発表などお互いを高めあう学びを通じて、思考力、判断力、表現力などを育成すること」
学びのイノベーション事業における協働学習の活動内容の分類
活動1 発表や話合い
:考えや作品を提示・交換しての発表や話合い
活動2 協働での意見整理
:複数の意見や考えを議論して整理
活動3 協働制作
:グループでの分担や協力による作品の制作
活動4 学校の壁を越えた学習
:遠隔地の学校等との交流
○大辞泉の定義
学習者が相互に協力しながら、共通の目標や課題の達成を目指す学習
【協同学習】
協同学習とは、小グループ(男女混合4人班を基本とする)でお互いに力 をあわせ、助け合いながら学習を進めていく集団学習
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://chigai-allguide.com/ より
共同と協同と協働は、複数の人や団体が事にあたるという意味で共通し、どの表記を用いても良い場合もあるが、使用する場面・ニュアンスの違いによって表記が限られたり、使い分けされることがある。
共同には、力を合わせて事を行うという意味のほか、同じ条件・資格で結合したり、関係するといった意味もある。
同じ条件で使用する意味の「共同トイレ」や「共同墓地」などに、「協同」や「協働」の表記は用いられない。
協同には、共に心と力を合わせて物事を行う意味があり、互いに協力するといった精神面を強調する際に用いられることが多い。
協同組合は、業者や消費者などが、事業や生活の改善を図るために組織される団体であるため、「協同」の表記が用いられる。
協働は、協力して働くという意味。
協同も協働も、同じ目的に向かって力を合わせ物事を行うという意味では同じだが、協同は役割分担などが事前に決まっていることが多いのに対し、協働はそれぞれができること、得意分野のことをする場合に用いられることが多い。
また、どちらも一緒に行動するとは限らないが、協同よりも協働の方が、より一緒に行動するという意味合いが強い。
(こんなサイトもあるんですね~,すごい!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ということでした。だいぶイメージがわきました。
特に文科省が定めている定義に沿っている場合には,協働学習という言葉を使っても差し支えなさそうです。
また,何が違うの?と言われたら,共同トイレと協同組合を引き合いに出せば伝わりそうな気がします。
やっぱりなんでも調べてみるものですね。
そしたら,他の先生に「協働」のところを「共同」へ直されました。
その先生が「協働学習」を知らないのか,自分が「協働学習」の使い方を間違っていたのか,判断はつかないです。
しかし,「じゃあ協働学習ってなに?」と聞かれても,字から想像する以上のきちんとした説明ができる自信がありません。
そこで,「協働学習」とは何か調べて,自分なりにまとめてみました。
【協働学習】
○文部科学省の定義
協働学習とは「子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び」でする。
学びのイノベーション事業の報告書では,具体的な活動として「タブレットPCや電子黒板等を活用し、教室内の授業や他地域・海外の学校との交流学習において子供同士による意見交換、発表などお互いを高めあう学びを通じて、思考力、判断力、表現力などを育成すること」
学びのイノベーション事業における協働学習の活動内容の分類
活動1 発表や話合い
:考えや作品を提示・交換しての発表や話合い
活動2 協働での意見整理
:複数の意見や考えを議論して整理
活動3 協働制作
:グループでの分担や協力による作品の制作
活動4 学校の壁を越えた学習
:遠隔地の学校等との交流
○大辞泉の定義
学習者が相互に協力しながら、共通の目標や課題の達成を目指す学習
【協同学習】
協同学習とは、小グループ(男女混合4人班を基本とする)でお互いに力 をあわせ、助け合いながら学習を進めていく集団学習
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://chigai-allguide.com/ より
共同と協同と協働は、複数の人や団体が事にあたるという意味で共通し、どの表記を用いても良い場合もあるが、使用する場面・ニュアンスの違いによって表記が限られたり、使い分けされることがある。
共同には、力を合わせて事を行うという意味のほか、同じ条件・資格で結合したり、関係するといった意味もある。
同じ条件で使用する意味の「共同トイレ」や「共同墓地」などに、「協同」や「協働」の表記は用いられない。
協同には、共に心と力を合わせて物事を行う意味があり、互いに協力するといった精神面を強調する際に用いられることが多い。
協同組合は、業者や消費者などが、事業や生活の改善を図るために組織される団体であるため、「協同」の表記が用いられる。
協働は、協力して働くという意味。
協同も協働も、同じ目的に向かって力を合わせ物事を行うという意味では同じだが、協同は役割分担などが事前に決まっていることが多いのに対し、協働はそれぞれができること、得意分野のことをする場合に用いられることが多い。
また、どちらも一緒に行動するとは限らないが、協同よりも協働の方が、より一緒に行動するという意味合いが強い。
(こんなサイトもあるんですね~,すごい!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ということでした。だいぶイメージがわきました。
特に文科省が定めている定義に沿っている場合には,協働学習という言葉を使っても差し支えなさそうです。
また,何が違うの?と言われたら,共同トイレと協同組合を引き合いに出せば伝わりそうな気がします。
やっぱりなんでも調べてみるものですね。
質問に来ないのは当たり前? ― 2015/07/15

「分からないところがあったら、いつでも質問に来なさい。」
と言っても、生徒は質問に来ないですね。
どうしてかなー?と考えていた時期がありました。
まず1つ目、「部活や委員会で忙しくて聞きに行けない。」
生徒にしてみれば、喉元を通りすぎた「分からないこと」よりも、目の前の部活や仕事に忙しいのです。
これは質問の時間を確保してあげれば、質問に来ます。
教科として授業時間中に設定するか、学年や学校として放課後に設定するか、とにかく安心して堂々と質問に来る時間を作ってあげます。
その2 「先生が忙しそうにしている。」
意外といそうなのが、このパターンです。気を使ってしまう子です。
生徒たちは先生のことをよく見ています。
先生の顔色や気持ちをよく見取っています。
生徒の前では,余裕のある姿を見せたいものです(実際にはできてない。)
その3 「何を聞いたらいいのか分からない。」
一番多いのがこのパターンです。
質問するということは、自分が何を分かっていないのか分かっているということです。
そこまで自分の理解度を判別できるなら、分からないことを理解することもできるはずです。
分からないことが分からない。分かっていないことが分かっていない。それが本当のところでしょう。
その4 「先生の教え方が合わないと思っている。」
これは塾に行っている生徒に当てはまるかもしれません。
塾で聞けばいいや。塾の先生のほうが分かりやすいし…。
そう思われたら悔しいですね。
自分で教えるときには、生徒に合わせた教え方を選ぶことが大切です。もちろんそれだけ教材理解が必要です。
同じことを教えるために、何パターンの話し方ができますか。
塾というのは、学習指導に特化した場所です。何も努力しなければ、塾のほうが分かりやすのは当然なのです。
先日、教材研究が一回り終わりました。
また1からスタートです。
夏休みの自分の課題です。
と言っても、生徒は質問に来ないですね。
どうしてかなー?と考えていた時期がありました。
まず1つ目、「部活や委員会で忙しくて聞きに行けない。」
生徒にしてみれば、喉元を通りすぎた「分からないこと」よりも、目の前の部活や仕事に忙しいのです。
これは質問の時間を確保してあげれば、質問に来ます。
教科として授業時間中に設定するか、学年や学校として放課後に設定するか、とにかく安心して堂々と質問に来る時間を作ってあげます。
その2 「先生が忙しそうにしている。」
意外といそうなのが、このパターンです。気を使ってしまう子です。
生徒たちは先生のことをよく見ています。
先生の顔色や気持ちをよく見取っています。
生徒の前では,余裕のある姿を見せたいものです(実際にはできてない。)
その3 「何を聞いたらいいのか分からない。」
一番多いのがこのパターンです。
質問するということは、自分が何を分かっていないのか分かっているということです。
そこまで自分の理解度を判別できるなら、分からないことを理解することもできるはずです。
分からないことが分からない。分かっていないことが分かっていない。それが本当のところでしょう。
その4 「先生の教え方が合わないと思っている。」
これは塾に行っている生徒に当てはまるかもしれません。
塾で聞けばいいや。塾の先生のほうが分かりやすいし…。
そう思われたら悔しいですね。
自分で教えるときには、生徒に合わせた教え方を選ぶことが大切です。もちろんそれだけ教材理解が必要です。
同じことを教えるために、何パターンの話し方ができますか。
塾というのは、学習指導に特化した場所です。何も努力しなければ、塾のほうが分かりやすのは当然なのです。
先日、教材研究が一回り終わりました。
また1からスタートです。
夏休みの自分の課題です。
つ「勉強をする意味が分からない。」 ― 2015/05/01

たしかに。
じゃあどうして食事を取るの?
ビタミン剤などの栄養剤を取ればいいではないか?
食事をする意味が分からない・・・?
生きていくのに必要な錠剤だけ飲んでいても,つまらないし,続かないよね。
食事だからこそ,楽しく続けられて,いつのまにか栄養を取ることができる。
だから,意味は分からないけど食事をしている。
人間として必要な生きていく方法は,そのままではつまらないし,続かない。
授業だからこそ,楽しく続けられて,いつのまにか身につけることができる。
だから,意味は分からなくても勉強をしている。
じゃあ,生きていく方法というのは何だろう?
じゃあ,人間として必要なものは何だろう?
答えは誰にも分からない。
だからみんな必死に勉強して生きている。
あなたもね。
じゃあどうして食事を取るの?
ビタミン剤などの栄養剤を取ればいいではないか?
食事をする意味が分からない・・・?
生きていくのに必要な錠剤だけ飲んでいても,つまらないし,続かないよね。
食事だからこそ,楽しく続けられて,いつのまにか栄養を取ることができる。
だから,意味は分からないけど食事をしている。
人間として必要な生きていく方法は,そのままではつまらないし,続かない。
授業だからこそ,楽しく続けられて,いつのまにか身につけることができる。
だから,意味は分からなくても勉強をしている。
じゃあ,生きていく方法というのは何だろう?
じゃあ,人間として必要なものは何だろう?
答えは誰にも分からない。
だからみんな必死に勉強して生きている。
あなたもね。




最近のコメント