【MM】一週間を振り返るために悩む ― 2016/07/01
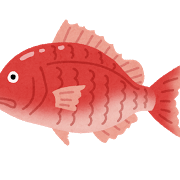
今回は「これまでの1週間」というマインドマップを描いてみました。
6/25(土)から7/1(金)までの1週間です。
月曜から日曜でも良かったのですが、描こうと思ったのが木曜日で、時間を取れたのが金曜の夜中だったので仕方ないですね。
でもこれはこれで、土日に来週の計画を立てたり、今週の足りなかった分を補ったりするのにいいかな、と思いました。
はじめに「センターイメージ」をどうしようか悩みました。
悩んだ末に、先日の二女の「お食い初め」でいただいた魚のキンキの素揚げの顔が浮かびました。
そんなわけで,真ん中に魚の絵を茶色のペンで描きました。
次にBOI(Basic Ordering Idea = キーコンセプト,基本アイデア)となるブランチも迷いました。
7本のブランチを伸ばして7日間の日付を割り当てることも考えました。
しかし、日付では安直だし、ポリシーも感じられません。
単なる記録ではなく、そこから何かを見つけるために振り返るわけですから、何か価値ある言葉を割り当てたいと思います。
他に考えたのは「自分の役割」です。
「父親」「旦那」「担任」「顧問」「現職主任」「情報担当」「個人」
なんかが主な役割でしょうか。深く探れば「息子」「地球人」とかありそうです。
それぞれの立場で何をしたのか振り返ればいいわけです。
もう一つ考えたのは「ミッション・ステートメント」です。
「笑顔」「感動」「実感」「納得」「自然」「未来」「バランス」
この7つが自分の最重要価値項目として挙がっています。
この価値に対して自分が何をしたのか振り返るのです。
最後に考えたのは「とりあえず思いついたこと」です。
実際にはこれをBOIにして書いてしまいました。
「家族」「部活」「読書」「仕事」「対人」
という何だかレベルの違うものを挙げながら描き進めました。
しかし,意外とこれが良かったのか,スラスラと書いていくことができました。
前回同様に絵を描いたり,英単語を書いたりしました。楽しいです。
今回はクラウドも書いてみました。この効果は分かりません…汗
反対に破裂音の吹き出しを使って,できなかったことを強調したほうが反省になっていいです。
それから矢印(→)でつなぐということもしてみました。
意外と枝先に来ると同じ単語を書いていたりして,この週はこれがテーマだったんだな,などと気が付きました。
例えば「お礼」「伝える」「寄り添う」などです。
こんなことを書きながら,頭の中では様々なことを考えました。
やはり,マインドマップを書き終わったら、そこからの新たな気づきを文にしてメモすることが大切だと思いました。
忘れないうちにEvernoteに記入しました。マインドマップをスキャナで取り込んで,合わせて保存しておくといいのでしょう。
マインドマップの描き方も,活用の仕方も,まだまだこれからだと思いますが,続けてみます。
【MM】一週間を振り返っての学び ― 2016/07/02

昨日のマインドマップから,振り返って気が付いたことのメモです。個人名は消しておきます。
もっと時間を掛ければもっともっと見つかるのでしょうが,それよりも大切なことは,どのようなアクション(改善)を取るかだと思います。
自分の中でPDCAが回ればいいな~なんて思いました。
1. 立志式の作文の添削、教材研究としての教科書読み、期末テスト作りでの問題の確認、すべてにおいて「やったあとのフォロー」が足りていない。
→ その時間をとっていないから、これからはその時間も確保するようにする。
2. 短い時間での読書はした。特にノート術に関する本を読んだ。『「結果を出す人」は ノートに何を 書いているのか』は面白かった。28日には図書館に行って本を借りてきた。モレスキンの本が面白い。
→ 自分が関心のあることなら読書の時間を見つけるんだな。教科書に関心を持てばいい。
3. 生徒の母親から慰労会の案内をもらった。そこに一言お礼が書いてあってうれしかった。結婚記念日で嫁ちゃんにお礼を言ったり,防犯教室で犯人役の先生にお礼を言ったり,タブレットのことで来てもらった指導主事の先生にお礼を言ったりした。
→ お礼を伝えることは大切だ。もっともっと「ありがとうございます」が言えるようになろう。特に嫁ちゃんには感謝の気持ちを伝えるように心がけよう。
4. 立志式に向けて学級を進めたいのに,自分が添削をしていないために進まない。1名は居残りのあと部活に行かずに帰ってしまった。
→ どうやったら先生の気持ちが伝わるのか。もっと話し方を工夫する。生徒のことを理解する。寄り添った指導をしてあげたい。
寄り添う=甘い,ではないはず。
5. お食い初めだった。二女のために,長女のために,嫁ちゃんのために,それぞれできることを常に意識しよう。
→ 自分の仕事と同じように,きちんと時間を配分して,やってあげたいことがやってあげられるようにしよう。遅くてもこれから取り掛かる。
もっと時間を掛ければもっともっと見つかるのでしょうが,それよりも大切なことは,どのようなアクション(改善)を取るかだと思います。
自分の中でPDCAが回ればいいな~なんて思いました。
1. 立志式の作文の添削、教材研究としての教科書読み、期末テスト作りでの問題の確認、すべてにおいて「やったあとのフォロー」が足りていない。
→ その時間をとっていないから、これからはその時間も確保するようにする。
2. 短い時間での読書はした。特にノート術に関する本を読んだ。『「結果を出す人」は ノートに何を 書いているのか』は面白かった。28日には図書館に行って本を借りてきた。モレスキンの本が面白い。
→ 自分が関心のあることなら読書の時間を見つけるんだな。教科書に関心を持てばいい。
3. 生徒の母親から慰労会の案内をもらった。そこに一言お礼が書いてあってうれしかった。結婚記念日で嫁ちゃんにお礼を言ったり,防犯教室で犯人役の先生にお礼を言ったり,タブレットのことで来てもらった指導主事の先生にお礼を言ったりした。
→ お礼を伝えることは大切だ。もっともっと「ありがとうございます」が言えるようになろう。特に嫁ちゃんには感謝の気持ちを伝えるように心がけよう。
4. 立志式に向けて学級を進めたいのに,自分が添削をしていないために進まない。1名は居残りのあと部活に行かずに帰ってしまった。
→ どうやったら先生の気持ちが伝わるのか。もっと話し方を工夫する。生徒のことを理解する。寄り添った指導をしてあげたい。
寄り添う=甘い,ではないはず。
5. お食い初めだった。二女のために,長女のために,嫁ちゃんのために,それぞれできることを常に意識しよう。
→ 自分の仕事と同じように,きちんと時間を配分して,やってあげたいことがやってあげられるようにしよう。遅くてもこれから取り掛かる。
【文具】ネオクリッツフラットってどうなん…? ― 2016/07/03

筆記用具を入れているのに、フラットにすることってあるの?
流通段階ではかさ張らなくていいというメリットはありそうだけど、
購入者のメリットが分からないんですが…。
女子とは文房具トークをがんばっています(笑)
追記・・・
文句言っているわけではないのですが,気になって使用者のブログを読みました。
ネオクリッツの底面は固いため,フラットになるぶん嵩張らないということのようです。内容量も増えているようです。
文房具ほしいな~。(具体性はないw)
流通段階ではかさ張らなくていいというメリットはありそうだけど、
購入者のメリットが分からないんですが…。
女子とは文房具トークをがんばっています(笑)
追記・・・
文句言っているわけではないのですが,気になって使用者のブログを読みました。
ネオクリッツの底面は固いため,フラットになるぶん嵩張らないということのようです。内容量も増えているようです。
文房具ほしいな~。(具体性はないw)
【MM】笑顔で過ごすためのマインドマップ ― 2016/07/07

今日、参観させていただいた先生は、授業のときはニコニコしていらっしゃる先生でした。
もちろん授業も楽しそうにやっています。そうなれば当然生徒達も楽しそうに授業を受けています。
細かなテクニックや、今までとちがう授業展開といった、新しい気付きもありましたが、何よりも笑顔が印象的でした。
自分自身の授業では、つい授業規律をキープするためであったり、授業進度の焦りもあったりして、ピリピリしていることがあります。
そういうときは生徒の反応もイマイチです。質問してもパッと返ってこないし、発問してもンッ!という反応がありません。
自分が楽しめていないから生徒も楽しくないだろうなと思って、分かってはいます。でも直せない…。
次の日も研修で頑張らなくてはいけないというのに、5時に起き上がって、おもむろにマインドマップを書きはじめました。
テーマは「いつも笑顔で過ごすために」です。
「笑顔」というキーワードは、実は自分のミッションステートメントのはじめに挙げている項目なのです。
「笑顔」は授業だけでなく、教室でも職員室でも、家庭でも、どこででも大切にしようと思っています。それなのにできていない。何とかしようという気持ちが働いて寝ていられませんでした。
センターイメージに「笑顔で過ごす」と書いて、笑った雲を描き、いつでもの意味で太陽や月を描きました。また幸せのクローバーも添えました。
またBOIに悩んだのですが、「学校で」「家で」「心」「体」の4つになりました。
マインドマップは中間生成物ですので、詳細は書きません。画像としてアップするといいのかな?
以下、マップからの気付きを成果として挙げておきます。
「いつも笑顔で過ごすために」
① 1日の半分を過ごしている学校で笑顔でいられるようにする。
授業でも教室でも部活でも、生徒一人一人のことをよく見て小さな変化に気付いて褒めてあげる。生徒に笑顔が生まれれば、自分も笑顔になれる。
ただ褒めるのではなく、大いに褒める。それぐらいの意識がないと、自分は変われない。朝と帰りにほめることで、希望や見通しをもたせることができる。
叱るときも必要だけど、そのルールや基準をはっきりさせておく。
どれくらい褒めたか、自分自身の成長のためにも記録を取っていく。褒め言葉を集めたり、シールやスタンプも活用していく。
② 家でも家族が笑顔で過ごせるように心掛ける。
自分から話題を見つけたり、イベントを提案したり、ときには計画的にサプライズをしかける。(やられてばかりじゃダメ)もちろん子供とは全力で遊ぶ。
アンテナを高くして情報を集めるとともに、実現できるように休みを上手にとっていく。
自分一人のときも、時間をムダにしなように、書斎でやることと家事としてやることをテキパキやるようにする。
③ 笑顔でいるためには体も大切。健康に過ごし、若さを保つためにも、食事や睡眠といったライフログを活用するようにする。
疲れていないときには、それをキープするために筋トレやストレッチをする。疲れているときには、リフレッシュを考える。瞑想なんかもいいかも。
④ 笑顔でいるためには、心も大切。
ポジティブでいるために時間的な余裕を生み出す。そのためにライフハックを活用していく。
ネガティブになったときのスイッチをたくさん持つようにする。NLPやアドラー心理学を活用する。
心残りは後悔に繋がるので、1日1日を大切に過ごす。
明るさは周りを照らし、跳ね返って自分にも笑顔を生み出す。笑顔のキャッチボールができるように、笑顔を返す癖付けと、自然な笑顔を鏡でチェックする習慣をつける。
以上、こんなところです。
3回目のマインドマップ。描くのに40分かかりました。成文化するのに20分ですかね。一時間かけた甲斐はあったように思います。
マップも少しは上手になってきたかな?またそのうちチャレンジしてみます。
もちろん授業も楽しそうにやっています。そうなれば当然生徒達も楽しそうに授業を受けています。
細かなテクニックや、今までとちがう授業展開といった、新しい気付きもありましたが、何よりも笑顔が印象的でした。
自分自身の授業では、つい授業規律をキープするためであったり、授業進度の焦りもあったりして、ピリピリしていることがあります。
そういうときは生徒の反応もイマイチです。質問してもパッと返ってこないし、発問してもンッ!という反応がありません。
自分が楽しめていないから生徒も楽しくないだろうなと思って、分かってはいます。でも直せない…。
次の日も研修で頑張らなくてはいけないというのに、5時に起き上がって、おもむろにマインドマップを書きはじめました。
テーマは「いつも笑顔で過ごすために」です。
「笑顔」というキーワードは、実は自分のミッションステートメントのはじめに挙げている項目なのです。
「笑顔」は授業だけでなく、教室でも職員室でも、家庭でも、どこででも大切にしようと思っています。それなのにできていない。何とかしようという気持ちが働いて寝ていられませんでした。
センターイメージに「笑顔で過ごす」と書いて、笑った雲を描き、いつでもの意味で太陽や月を描きました。また幸せのクローバーも添えました。
またBOIに悩んだのですが、「学校で」「家で」「心」「体」の4つになりました。
マインドマップは中間生成物ですので、詳細は書きません。画像としてアップするといいのかな?
以下、マップからの気付きを成果として挙げておきます。
「いつも笑顔で過ごすために」
① 1日の半分を過ごしている学校で笑顔でいられるようにする。
授業でも教室でも部活でも、生徒一人一人のことをよく見て小さな変化に気付いて褒めてあげる。生徒に笑顔が生まれれば、自分も笑顔になれる。
ただ褒めるのではなく、大いに褒める。それぐらいの意識がないと、自分は変われない。朝と帰りにほめることで、希望や見通しをもたせることができる。
叱るときも必要だけど、そのルールや基準をはっきりさせておく。
どれくらい褒めたか、自分自身の成長のためにも記録を取っていく。褒め言葉を集めたり、シールやスタンプも活用していく。
② 家でも家族が笑顔で過ごせるように心掛ける。
自分から話題を見つけたり、イベントを提案したり、ときには計画的にサプライズをしかける。(やられてばかりじゃダメ)もちろん子供とは全力で遊ぶ。
アンテナを高くして情報を集めるとともに、実現できるように休みを上手にとっていく。
自分一人のときも、時間をムダにしなように、書斎でやることと家事としてやることをテキパキやるようにする。
③ 笑顔でいるためには体も大切。健康に過ごし、若さを保つためにも、食事や睡眠といったライフログを活用するようにする。
疲れていないときには、それをキープするために筋トレやストレッチをする。疲れているときには、リフレッシュを考える。瞑想なんかもいいかも。
④ 笑顔でいるためには、心も大切。
ポジティブでいるために時間的な余裕を生み出す。そのためにライフハックを活用していく。
ネガティブになったときのスイッチをたくさん持つようにする。NLPやアドラー心理学を活用する。
心残りは後悔に繋がるので、1日1日を大切に過ごす。
明るさは周りを照らし、跳ね返って自分にも笑顔を生み出す。笑顔のキャッチボールができるように、笑顔を返す癖付けと、自然な笑顔を鏡でチェックする習慣をつける。
以上、こんなところです。
3回目のマインドマップ。描くのに40分かかりました。成文化するのに20分ですかね。一時間かけた甲斐はあったように思います。
マップも少しは上手になってきたかな?またそのうちチャレンジしてみます。
新しいプリンターが欲しい ― 2016/07/09

どうしてと言われると強い理由がないので,即却下されるのは承知の上で記事にします。
エプソンのEP-805Aを使っています。
かつてはCanon派だったのですが,写真の画質が上がるにつれてEPSON派になってきました。
昔はPM-4000PXなんていう名機も持っていました。激遅だったけど。。。
普段使いで,EP-805Aに特に不満はありません。
印刷品質も十分です。写真も文書も不満はありません。ランニングコストなんて,他のと比べてもどんぐりだから気にしていません。
CD/DVDのラベル印刷も年に数回はお世話になっています。先日もクラス全員に配るDVDのラベルを印刷しました。
スキャナはScanSnap S1500があるのでめったに使いませんが,その品質もスピードも特に不満はありません。
では,なぜ新しいのが欲しいのか。理由は3つ。
その1 「ときどきA3がしたい。」
CMの影響を受けまくっていますね。
教材として掲示資料を作りたいな~なんて思うと,インパクトのあるA3サイズで出したくなります。
ただ,学校に行けばカラーインクジェットもあるし,モノクロレーザーもあるし,コピー機もあります。
自分で家で作りたい,というところさえ我慢すれば,学校で好きなだけできるのです。(無駄にやったら怒られそうだけど)
その2 「A3でスキャナしたい。」
その1からすると,ほぼ自動的にエプソンの「EP-978A3」が候補に挙がります。
しかし,ちょっと調べたところによると,スキャナとしてはA4サイズなんですね。
A3の原稿は,A4サイズで3回(左右真ん中)スキャンして合成することで,A3読み取りをしているそうです。
ScanSnapS1500も,A3の読み取りは専用フォルダに挟むという手間がかかっていやだったのですが,どちらも手間だと分かりました。
だったら学校で縮小コピーしてからスキャンするというズルをしても同じです。
めったにやらないA3スキャンだからこそ,簡単にできたらと期待したのですがね。。。
その3 「A4からA5に縮小コピーできない」
EP-805Aを使っていても,しばらくこのことに気が付きませんでした。
プリンター単体で,A4をA5に縮小コピーしようとすると,用紙選択にA5がないので,手動で71%にしてやっていました。
しかもA4用紙にやって,それをカッターでA5に切り抜くという手間もかかっていました。
特にそこに不満はなかったのです。A5なんてめったに使う人いないもんな。オレのわがままだよな,と思っていたのです。
しかし違いました。トレイにはA5という位置があるのです。そしてパソコン上からはA5サイズで印刷できるのです。
プリンター単体でA5に印刷ができないというだけです。どうしてでしょう?A4→B5ができて,A4→A5ができない理由が分かりません。メーカーの怠慢です。
そう気付いて,不満に思い始めて,最近の機種を見てみると,ちゃんとプリンター単体でA4→A5にできるようになっていました。
A5のシステム手帳を使っている関係で,けっこうA4→A5は使いたいのです。
これだけでも買い替える理由にはなります。できなかったことができるようになるというのはワクワクしますね。
ただパソコンがあればできると分かっているのに,お金をかけたくないな。。。
ただ結局は,EP-978A3の約¥26000もEP-808ABの約¥14000も払えず,今のプリンターのインクをもう一箱買ってきてしまいました。
インクがあるうちは,決断を先送りできます。都合よく壊れたら,そのときは上記2機種で検討します。
それまではこいつ(EP-805AB)を使い込んでいきます。
エプソンのEP-805Aを使っています。
かつてはCanon派だったのですが,写真の画質が上がるにつれてEPSON派になってきました。
昔はPM-4000PXなんていう名機も持っていました。激遅だったけど。。。
普段使いで,EP-805Aに特に不満はありません。
印刷品質も十分です。写真も文書も不満はありません。ランニングコストなんて,他のと比べてもどんぐりだから気にしていません。
CD/DVDのラベル印刷も年に数回はお世話になっています。先日もクラス全員に配るDVDのラベルを印刷しました。
スキャナはScanSnap S1500があるのでめったに使いませんが,その品質もスピードも特に不満はありません。
では,なぜ新しいのが欲しいのか。理由は3つ。
その1 「ときどきA3がしたい。」
CMの影響を受けまくっていますね。
教材として掲示資料を作りたいな~なんて思うと,インパクトのあるA3サイズで出したくなります。
ただ,学校に行けばカラーインクジェットもあるし,モノクロレーザーもあるし,コピー機もあります。
自分で家で作りたい,というところさえ我慢すれば,学校で好きなだけできるのです。(無駄にやったら怒られそうだけど)
その2 「A3でスキャナしたい。」
その1からすると,ほぼ自動的にエプソンの「EP-978A3」が候補に挙がります。
しかし,ちょっと調べたところによると,スキャナとしてはA4サイズなんですね。
A3の原稿は,A4サイズで3回(左右真ん中)スキャンして合成することで,A3読み取りをしているそうです。
ScanSnapS1500も,A3の読み取りは専用フォルダに挟むという手間がかかっていやだったのですが,どちらも手間だと分かりました。
だったら学校で縮小コピーしてからスキャンするというズルをしても同じです。
めったにやらないA3スキャンだからこそ,簡単にできたらと期待したのですがね。。。
その3 「A4からA5に縮小コピーできない」
EP-805Aを使っていても,しばらくこのことに気が付きませんでした。
プリンター単体で,A4をA5に縮小コピーしようとすると,用紙選択にA5がないので,手動で71%にしてやっていました。
しかもA4用紙にやって,それをカッターでA5に切り抜くという手間もかかっていました。
特にそこに不満はなかったのです。A5なんてめったに使う人いないもんな。オレのわがままだよな,と思っていたのです。
しかし違いました。トレイにはA5という位置があるのです。そしてパソコン上からはA5サイズで印刷できるのです。
プリンター単体でA5に印刷ができないというだけです。どうしてでしょう?A4→B5ができて,A4→A5ができない理由が分かりません。メーカーの怠慢です。
そう気付いて,不満に思い始めて,最近の機種を見てみると,ちゃんとプリンター単体でA4→A5にできるようになっていました。
A5のシステム手帳を使っている関係で,けっこうA4→A5は使いたいのです。
これだけでも買い替える理由にはなります。できなかったことができるようになるというのはワクワクしますね。
ただパソコンがあればできると分かっているのに,お金をかけたくないな。。。
ただ結局は,EP-978A3の約¥26000もEP-808ABの約¥14000も払えず,今のプリンターのインクをもう一箱買ってきてしまいました。
インクがあるうちは,決断を先送りできます。都合よく壊れたら,そのときは上記2機種で検討します。
それまではこいつ(EP-805AB)を使い込んでいきます。
【文具】スタイルフィットのペンを入れ替える ― 2016/07/11

先日,すごい久しぶりにヨドバシに行ってきました。
何も買えないのに指をくわえて見ているだけだったのですが,くやしくてパソコン・家電ではなく,文房具を買ってきました。
先日から使い始めた,スタイルフィットの残りの色たちです。
ホルダーは3本とも5色タイプです。
ミッキーグローブとドナルドを持っていましたが,3本目はミニーリボンではなく,限定セサミロゴにしました。
というのも,ペンケースに入れたときに,ミッキーとミニーが同じ黒い軸で分かりづらいと思ったからです。
レッドエルモがなくてセサミロゴでしたが,それでも軸が赤いので,3本の区別がつきやすくなりました。
そしてその中の色を少し入れ替えました。
「ノックの部分を油性マッキーで染めると,何色が分かっているか分かりやすい。」というアイデア(ハック)がありましたが,いまだにやっていません。
思いついたのは,クリップがあるので,そのクリップに差してあるのが一番使う色にすることです。
そしてクリップの右側が2番目に使う色,左側が3番目に使う色,という感じでクリップを中心に覚えておけばいいのだと気が付いたのです。
というわけで,あらためて紹介します。
色の意味は,いちおう程度で,絶対的なルールにはしていません。
気分で使い分けている緩さがあります。
「ミッキーグローブ」(軸=黒)…メイン5色
クリップから右回りに…
ブルーブラック …メモのほとんどはこの色
レッド …1番大事なこと,チェックするとき
バイオレット …生徒のこと,子供のこと
ブラック …基本ですよね
ブルー …2番目に大事なこと,ブルーブラックの代理
「ドナルド」(軸=青)…サブ5色
クリップから右回りに…
ライトブルー …自分のこと,日記
ピンク …嫁ちゃんのこと
オレンジ …ほめ日記,感謝の気持ち
ブラウンブラック …メモへの追記
グリーン …部活,PTA
「セサミロゴ」(軸=赤)…オマケ5色
クリップから右回りに…
ゴールデンイエロー
マンダリンオレンジ
ベビーピンク
ローズピンク
ライムグリーン
というわけで,持っていないのはスカイブルーだけとなりました。
16色あるので,どうしても1色余るのですが,私の中でそれはスカイブルーでした。
スカイブルーは色が薄くて見づらいので,もともと使わない色なのでいいかなと思っています。
何も買えないのに指をくわえて見ているだけだったのですが,くやしくてパソコン・家電ではなく,文房具を買ってきました。
先日から使い始めた,スタイルフィットの残りの色たちです。
ホルダーは3本とも5色タイプです。
ミッキーグローブとドナルドを持っていましたが,3本目はミニーリボンではなく,限定セサミロゴにしました。
というのも,ペンケースに入れたときに,ミッキーとミニーが同じ黒い軸で分かりづらいと思ったからです。
レッドエルモがなくてセサミロゴでしたが,それでも軸が赤いので,3本の区別がつきやすくなりました。
そしてその中の色を少し入れ替えました。
「ノックの部分を油性マッキーで染めると,何色が分かっているか分かりやすい。」というアイデア(ハック)がありましたが,いまだにやっていません。
思いついたのは,クリップがあるので,そのクリップに差してあるのが一番使う色にすることです。
そしてクリップの右側が2番目に使う色,左側が3番目に使う色,という感じでクリップを中心に覚えておけばいいのだと気が付いたのです。
というわけで,あらためて紹介します。
色の意味は,いちおう程度で,絶対的なルールにはしていません。
気分で使い分けている緩さがあります。
「ミッキーグローブ」(軸=黒)…メイン5色
クリップから右回りに…
ブルーブラック …メモのほとんどはこの色
レッド …1番大事なこと,チェックするとき
バイオレット …生徒のこと,子供のこと
ブラック …基本ですよね
ブルー …2番目に大事なこと,ブルーブラックの代理
「ドナルド」(軸=青)…サブ5色
クリップから右回りに…
ライトブルー …自分のこと,日記
ピンク …嫁ちゃんのこと
オレンジ …ほめ日記,感謝の気持ち
ブラウンブラック …メモへの追記
グリーン …部活,PTA
「セサミロゴ」(軸=赤)…オマケ5色
クリップから右回りに…
ゴールデンイエロー
マンダリンオレンジ
ベビーピンク
ローズピンク
ライムグリーン
というわけで,持っていないのはスカイブルーだけとなりました。
16色あるので,どうしても1色余るのですが,私の中でそれはスカイブルーでした。
スカイブルーは色が薄くて見づらいので,もともと使わない色なのでいいかなと思っています。
【アプリ】iPad「Duet Display」をダウンロード ― 2016/07/12
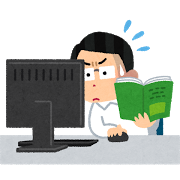
iPadをなんとか仕事に活用できないかと,いつも思っています。
学校のネットワークはセキュリティが厳しくクラウドサービスにつながらないので,Evernoteが使えないのが最高に痛いのです。
それでも諦めずに検討を続けていました。
そして先日のテストつくりのときに,学校でもデュアルディスプレイで仕事がしたいな~と思ったのです。
あのときは職員室のデスクトップパソコンのディスプレイを勝手に外して自分のデスクに持って行って実現したのですが,それは休みで誰もいなかったからできたこと。
そこで何とかiPadを使えないかな~と調べてみました。
そしたらちゃんとありました。
無料,有料それぞれいくつかありました。
無料アプリで試したいところですが,お試し期間があるものや,数分ごとに再接続をさせて有料に促すものなど,さまざまです。
Wi-Fiを使う無線形式のものや,USBケーブルでつなぐ有線のものもありました。学校では無線が使えませんから有線しか考えられません。
そんなわけで,悩むのもバカらしくなってきて,最初からしっかりした有料アプリを購入しました。
見つけたのは,『Duet Display』というアプリです。
使い方はいたって簡単。
iPadにアプリをダウンロード・インストールします。
パソコンにサイトから専用ソフトをダウンロード・インストールします。
あとはUSBでつなぐだけです。まもなくiPadを拡張ディスプレイとして認識して扱えます。
背景はもちろん,マウスのカーソルが動きまわり,普通にディスプレイとして使えることが不思議でなりません。便利に使えそうです。
唯一のネックは,アプリが\2400と高価なところですね。最初は\1200だったようですが,2倍に高騰しています。物価の変動の影響もあると思いますが,それくらい便利だということでしょう。
学校でもソフトのダウンロードとインストールがなんとかできました。試しにつないでみたら,ちょっと挙動不審になりながらも,デュアルディスプレイになることを確認しました。
周りの目がちょっと気になりますが,夏休みに積極的に使ってみようと思います。
http://www.duetdisplay.com/jp/
学校のネットワークはセキュリティが厳しくクラウドサービスにつながらないので,Evernoteが使えないのが最高に痛いのです。
それでも諦めずに検討を続けていました。
そして先日のテストつくりのときに,学校でもデュアルディスプレイで仕事がしたいな~と思ったのです。
あのときは職員室のデスクトップパソコンのディスプレイを勝手に外して自分のデスクに持って行って実現したのですが,それは休みで誰もいなかったからできたこと。
そこで何とかiPadを使えないかな~と調べてみました。
そしたらちゃんとありました。
無料,有料それぞれいくつかありました。
無料アプリで試したいところですが,お試し期間があるものや,数分ごとに再接続をさせて有料に促すものなど,さまざまです。
Wi-Fiを使う無線形式のものや,USBケーブルでつなぐ有線のものもありました。学校では無線が使えませんから有線しか考えられません。
そんなわけで,悩むのもバカらしくなってきて,最初からしっかりした有料アプリを購入しました。
見つけたのは,『Duet Display』というアプリです。
使い方はいたって簡単。
iPadにアプリをダウンロード・インストールします。
パソコンにサイトから専用ソフトをダウンロード・インストールします。
あとはUSBでつなぐだけです。まもなくiPadを拡張ディスプレイとして認識して扱えます。
背景はもちろん,マウスのカーソルが動きまわり,普通にディスプレイとして使えることが不思議でなりません。便利に使えそうです。
唯一のネックは,アプリが\2400と高価なところですね。最初は\1200だったようですが,2倍に高騰しています。物価の変動の影響もあると思いますが,それくらい便利だということでしょう。
学校でもソフトのダウンロードとインストールがなんとかできました。試しにつないでみたら,ちょっと挙動不審になりながらも,デュアルディスプレイになることを確認しました。
周りの目がちょっと気になりますが,夏休みに積極的に使ってみようと思います。
http://www.duetdisplay.com/jp/
【図書館】モレスキン 「伝説のノート」活用術 ― 2016/07/15

モレスキン 「伝説のノート」活用術~記録・発想・個性を刺激する75の使い方
(堀 正岳,中牟田 洋子/ダイヤモンド社)
を読みました。
本書の内容は、特にモレスキンに拘らなくても、ダイソーのダイスキンでも、何ででもできそうな気がします。
モレスキン愛が強すぎて、モレスキン最大のメリットは、硬い表紙だけなのではないかとさえ思えてきます。
私はモレスキンを使う気も買う気もありません。あくまでも自分のシステム手帳で使えそうなネタがないかなと思い読んでみました。
参考になったことと感想
その1 「ユビキタス・キャプチャー」
その時の事実と感想を残す。いつでもどこでもどんなことでも。 フォーマットを複数用意して、時間的に書ける量を考えて使うようにする。
そのとおりで,とにかく書き残すことが大切ですね。何としてでも。今の課題は休日の記録を残すことです。どうしても子供最優先で,記録は後回しになっているので。
その2 「毎日レビュー,週次レビュー」
週次レビューが習慣化しない自分にとって,少しは刺激になりました。
ユビキタス・キャプチャーと毎日レビューにはゼロ秒思考を使い,週次レビューはマインドマップで行いたいと考えています。
マインドマップについては,もっと書いて考えてみる必要があります。週末にその時間を取るのが至難の業です。
その3 「ハイパーリンクをはる」
一冊のなかで行ったり来たりするために、ページ番号を振るだけでなく、ページ見開きを4つのエリア(ABCD)に分けて、p39Aのように書かれている場所がおおよそ分かるようにする。
面白いことするな~と思いました。システム手帳ならばそのまま入れ替えれば済みます。ハイパーリンクやスレッド表示で行ったり来たりするほうがはるかに面倒だと思うのですがね。
その4 「タグ付け」「アイコン表示」
このへんはシールやスタンプでやりたいですね。自分なりに工夫してみようと思います。
ただこういった文具を使う時というのは,将来的にも入手可能なのかと考えてしまうんですよね。
新しいものに飛びつくよりも,既存のものを活用するようにします。
その5 「索引づくり」
たしかにあったほうがいいんですけどね,面倒なんですよね。あとで書きますが,いまは月に1回月間リフィルでやるようにしています。
そんな感じです。特に目新しい部分は少ないですね。
分かっちゃいるけどやっていない,やってみたいけどできていない,という部分を,もう一度背中を押された感じがします。
ブログで自分の手帳の使い方を紹介できたらいいな,なんて思いました。そのうちやります。そのうち…。
【目次】
はじめに あなたの脳を「拡張」するノート
なぜ紙のノートでなくてはいけないのか?
「外部の脳」にふさわしいモレスキンノート
人生を豊かにする一冊へ
第1章 なぜ、モレスキンノートが選ばれるのか
モレスキンノートとは何か?
基本とラインナップ
経験を蓄積する「手帳」としての使い方
なぜ、モレスキンノートが選ばれるのか?
「自由」を愛する精神
デジタルツールとの使い分け
はじめて書き込んでみる
第2章 モレスキンノートに人生を入れる
忘れるよりも早く記録するユビキタス・キャプチャー
ユビキタス・キャプチャーの基本ルール
ユビキタス・キャプチャーの形式
キャプチャーによって文体と文章量も選ぶ
吹き出しアイコンであえて制限を加える
素早いメモにはロディアを使う
感情をとらえる書き方をマスターする
つらい出来事もすべて書き込むメリット
一番大切なキャプチャーをとらえそこねない
ラベルシールで画像を取り込む
スタンプを利用して記入に近道を作る
ユビキタス・キャプチャーをマスターする
第3章 モレスキンノート「3ステップ活用法」
モレスキンノートを活用する3ステップ
「毎日レビュー」で情報を立ち上がらせる
毎日レビューの進め方
ページとページをつなぐ「ハイパーリンク」
ページの検察性を上げるための「タグづけ」
「カテゴリ分け」で流れを作る
「アイコン表示」でページの雰囲気を一瞬で伝える
ページを「拡張」する
週に一度、情報のつながりをレビューする
「週次レビュー」で情報を永続化する
一瞬で重要な情報を引き出せる「索引作り」
「スレッド表示」で断片的なキャプチャーを一カ所に集約する
開かなくても中身が見えるようにする工夫
「メタノート」で散らばった情報を集めていく
Evernoteを利用してモレスキンノートをデジタル化
仕上げに背表紙に銘を入れる
過去のノートが今の自分を助けてくれる
第4章 モレスキンノート「ビジネス活用術」
システム手帳を「卒業」しよう
「できる人」は自分の手帳を作る
自分に合ったダイアリーを選ぶ
ミニシステム手帳に作り変える
デイリーダイアリーで「時間トラッキング」
「行動メニュー」で無理なく分単位で時間を活用する
デジタルツールを連携させる書き方
モレスキンノートで「 GTDシステム」を作る
リポーターで「今やるべきこと」を書き留める
メモポケットに情報カードを入れて「To Do管理」をする
目標と常に向き合える仕組み作り
偶然の出会いからアイデアを生み出すヒント
フォリオノートで毎日一枚のマインドマップを描く
フォリオフォルダーを仕事のブリーフケースにする
第5章 モレスキンノート「生活活用術」
モレスキンノートの使い方に制限を加えない
絵日記をつける
万年筆と文字で日記をつける
交換ノートをする
読書日記をつける
フォトアルバムを作る
トラベルノートを作る
コレクションブックを作る
レシピブックを作る
スケッチをする
イベントめぐりを記録する
グルメめぐりを記録する
健康を記録する
単語帳を作る
第6章 モレスキンノート「DIYカスタマイズ術」
世界でただ一つのノートを作る
ペンをどうやって持ち歩く?
しおり紐をカスタマイズする
表紙をデコレーションする
カバーをつける
拡張ポケットに窓をつける
財布にして持ち歩く
ハードカバー+三冊カイエと二ヴォラン
MSKを利用する
ダイアリーに日本の祝日を書き込む
保存方法を工夫する
第7章 モレスキンノートと相性のいい文房具
(堀 正岳,中牟田 洋子/ダイヤモンド社)
を読みました。
本書の内容は、特にモレスキンに拘らなくても、ダイソーのダイスキンでも、何ででもできそうな気がします。
モレスキン愛が強すぎて、モレスキン最大のメリットは、硬い表紙だけなのではないかとさえ思えてきます。
私はモレスキンを使う気も買う気もありません。あくまでも自分のシステム手帳で使えそうなネタがないかなと思い読んでみました。
参考になったことと感想
その1 「ユビキタス・キャプチャー」
その時の事実と感想を残す。いつでもどこでもどんなことでも。 フォーマットを複数用意して、時間的に書ける量を考えて使うようにする。
そのとおりで,とにかく書き残すことが大切ですね。何としてでも。今の課題は休日の記録を残すことです。どうしても子供最優先で,記録は後回しになっているので。
その2 「毎日レビュー,週次レビュー」
週次レビューが習慣化しない自分にとって,少しは刺激になりました。
ユビキタス・キャプチャーと毎日レビューにはゼロ秒思考を使い,週次レビューはマインドマップで行いたいと考えています。
マインドマップについては,もっと書いて考えてみる必要があります。週末にその時間を取るのが至難の業です。
その3 「ハイパーリンクをはる」
一冊のなかで行ったり来たりするために、ページ番号を振るだけでなく、ページ見開きを4つのエリア(ABCD)に分けて、p39Aのように書かれている場所がおおよそ分かるようにする。
面白いことするな~と思いました。システム手帳ならばそのまま入れ替えれば済みます。ハイパーリンクやスレッド表示で行ったり来たりするほうがはるかに面倒だと思うのですがね。
その4 「タグ付け」「アイコン表示」
このへんはシールやスタンプでやりたいですね。自分なりに工夫してみようと思います。
ただこういった文具を使う時というのは,将来的にも入手可能なのかと考えてしまうんですよね。
新しいものに飛びつくよりも,既存のものを活用するようにします。
その5 「索引づくり」
たしかにあったほうがいいんですけどね,面倒なんですよね。あとで書きますが,いまは月に1回月間リフィルでやるようにしています。
そんな感じです。特に目新しい部分は少ないですね。
分かっちゃいるけどやっていない,やってみたいけどできていない,という部分を,もう一度背中を押された感じがします。
ブログで自分の手帳の使い方を紹介できたらいいな,なんて思いました。そのうちやります。そのうち…。
【目次】
はじめに あなたの脳を「拡張」するノート
なぜ紙のノートでなくてはいけないのか?
「外部の脳」にふさわしいモレスキンノート
人生を豊かにする一冊へ
第1章 なぜ、モレスキンノートが選ばれるのか
モレスキンノートとは何か?
基本とラインナップ
経験を蓄積する「手帳」としての使い方
なぜ、モレスキンノートが選ばれるのか?
「自由」を愛する精神
デジタルツールとの使い分け
はじめて書き込んでみる
第2章 モレスキンノートに人生を入れる
忘れるよりも早く記録するユビキタス・キャプチャー
ユビキタス・キャプチャーの基本ルール
ユビキタス・キャプチャーの形式
キャプチャーによって文体と文章量も選ぶ
吹き出しアイコンであえて制限を加える
素早いメモにはロディアを使う
感情をとらえる書き方をマスターする
つらい出来事もすべて書き込むメリット
一番大切なキャプチャーをとらえそこねない
ラベルシールで画像を取り込む
スタンプを利用して記入に近道を作る
ユビキタス・キャプチャーをマスターする
第3章 モレスキンノート「3ステップ活用法」
モレスキンノートを活用する3ステップ
「毎日レビュー」で情報を立ち上がらせる
毎日レビューの進め方
ページとページをつなぐ「ハイパーリンク」
ページの検察性を上げるための「タグづけ」
「カテゴリ分け」で流れを作る
「アイコン表示」でページの雰囲気を一瞬で伝える
ページを「拡張」する
週に一度、情報のつながりをレビューする
「週次レビュー」で情報を永続化する
一瞬で重要な情報を引き出せる「索引作り」
「スレッド表示」で断片的なキャプチャーを一カ所に集約する
開かなくても中身が見えるようにする工夫
「メタノート」で散らばった情報を集めていく
Evernoteを利用してモレスキンノートをデジタル化
仕上げに背表紙に銘を入れる
過去のノートが今の自分を助けてくれる
第4章 モレスキンノート「ビジネス活用術」
システム手帳を「卒業」しよう
「できる人」は自分の手帳を作る
自分に合ったダイアリーを選ぶ
ミニシステム手帳に作り変える
デイリーダイアリーで「時間トラッキング」
「行動メニュー」で無理なく分単位で時間を活用する
デジタルツールを連携させる書き方
モレスキンノートで「 GTDシステム」を作る
リポーターで「今やるべきこと」を書き留める
メモポケットに情報カードを入れて「To Do管理」をする
目標と常に向き合える仕組み作り
偶然の出会いからアイデアを生み出すヒント
フォリオノートで毎日一枚のマインドマップを描く
フォリオフォルダーを仕事のブリーフケースにする
第5章 モレスキンノート「生活活用術」
モレスキンノートの使い方に制限を加えない
絵日記をつける
万年筆と文字で日記をつける
交換ノートをする
読書日記をつける
フォトアルバムを作る
トラベルノートを作る
コレクションブックを作る
レシピブックを作る
スケッチをする
イベントめぐりを記録する
グルメめぐりを記録する
健康を記録する
単語帳を作る
第6章 モレスキンノート「DIYカスタマイズ術」
世界でただ一つのノートを作る
ペンをどうやって持ち歩く?
しおり紐をカスタマイズする
表紙をデコレーションする
カバーをつける
拡張ポケットに窓をつける
財布にして持ち歩く
ハードカバー+三冊カイエと二ヴォラン
MSKを利用する
ダイアリーに日本の祝日を書き込む
保存方法を工夫する
第7章 モレスキンノートと相性のいい文房具
家づくりのDVDが送られてきた ― 2016/07/17

嫁ちゃんはそういうサービスがあると知っていたらしいのですが、私はすっかり忘れていました。
先日突然ハウスメーカーから、今までの家づくりにまつわる写真を動画に編集されたものが送られてきました。
完成して約1年が経とうとしていて、1年点検の案内がおそいな~と思っていた時期でした。
娘ちゃんに邪魔されながら、二人で懐かしく見させてもらいました。
そういえばブログでも記事にしようと思っていたのに、忙しさにかまけて完全に頓挫しています。
そんなわけで、ハウスメーカーの担当営業さんに久しぶりに電話をして、このDVDに使われている写真をデータで送ってほしいとお願いしました。
さすがに「ブログに載せたいので。」とは言いませんでしたが、さすが営業さん。その日のうちに家まで届けてくれました。
その際、家づくりについてインタビューさせてほしいとお願いされました。
ハウスメーカーのDMで、家を建てた人たちの感想などを写真を交えて掲載しているので、それをやってほしいというわけです。
自分たちもそれを見ては、好き勝手にあーだこーだ言っていたことを思い出します。それに載ることになりました。
さっそく二人で、「え~どこ撮ってもらう?」「どこまで片付ければいいのかな?」と話しました。
もちろんこちらが撮ってほしくないところと、向こうが撮りたいところと相談になるのだと思いますが、
片付けと装飾と、取材予定日までに少し頑張っておこうと思います。
先日突然ハウスメーカーから、今までの家づくりにまつわる写真を動画に編集されたものが送られてきました。
完成して約1年が経とうとしていて、1年点検の案内がおそいな~と思っていた時期でした。
娘ちゃんに邪魔されながら、二人で懐かしく見させてもらいました。
そういえばブログでも記事にしようと思っていたのに、忙しさにかまけて完全に頓挫しています。
そんなわけで、ハウスメーカーの担当営業さんに久しぶりに電話をして、このDVDに使われている写真をデータで送ってほしいとお願いしました。
さすがに「ブログに載せたいので。」とは言いませんでしたが、さすが営業さん。その日のうちに家まで届けてくれました。
その際、家づくりについてインタビューさせてほしいとお願いされました。
ハウスメーカーのDMで、家を建てた人たちの感想などを写真を交えて掲載しているので、それをやってほしいというわけです。
自分たちもそれを見ては、好き勝手にあーだこーだ言っていたことを思い出します。それに載ることになりました。
さっそく二人で、「え~どこ撮ってもらう?」「どこまで片付ければいいのかな?」と話しました。
もちろんこちらが撮ってほしくないところと、向こうが撮りたいところと相談になるのだと思いますが、
片付けと装飾と、取材予定日までに少し頑張っておこうと思います。
春休みと夏休みの仕事の違い ― 2016/07/21
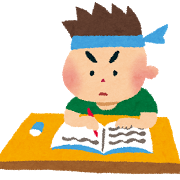
春休みと夏休みは全く違います。
春休みは、あらゆる仕事が締め切りをもって迫っています。
年度末の事務処理は3月31日、もしくは管理職の決めた日まで(特に管理職が異動になる場合は厳守)だし、
新年度の事務処理は4月1日の職員会議、もしくは入学式の日までとなります。
春休みに入って最初の締め切りが1週間後、次の締め切りがその1週間後に迫っています。
ですから、1日ごとにタスクを決めて、「ここまで」というラインを決めて、どんどん仕事をすることになります。
だから成果が挙がるのです。ものすごく疲れますが達成感もあります。
しかし、夏休みはそうではありません。
もちろん、1学期の諸表簿提出という締め切りはありますが、それも夏休みに入って1週間程度までです。
出張や研究会などで持参資料があっても、そこまで頑張れば終わりです。
だいたいの「やらなければならない仕事」は、夏休み前半(7月末まで)で終わってしまうのです。
そうすると、後半はダラダラしがちです。
部活をやって汗だくになって、お昼にまったりすると、もう今日はいいかなと思えてしまいます。
管理職も「休める時に休んでね」なんて甘いことを言ってきます。
ついつい年休をもらって帰ってしまい、そのまま家でもダラダラしてしまいます。(独身時代の経験談)
これが春休みと夏休みのちがいです。
夏休み後半は、第2領域(重要だが、緊急ではない)に取り組める最大のチャンスです。
締め切りに追われる春休みの緊張感で、余裕のある夏休み後半を過ごせると、飛躍的に成長できると思います。
今年の夏休み、部活の疲れにも負けず、汗だくの体にも負けず、管理職の甘い言葉にも負けずに、仕事をしてみましょう。
退勤時間までは仕事(第2領域)に専念するのです。
お互い、がんばりましょう。(ごめんね、嫁ちゃん。辛いときはメールして。)
春休みは、あらゆる仕事が締め切りをもって迫っています。
年度末の事務処理は3月31日、もしくは管理職の決めた日まで(特に管理職が異動になる場合は厳守)だし、
新年度の事務処理は4月1日の職員会議、もしくは入学式の日までとなります。
春休みに入って最初の締め切りが1週間後、次の締め切りがその1週間後に迫っています。
ですから、1日ごとにタスクを決めて、「ここまで」というラインを決めて、どんどん仕事をすることになります。
だから成果が挙がるのです。ものすごく疲れますが達成感もあります。
しかし、夏休みはそうではありません。
もちろん、1学期の諸表簿提出という締め切りはありますが、それも夏休みに入って1週間程度までです。
出張や研究会などで持参資料があっても、そこまで頑張れば終わりです。
だいたいの「やらなければならない仕事」は、夏休み前半(7月末まで)で終わってしまうのです。
そうすると、後半はダラダラしがちです。
部活をやって汗だくになって、お昼にまったりすると、もう今日はいいかなと思えてしまいます。
管理職も「休める時に休んでね」なんて甘いことを言ってきます。
ついつい年休をもらって帰ってしまい、そのまま家でもダラダラしてしまいます。(独身時代の経験談)
これが春休みと夏休みのちがいです。
夏休み後半は、第2領域(重要だが、緊急ではない)に取り組める最大のチャンスです。
締め切りに追われる春休みの緊張感で、余裕のある夏休み後半を過ごせると、飛躍的に成長できると思います。
今年の夏休み、部活の疲れにも負けず、汗だくの体にも負けず、管理職の甘い言葉にも負けずに、仕事をしてみましょう。
退勤時間までは仕事(第2領域)に専念するのです。
お互い、がんばりましょう。(ごめんね、嫁ちゃん。辛いときはメールして。)




最近のコメント