家の棟上げが終わりました ― 2015/04/01

2×4工法は早いと聞いていましたが、ほんと早い!
もう完成したんじゃないか?ってくらいの早さでした。
先日、土台ができあがって、週末に資材を搬入していました。
火曜日に棟上げと言っていたので、嫁ちゃんが娘ちゃんを抱っこしながら見に行きました。
午前中に一階ができあがり、午後には二階ができあがっていたそうです。
夕方、仕事を切り上げて見に行ったときには屋根を張っていました。
うーん、なんとも残念です。
家が立ち上がっていくのが一番の見所だと思うのですが、その過程を見ることができませんでした。
どうして、棟上げを土日にしてくれなかったのか…。
大工さんたちにご挨拶して、缶コーヒーを差し入れして一度帰ったあと、工事が終わった頃を見計らって、覗きに行ってみました。
土足ではいけないと思って、中には入りませんでしたが、周りを囲っている足場から覗き込んでみました。
さらに、階段を上がって、2F、屋根まで見てきました。屋根を見れるのは、もう建築中しかないでしょう。屋根からの見晴らしは最高でした。
屋根に上がれば花火も見えそうです。まぁソーラーパネルが乗っかるから,ほとんど屋根には上がれませんが。怖いし。
ともかく、一気に側が出来上がってしまいました。
2軒隣で新築中の在来軸組工法の家に追いついてしまいました。
これからどんどん進んでいくのでしょうね。楽しみです。
もう完成したんじゃないか?ってくらいの早さでした。
先日、土台ができあがって、週末に資材を搬入していました。
火曜日に棟上げと言っていたので、嫁ちゃんが娘ちゃんを抱っこしながら見に行きました。
午前中に一階ができあがり、午後には二階ができあがっていたそうです。
夕方、仕事を切り上げて見に行ったときには屋根を張っていました。
うーん、なんとも残念です。
家が立ち上がっていくのが一番の見所だと思うのですが、その過程を見ることができませんでした。
どうして、棟上げを土日にしてくれなかったのか…。
大工さんたちにご挨拶して、缶コーヒーを差し入れして一度帰ったあと、工事が終わった頃を見計らって、覗きに行ってみました。
土足ではいけないと思って、中には入りませんでしたが、周りを囲っている足場から覗き込んでみました。
さらに、階段を上がって、2F、屋根まで見てきました。屋根を見れるのは、もう建築中しかないでしょう。屋根からの見晴らしは最高でした。
屋根に上がれば花火も見えそうです。まぁソーラーパネルが乗っかるから,ほとんど屋根には上がれませんが。怖いし。
ともかく、一気に側が出来上がってしまいました。
2軒隣で新築中の在来軸組工法の家に追いついてしまいました。
これからどんどん進んでいくのでしょうね。楽しみです。
電気工事に立ち会って位置を変更 ― 2015/04/04

夕方前に家を見に行くと、今日は電気工事でした。
朝から作業をしていたそうで、そろそろ終わる頃でした。
挨拶をして、建物のなかを見せてもらいました。
初めて家のなかを見ました。
まだ中は柱しかないので、スカスカで見通しが良くなっています。
「ここが廊下で、ここが収納、ここが階段下かー。」と確認しながら見て回りました。
電気工事ということで、柱に穴を開けて、電気とテレビの配線が通っていました。
またその柱に、コンセントとスイッチの場所に黒いボックスが木ネジで固定されていました。
しかしよく見ると、キッチンの横の窓の下にあるコンセントの位置がおかしいです。
図面では窓のすぐ下に来るように指定したはずです。しかし、他のコンセントと同じで床上30cmに合わせてあります。
電気工のおじさんに言ってみると、「窓下ってのはそういうことですか?わかりました。直しましょう。」と言って直してくれました。
続けて、「リビングのコンセントの位置が図面だとよく分からないんですよね。」と言われました。たしかに付いていません。
そこで、「この図面はこういうことなんです。」と場所を伝えてつけてもらいました。念のため図面より10cm高くしておきました。
しかし、こうなってくると不安です。他の場所もチェックして直してもらいました。
位置変更その①
リビングの南側のコンセントを壁の真ん中ではなく、掃き出し窓寄りにしてもらいました。
この方が、ウッドデッキで何かするときにも電気を使いやすいと考えての変更です。
位置変更その②
洗面脱衣室の洗濯機のコンセントは、水道よりも手前に来るように直してもらいました。
水道は止めませんが、コンセントは節電のために小まめにプラグを抜いているからです。
位置変更その③
書斎の北側のコンセントは、「コンセント2つとテレビとLAN」と「コンセント2つ」の位置を逆にしました。
その方が配線をパソコンの裏側に隠せるかなと考えたからです。そもそもなんで見える位置にしてたのかな?
他の場所は大丈夫でした。大丈夫なはずです。実際に住んでみるとどうなかは分かりません。
電気工事のおじさんは、「今しか直せませんから。断熱材入れて、壁を作ってしまったら、直せませんからね。」と言って、一つ一つ確認しながらやってくれました。
いい人で良かった。そして、タイミングよく会えて良かった。
少し帰るのを遅くしてしまいましたが、本当に良かったです。
朝から作業をしていたそうで、そろそろ終わる頃でした。
挨拶をして、建物のなかを見せてもらいました。
初めて家のなかを見ました。
まだ中は柱しかないので、スカスカで見通しが良くなっています。
「ここが廊下で、ここが収納、ここが階段下かー。」と確認しながら見て回りました。
電気工事ということで、柱に穴を開けて、電気とテレビの配線が通っていました。
またその柱に、コンセントとスイッチの場所に黒いボックスが木ネジで固定されていました。
しかしよく見ると、キッチンの横の窓の下にあるコンセントの位置がおかしいです。
図面では窓のすぐ下に来るように指定したはずです。しかし、他のコンセントと同じで床上30cmに合わせてあります。
電気工のおじさんに言ってみると、「窓下ってのはそういうことですか?わかりました。直しましょう。」と言って直してくれました。
続けて、「リビングのコンセントの位置が図面だとよく分からないんですよね。」と言われました。たしかに付いていません。
そこで、「この図面はこういうことなんです。」と場所を伝えてつけてもらいました。念のため図面より10cm高くしておきました。
しかし、こうなってくると不安です。他の場所もチェックして直してもらいました。
位置変更その①
リビングの南側のコンセントを壁の真ん中ではなく、掃き出し窓寄りにしてもらいました。
この方が、ウッドデッキで何かするときにも電気を使いやすいと考えての変更です。
位置変更その②
洗面脱衣室の洗濯機のコンセントは、水道よりも手前に来るように直してもらいました。
水道は止めませんが、コンセントは節電のために小まめにプラグを抜いているからです。
位置変更その③
書斎の北側のコンセントは、「コンセント2つとテレビとLAN」と「コンセント2つ」の位置を逆にしました。
その方が配線をパソコンの裏側に隠せるかなと考えたからです。そもそもなんで見える位置にしてたのかな?
他の場所は大丈夫でした。大丈夫なはずです。実際に住んでみるとどうなかは分かりません。
電気工事のおじさんは、「今しか直せませんから。断熱材入れて、壁を作ってしまったら、直せませんからね。」と言って、一つ一つ確認しながらやってくれました。
いい人で良かった。そして、タイミングよく会えて良かった。
少し帰るのを遅くしてしまいましたが、本当に良かったです。
画鋲の針が残っていないか確認! ― 2015/04/06

新学期スタートに向けて、教室準備は終わりましたか?
私は土日も使って、嫁ちゃんにも手伝ってもらって、なんとか終わらせました。
というかもう、終わったことにするしかないです。
さて、タイトルの件です。
教室や廊下の壁に、画鋲の針が残っていませんか?
もしやったことがない方がいらっしゃったら、念のため確認することをお薦めします。
画鋲を取ったときに、頭だけ取れて、針が残ってしまうことがあります。その針のことです。
取れてしまった時にはどうしようもないですし、生徒がやったときには言ってくれないことも多いです。
ひどいときは、壁の至るところに針が残っていることがあります。
壁に手を当てたり、手でなでたりすると、切り傷を作ります。
制服やジャージをほつれさせたり、プリントに穴を開けてしまったりすることもあります。
そうならないために、予防的にしっかり確認しておきましょう。
やり方は簡単です。よーく壁を見るか、ゆーっくら手でなでてみましょう。
見つけたら、ラジオペンチで抜きます。抜けないときは、ラジオペンチか金づちで押し込んでしまいます。
これらの道具は、用務員さんや事務室で借りてから教室に向かうといいですね。
また、廊下や他教室の壁も見ておくと、学校全体の安全管理が見えてきます。
(もう新学期が始まってしまった!)という方は、逆転の発想で、生徒が見ているときにやりましょう。
「先生は私達がケガしないように、そんなところまで気遣ってくれているんだ!」というアピールになります。(ただ、他の先生の前では気を付けて、嫌味に取られないように…。)
というわけで、年度の始めに点検しましょう。
本来であれば年度の終わりに点検してから、次の先生へ引き継ぐべきです。
もちろん、いつでも見つけたら対応しましょう。生徒のためです。
では、今年度もがんばりましょう。
私は土日も使って、嫁ちゃんにも手伝ってもらって、なんとか終わらせました。
というかもう、終わったことにするしかないです。
さて、タイトルの件です。
教室や廊下の壁に、画鋲の針が残っていませんか?
もしやったことがない方がいらっしゃったら、念のため確認することをお薦めします。
画鋲を取ったときに、頭だけ取れて、針が残ってしまうことがあります。その針のことです。
取れてしまった時にはどうしようもないですし、生徒がやったときには言ってくれないことも多いです。
ひどいときは、壁の至るところに針が残っていることがあります。
壁に手を当てたり、手でなでたりすると、切り傷を作ります。
制服やジャージをほつれさせたり、プリントに穴を開けてしまったりすることもあります。
そうならないために、予防的にしっかり確認しておきましょう。
やり方は簡単です。よーく壁を見るか、ゆーっくら手でなでてみましょう。
見つけたら、ラジオペンチで抜きます。抜けないときは、ラジオペンチか金づちで押し込んでしまいます。
これらの道具は、用務員さんや事務室で借りてから教室に向かうといいですね。
また、廊下や他教室の壁も見ておくと、学校全体の安全管理が見えてきます。
(もう新学期が始まってしまった!)という方は、逆転の発想で、生徒が見ているときにやりましょう。
「先生は私達がケガしないように、そんなところまで気遣ってくれているんだ!」というアピールになります。(ただ、他の先生の前では気を付けて、嫌味に取られないように…。)
というわけで、年度の始めに点検しましょう。
本来であれば年度の終わりに点検してから、次の先生へ引き継ぐべきです。
もちろん、いつでも見つけたら対応しましょう。生徒のためです。
では、今年度もがんばりましょう。
【8万アクセス】教師としてどうしてブログを書くのか ― 2015/04/08

このブログは,公私混同で書いています。
それには,私自身が仕事人間だった自分を改め,私生活も大切なのだと思うようになったことをきっかけに,
『ワーク・ライフ・バランスを取るため』という理由があります。
生徒や学校の話ばかり書いているときは,家族や自分のことを疎かにしている。
趣味や物欲の話ばかり書いているときは,仕事や家庭のことを怠けている。
そんな風に考えて,混同にすることでバランスが取れると思っています。
実は,もう一つ理由があります。
それは,
『教師として自分自身が,「一人の大人のモデル」を示す』
ためです。
ここからは私の勝手な私見です。
小学校までは学級担任が基本的に全教科を受け持ちます。
朝から帰るまでずっと一緒に生活することで,基本的生活習慣,学習習慣,人間関係力の基本を指導することができます。
それに対して,中学校は教科担任制です。一人の生徒にたくさんの教師(大人)が関わります。
それによって,中学生に,さまざまな大人としての生き方のモデルを示しているのだと考えています。
いろいろな大人がいること,いろいろな生き方があることを,生徒に提示するのが中学校なのだと考えています。
教師は本や話の中よりも『よりリアルな大人』をモデルとして提示します。
つまり,学生を卒業して,仕事をし,結婚して,子供を育て,家を建て,健康に気を使い,部活動に打ち込み,勉強を続け,転任・退職していく。
そういう一人の人間としての生き方を,自分の人生を題材として,生徒に提示するのです。
同じ「教師」という仕事でありながらも,さまままな大人がいることを示していきます。カメラが特技の理科教師がいれば,野球が趣味の国語教師もいるのです。
子供たちは,教師のそういう生き方を見て,「自分もああなりたいな。」「自分はああはならないぞ。」と取捨選択しながら大人になっていくのだと考えています。
さらにその中で,子供たちは職業というものを理解し始め,「ああ,ああいう仕事もいいな。」「なるほど,そういう仕事もあるのか。」と感じて,自分の夢にしていくこともあるわけです。
例えば,私が結婚した年に受け持っていた女子生徒の一人は,将来の夢に「ウェディングプランナー」と書いていました。
家を建てた今年は,そんな話はしていないのですが,「建築家になりたい。」と書いた生徒がいました。
つまり,教師の今のライフステージが,生徒の進路にも影響を及ぼすことがあるわけです。だから色々な世代の先生がいる学校の方が,本当はいいのです。
私がブログを通して表現したいことの一つは,
そうやって仕事と家庭のあいだを行ったり来たりするのが生きると言うことであり,
そうやって失敗してショ気たり,うまくいって喜んだりするのが人間というものなんだ,
ということを中学生に伝えていきたいわけです。
(理想的なモデルではなく,現実にいる等身大の一つの例として。)
以上,そんなことを考えたり考えなかったりしながら,どこまで続くか,このブログで書いていきます。
ほんとは単純に,ブログを2つも管理するなんて無理!というのが本音かもしれません^^;
今日で8万アクセスを達成しました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
それには,私自身が仕事人間だった自分を改め,私生活も大切なのだと思うようになったことをきっかけに,
『ワーク・ライフ・バランスを取るため』という理由があります。
生徒や学校の話ばかり書いているときは,家族や自分のことを疎かにしている。
趣味や物欲の話ばかり書いているときは,仕事や家庭のことを怠けている。
そんな風に考えて,混同にすることでバランスが取れると思っています。
実は,もう一つ理由があります。
それは,
『教師として自分自身が,「一人の大人のモデル」を示す』
ためです。
ここからは私の勝手な私見です。
小学校までは学級担任が基本的に全教科を受け持ちます。
朝から帰るまでずっと一緒に生活することで,基本的生活習慣,学習習慣,人間関係力の基本を指導することができます。
それに対して,中学校は教科担任制です。一人の生徒にたくさんの教師(大人)が関わります。
それによって,中学生に,さまざまな大人としての生き方のモデルを示しているのだと考えています。
いろいろな大人がいること,いろいろな生き方があることを,生徒に提示するのが中学校なのだと考えています。
教師は本や話の中よりも『よりリアルな大人』をモデルとして提示します。
つまり,学生を卒業して,仕事をし,結婚して,子供を育て,家を建て,健康に気を使い,部活動に打ち込み,勉強を続け,転任・退職していく。
そういう一人の人間としての生き方を,自分の人生を題材として,生徒に提示するのです。
同じ「教師」という仕事でありながらも,さまままな大人がいることを示していきます。カメラが特技の理科教師がいれば,野球が趣味の国語教師もいるのです。
子供たちは,教師のそういう生き方を見て,「自分もああなりたいな。」「自分はああはならないぞ。」と取捨選択しながら大人になっていくのだと考えています。
さらにその中で,子供たちは職業というものを理解し始め,「ああ,ああいう仕事もいいな。」「なるほど,そういう仕事もあるのか。」と感じて,自分の夢にしていくこともあるわけです。
例えば,私が結婚した年に受け持っていた女子生徒の一人は,将来の夢に「ウェディングプランナー」と書いていました。
家を建てた今年は,そんな話はしていないのですが,「建築家になりたい。」と書いた生徒がいました。
つまり,教師の今のライフステージが,生徒の進路にも影響を及ぼすことがあるわけです。だから色々な世代の先生がいる学校の方が,本当はいいのです。
私がブログを通して表現したいことの一つは,
そうやって仕事と家庭のあいだを行ったり来たりするのが生きると言うことであり,
そうやって失敗してショ気たり,うまくいって喜んだりするのが人間というものなんだ,
ということを中学生に伝えていきたいわけです。
(理想的なモデルではなく,現実にいる等身大の一つの例として。)
以上,そんなことを考えたり考えなかったりしながら,どこまで続くか,このブログで書いていきます。
ほんとは単純に,ブログを2つも管理するなんて無理!というのが本音かもしれません^^;
今日で8万アクセスを達成しました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
春休みのタスク管理はWordでやりました ― 2015/04/14

昨年度は3年担任だったので,3月後半,卒業式以降は少し時間的に余裕ができました。
おかげで,事務仕事をガンガンに進めて,年度末の3学年の仕事,理科の仕事,校務分掌の事務を終わらせることができました。
そして3月最終週からは,つまり春休みに入ってすぐに新年度の準備を始めることができました。
校内人事の内示を受けて,今年度は1年主任兼担任と聞いていたので,学年主任としての仕事が増えることが予想されます。
どんな仕事があるか,リストアップしてみることにしました。(そうです,私は言語感覚優位ですw)
その時に使ったのが,自分の『教師手帳』ではなく,Evernoteでもなく,Microsoft Wordでした。
その理由は,手帳に書ききれないほどのタスク(todo)が予想されたからです。新年度準備の仕事量はハンパないことを経験的に知っています。
また,Evernoteにしなかったのは,学校のネットワークのセキュリティがかかっていて,クラウドサービスが使えないからです。
スマホでテザリングして,自前のノートPCやiPadを使うという手もありますが,学校支給のパソコンと並べて置くのもスペース的に難しいです。
結果,学校のノートPCを使って「Word」でタスク管理を行いました。それについて記録しておきます。
●その1 A5サイズで印刷できるようにしておく。
最終的にはシステム手帳に入れておきたいと思ったので,A5サイズにしました。周辺の余白20mmで,33行とれました。
●その2 チェックボックス(☐,☑)を単語登録する。
チェックボックスは四角ですが,標準ではなく環境依存文字の四角にしました。「ちぇっく」で変換すると出てくる環境依存文字の「レ」の四角と同じにするためです。
そして,まいど「しかく」とか「ちぇっく」とか入力するのは面倒なので,「四角(☐)」は「し」,「チェック(☑)」は「れ」で変換して出てくるように単語登録しました。
●その3 日付や項目に「スタイル」を設定する。
「平成26年度3月」という一行を「ホーム」タブの「スタイル」で「見出し1」にセットします。
その下に「20150324(火)」と日付を入れたら,「スタイル」で「見出し2」にセットします。
その下に【新年度準備】【教室準備】【入学式関係】などの項目を作ったら,「スタイル」で「見出し3」にセットします。
そして,それらの項目の下にタスク(todo)をチェックボックス(☐)付きでどんどん書いていきます。
もちろん,思いついたらとりあえず書いておいて,あとで並び替えればいいですよ。
各スタイルを右クリックすると,スタイルを変更するメニューが出ます。中にショートカットの設定もあるので,それを使うとより操作が早くなります。
●その4 「ナビゲーション」を表示して活用する。
「表示」タブの「表示」にある「ナビゲーション ウィンドウ」にチェックを入れると,画面の左側にナビゲーションが出てきます。
その項目になっているのが,先ほど設定した「見出し1~3」になっています。
その項目をクリックすれば,その場所にジャンプすることができます。
また,「文書の検索」で「チェックボックス(☐)」の文字を検索すれば,終わっていないタスクが黄色く反転するので探し出すことができます。
●その5 終わったらチェックボックス(☐)にチェック(☑)する。
これで検索に引っかからなくなります。また後ろに実際に行った日付やかかった時間を記録しておくと,記録として有効性が増しますね。
こんな感じでやっていきました。
ちなみに,3月24日~4月14日の3週間で,約400コのtodoをこなしていました。1日に約20コですね。
やはり手帳では無理なペースでした。まぁ春休み中はパソコンに向かって仕事ができる,というのも大きいですね。
やっと仕事も落ち着いてきて,そろそろ教師手帳に戻れそうです。
おかげで,事務仕事をガンガンに進めて,年度末の3学年の仕事,理科の仕事,校務分掌の事務を終わらせることができました。
そして3月最終週からは,つまり春休みに入ってすぐに新年度の準備を始めることができました。
校内人事の内示を受けて,今年度は1年主任兼担任と聞いていたので,学年主任としての仕事が増えることが予想されます。
どんな仕事があるか,リストアップしてみることにしました。(そうです,私は言語感覚優位ですw)
その時に使ったのが,自分の『教師手帳』ではなく,Evernoteでもなく,Microsoft Wordでした。
その理由は,手帳に書ききれないほどのタスク(todo)が予想されたからです。新年度準備の仕事量はハンパないことを経験的に知っています。
また,Evernoteにしなかったのは,学校のネットワークのセキュリティがかかっていて,クラウドサービスが使えないからです。
スマホでテザリングして,自前のノートPCやiPadを使うという手もありますが,学校支給のパソコンと並べて置くのもスペース的に難しいです。
結果,学校のノートPCを使って「Word」でタスク管理を行いました。それについて記録しておきます。
●その1 A5サイズで印刷できるようにしておく。
最終的にはシステム手帳に入れておきたいと思ったので,A5サイズにしました。周辺の余白20mmで,33行とれました。
●その2 チェックボックス(☐,☑)を単語登録する。
チェックボックスは四角ですが,標準ではなく環境依存文字の四角にしました。「ちぇっく」で変換すると出てくる環境依存文字の「レ」の四角と同じにするためです。
そして,まいど「しかく」とか「ちぇっく」とか入力するのは面倒なので,「四角(☐)」は「し」,「チェック(☑)」は「れ」で変換して出てくるように単語登録しました。
●その3 日付や項目に「スタイル」を設定する。
「平成26年度3月」という一行を「ホーム」タブの「スタイル」で「見出し1」にセットします。
その下に「20150324(火)」と日付を入れたら,「スタイル」で「見出し2」にセットします。
その下に【新年度準備】【教室準備】【入学式関係】などの項目を作ったら,「スタイル」で「見出し3」にセットします。
そして,それらの項目の下にタスク(todo)をチェックボックス(☐)付きでどんどん書いていきます。
もちろん,思いついたらとりあえず書いておいて,あとで並び替えればいいですよ。
各スタイルを右クリックすると,スタイルを変更するメニューが出ます。中にショートカットの設定もあるので,それを使うとより操作が早くなります。
●その4 「ナビゲーション」を表示して活用する。
「表示」タブの「表示」にある「ナビゲーション ウィンドウ」にチェックを入れると,画面の左側にナビゲーションが出てきます。
その項目になっているのが,先ほど設定した「見出し1~3」になっています。
その項目をクリックすれば,その場所にジャンプすることができます。
また,「文書の検索」で「チェックボックス(☐)」の文字を検索すれば,終わっていないタスクが黄色く反転するので探し出すことができます。
●その5 終わったらチェックボックス(☐)にチェック(☑)する。
これで検索に引っかからなくなります。また後ろに実際に行った日付やかかった時間を記録しておくと,記録として有効性が増しますね。
こんな感じでやっていきました。
ちなみに,3月24日~4月14日の3週間で,約400コのtodoをこなしていました。1日に約20コですね。
やはり手帳では無理なペースでした。まぁ春休み中はパソコンに向かって仕事ができる,というのも大きいですね。
やっと仕事も落ち着いてきて,そろそろ教師手帳に戻れそうです。
スーパー副担を目指して ― 2015/04/17
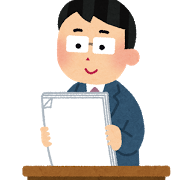
今年は1学年です。学年主任と学級担任を兼任です。
学年1クラスですから、それも仕方ないのですが、そもそも学年スタッフが自分だけです。
いわゆる副担任という先生がいません。
そのため、何をするにしても自分でやらなくてはなりません。
「学校生活のしおり」などの資料を作るのも、それを印刷するのも、配って説明するのも、すべて自分です。
表の仕事も裏の仕事も、すべて自分でやるしかありません。
なんでこんな校内人事なのか、副担任の先生がいる他学年がうらやましいときがあります。
副担というと,かつての勤務校では「スーパー副担」という言葉がありました。
副担任というのは,学年の担任の先生を補佐する役割と捉えられがちです。
1つの学級(担任)に1人の副担任がついていたら贅沢で,ふつうは2~4クラスを1人の副担がサポートするようになります。
しかし,スーパー副担はそれだけではありません。
スーパー副担は,学年主任の片腕として(ときには両腕両足として)仕事をしたり,教頭先生から仕事を任されて学校運営に関わったりします。
かつて私も講師だったころ,このスーパー副担をしていたときがありました。
それは校務分掌には載らない,つまり学校の表舞台には出てこないのだけれど,いないと困ってしまうという役回りでした。
学年主任の隣の席で仕事が回されてきたり,生徒全員の総合的な学習の時間の評価(文章表記)を書いたり,面接練習の計画を立てて実施したり,卒業式の礼法指導をしたり,卒業アルバムを作ったり・・・。教頭先生から大事な仕事を任されたこともありました。
そうです,「趣味は仕事です。」と言っても周りは誰も疑問に思わないほど仕事をしていた時期でした。20代だったからできた仕事だとも思います。
大変ではありましたが,とてもやりがいがありました。(よく燃え尽きなかったな~・・・。)
教頭先生の大変さや,教務,学年主任の苦労を,少し味わうことができたと思います。
その後,教頭先生から,「講師ではできない仕事がある。はやく教諭になりなさい。」と言われ,あらためて教員採用試験に向けて発奮したものでした。
そして,いろいろあって,今があります。あのときの経験が,時を経て,今役に立っている気がします。
自分一人ではありますが,今年一年なんとか乗り切って,学級担任としてだけでなく,学年主任として成長したいと思います。
学年1クラスですから、それも仕方ないのですが、そもそも学年スタッフが自分だけです。
いわゆる副担任という先生がいません。
そのため、何をするにしても自分でやらなくてはなりません。
「学校生活のしおり」などの資料を作るのも、それを印刷するのも、配って説明するのも、すべて自分です。
表の仕事も裏の仕事も、すべて自分でやるしかありません。
なんでこんな校内人事なのか、副担任の先生がいる他学年がうらやましいときがあります。
副担というと,かつての勤務校では「スーパー副担」という言葉がありました。
副担任というのは,学年の担任の先生を補佐する役割と捉えられがちです。
1つの学級(担任)に1人の副担任がついていたら贅沢で,ふつうは2~4クラスを1人の副担がサポートするようになります。
しかし,スーパー副担はそれだけではありません。
スーパー副担は,学年主任の片腕として(ときには両腕両足として)仕事をしたり,教頭先生から仕事を任されて学校運営に関わったりします。
かつて私も講師だったころ,このスーパー副担をしていたときがありました。
それは校務分掌には載らない,つまり学校の表舞台には出てこないのだけれど,いないと困ってしまうという役回りでした。
学年主任の隣の席で仕事が回されてきたり,生徒全員の総合的な学習の時間の評価(文章表記)を書いたり,面接練習の計画を立てて実施したり,卒業式の礼法指導をしたり,卒業アルバムを作ったり・・・。教頭先生から大事な仕事を任されたこともありました。
そうです,「趣味は仕事です。」と言っても周りは誰も疑問に思わないほど仕事をしていた時期でした。20代だったからできた仕事だとも思います。
大変ではありましたが,とてもやりがいがありました。(よく燃え尽きなかったな~・・・。)
教頭先生の大変さや,教務,学年主任の苦労を,少し味わうことができたと思います。
その後,教頭先生から,「講師ではできない仕事がある。はやく教諭になりなさい。」と言われ,あらためて教員採用試験に向けて発奮したものでした。
そして,いろいろあって,今があります。あのときの経験が,時を経て,今役に立っている気がします。
自分一人ではありますが,今年一年なんとか乗り切って,学級担任としてだけでなく,学年主任として成長したいと思います。
ご近所さんがまもなく完成です・・・ ― 2015/04/25

うちより早く建て始めているご近所さんがまもなく完成です。
あまり人の家の悪口は言いたくないので、「こ、これは!」ということだけ記事にしておきます。
1つ目「北側のお宅に一切日が当たらない…」
もちろん法律的にはクリアしているのでしょうけれど、北側は1メートルも開けていません。横も50cmギリギリです。
敷地限界に家を建てたのですね。高さも3階建てのアパートと同じくらいに見えます。
そのため、北側の家にはまったく日が当たらなくなっていました。狭いスペースに洗濯物が干してありました。
うちは北側を何メートル開けるかさんざん悩んだので、その遠慮のなさに驚きました。
いや、悪くはないんですよ。法律的にはね。だから、文句はありません。
うちは北側2メートルの有効活用を考えないといけません。
2つ目「建築中のうちの水道を勝手に使われた!」
先日、自分の家を見に行ったときのことです。
クルマを降りたところ、大工さんが一人外にいました。
トコトコと一輪車を押して、うちの外水道から水をくんで、ご近所の家へ行ってしまいました。
え?え?うちの水道を勝手に使っているということですか!?
信じられない…。
そんな話、聞いたことがない。
あっけに取られて、その場では抗議できなかったのが残念です。
すぐに現場監督に伝えて、向こうのハウスメーカーに苦情を入れてもらいました。
まぁ私が建築中の水道代を払うわけではないので、財布は痛くないのですが、気分はまったくよくありません。
こんなことで、住む前からご近所トラブルにはしたくないので、黙っておきますが、住む人たちに対しても印象が悪くなりました。
3つ目「ロフトで立ててしまった」
そんな家が完成見学会をやるというので、ご近所になるとは秘密で見に行きました。
既に印象が悪いので、なかの作りもなんかついつい批判的に見てしまいます。
まぁいいです。住むのは私達ではないし、施主達は納得しているのでしょうから。
それよりも、最後に案内された3階部分。「3階ですか?ロフトですか?」「3階ではないんですけど、ロフト…ではないんです。」「??」
扉を開けて入ってみると、私が少しひざを曲げるくらいの天井の高さです。つまり170cmくらいです。
「あれ?立てますね。ロフトって140cmでしたよね?なんで?」
「いや、実はですね・・・。」
もうこれ以上のことは書きません。そんなことまでやってしまうハウスメーカーだったということです。
うちのハウスメーカーはきちんとダメなことはダメと教えてくれました。
なんか、このハウスメーカーの印象がますます悪くなりました。
どうか、住む人たちとはうまくやっていけることを願います。
あまり人の家の悪口は言いたくないので、「こ、これは!」ということだけ記事にしておきます。
1つ目「北側のお宅に一切日が当たらない…」
もちろん法律的にはクリアしているのでしょうけれど、北側は1メートルも開けていません。横も50cmギリギリです。
敷地限界に家を建てたのですね。高さも3階建てのアパートと同じくらいに見えます。
そのため、北側の家にはまったく日が当たらなくなっていました。狭いスペースに洗濯物が干してありました。
うちは北側を何メートル開けるかさんざん悩んだので、その遠慮のなさに驚きました。
いや、悪くはないんですよ。法律的にはね。だから、文句はありません。
うちは北側2メートルの有効活用を考えないといけません。
2つ目「建築中のうちの水道を勝手に使われた!」
先日、自分の家を見に行ったときのことです。
クルマを降りたところ、大工さんが一人外にいました。
トコトコと一輪車を押して、うちの外水道から水をくんで、ご近所の家へ行ってしまいました。
え?え?うちの水道を勝手に使っているということですか!?
信じられない…。
そんな話、聞いたことがない。
あっけに取られて、その場では抗議できなかったのが残念です。
すぐに現場監督に伝えて、向こうのハウスメーカーに苦情を入れてもらいました。
まぁ私が建築中の水道代を払うわけではないので、財布は痛くないのですが、気分はまったくよくありません。
こんなことで、住む前からご近所トラブルにはしたくないので、黙っておきますが、住む人たちに対しても印象が悪くなりました。
3つ目「ロフトで立ててしまった」
そんな家が完成見学会をやるというので、ご近所になるとは秘密で見に行きました。
既に印象が悪いので、なかの作りもなんかついつい批判的に見てしまいます。
まぁいいです。住むのは私達ではないし、施主達は納得しているのでしょうから。
それよりも、最後に案内された3階部分。「3階ですか?ロフトですか?」「3階ではないんですけど、ロフト…ではないんです。」「??」
扉を開けて入ってみると、私が少しひざを曲げるくらいの天井の高さです。つまり170cmくらいです。
「あれ?立てますね。ロフトって140cmでしたよね?なんで?」
「いや、実はですね・・・。」
もうこれ以上のことは書きません。そんなことまでやってしまうハウスメーカーだったということです。
うちのハウスメーカーはきちんとダメなことはダメと教えてくれました。
なんか、このハウスメーカーの印象がますます悪くなりました。
どうか、住む人たちとはうまくやっていけることを願います。
【家具】 イケアに行きたい…! ― 2015/04/26

先日、大工さんと話したときに「イケアはイケアで揃えないとサイズとかデザインが合わないんですよねー。」なんて強がりを言いました。
ニトリや東京インテリアでもいいかなーと思っていました。しかし、自分の気に入るデザインが見つかりません。
ついついイケアに目が行ってしまいます。「リビング イケア」で検索したり。
悩んでいたら(そうか!家全体をイケアにする必要はないのか!)と気がつきました。
リビングと書斎はイケア、キッチンとダイニングはニトリ、といった感じで、空間ごとに分ければいいのです!
当たり前すぎて「!」を付けるほどでもないですか…。でも、おかげでインテリアの楽しみが広がりました。
とりあえずイケアで考えているのは、リビングと書斎です。
リビングはテレビ周りの壁面収納です。ロの字形のテレビボードは好きではなくて、コの字のデザインにしようと思っています。
ベストーシリーズを使って、上の部分は先日大工さんにお願いした下地を利用して、吊り戸棚にしようと思います。
横の棚はどんなでもいいのですが、下のテレビボードは今使っているものをそのまま使うか、ベストーに買い替えるか悩んでいます。
書斎は本棚をイケアのビリーシリーズにしようと思っています。
イケアにはコーナー部分の本棚を斜めに立てて固定するためのパーツがあったので、ぜひL字に並べたいです。
しかし、机をL字にするためには、部屋が狭くて本棚は南側1面しか無理かもしれません。
東側の壁にも下地を入れてもらので、ここに吊り戸棚をつければ、L字の本棚と、L字の机が両立できます。
ベストーにしてもビリーにしても、種類が豊富なのでよく見て検討しなくてはいけません。
配送サービスを利用することにはなると思いますが、組み立てはなんとか自分でやりたいですね。
大工さんに頼んで、一緒に組み立ててもらうってのもアリかなー。
とにかく、まずはイケアに出掛けてみたいと思います。
ニトリや東京インテリアでもいいかなーと思っていました。しかし、自分の気に入るデザインが見つかりません。
ついついイケアに目が行ってしまいます。「リビング イケア」で検索したり。
悩んでいたら(そうか!家全体をイケアにする必要はないのか!)と気がつきました。
リビングと書斎はイケア、キッチンとダイニングはニトリ、といった感じで、空間ごとに分ければいいのです!
当たり前すぎて「!」を付けるほどでもないですか…。でも、おかげでインテリアの楽しみが広がりました。
とりあえずイケアで考えているのは、リビングと書斎です。
リビングはテレビ周りの壁面収納です。ロの字形のテレビボードは好きではなくて、コの字のデザインにしようと思っています。
ベストーシリーズを使って、上の部分は先日大工さんにお願いした下地を利用して、吊り戸棚にしようと思います。
横の棚はどんなでもいいのですが、下のテレビボードは今使っているものをそのまま使うか、ベストーに買い替えるか悩んでいます。
書斎は本棚をイケアのビリーシリーズにしようと思っています。
イケアにはコーナー部分の本棚を斜めに立てて固定するためのパーツがあったので、ぜひL字に並べたいです。
しかし、机をL字にするためには、部屋が狭くて本棚は南側1面しか無理かもしれません。
東側の壁にも下地を入れてもらので、ここに吊り戸棚をつければ、L字の本棚と、L字の机が両立できます。
ベストーにしてもビリーにしても、種類が豊富なのでよく見て検討しなくてはいけません。
配送サービスを利用することにはなると思いますが、組み立てはなんとか自分でやりたいですね。
大工さんに頼んで、一緒に組み立ててもらうってのもアリかなー。
とにかく、まずはイケアに出掛けてみたいと思います。
大工さんに下地を入れてもらった ― 2015/04/29

うちの大工さんはとてもいい方で、家づくりのいろいろなことを教えてくれます。
ベランダの鉄板が熱くなるから、スノコのようなものを並べたほうがいいとか、
駐車場は道路から1メートルくらい奥まらせないと、除雪車が来たときに車が出せなくなるとか、
こちらが気がつかなかったことを教えてもらえました。平日は嫁ちゃん経由の話がほとんどですが。
今日は久しぶりに、大工さんに直接お会いできました。
そこで先日変更してもらった、コンセントやLAN端子、スイッチの位置を確認していきました。
図面上では良かれと思っていても、現場を見たり、大工さんと話していると、再度考えてしまいますね。パントリーの固定棚の高さを相談して、なんとか決めました。
そこからさらに雑談をしているときに、「リビングの収納も悩んでるんですよねー。」と振ってみました。そしたら大工さんも「テレビボードとかですか?」と言って、リビングへ移動。
私「テレビボードは開放感がなくて、ロの字は好きじゃないんです。できれば、コの字かニの字にしたいんです。」
大工さん「じゃあ、開口部を突っ張れば大丈夫ですね。そういうのもありますから。」
私「そういうのは見たことないですね。吊り戸棚みたいになるといいんですけどね。」
大工さん「じゃあ、この辺に下地を入れておきますか。」
という感じで、テレビボードを置く予定の場所の上イコール吊り戸棚が来そうな位置に、下地を入れてもらえることになりました。しかも、大工さんのサービスです。ありがたい!
さらに調子に乗って書斎へ。コンセントの話から本棚の話へ持っていき、本棚を固定するための下地を作ってもらえることになりました。
大工さん「先生だから、本もたくさんあるでしょう。高さ180cmの本棚が多いから、その辺りにしておきましょう。」
なんて気前のいい方なのでしょう。「現場監督には秘密にしておいて。何か言われたら、知らないって答えて。」と笑っていました。
下地がどこに入っているか分からなくなりそうなので、壁が仕上がる前に写真を撮っておこうと思います。
そしたら大工さんが「撮っておきますよ。」だって。どこまで優しい人なんだ。
むしろ、家具を買ってきたときに固定するのもお任せしたいと思ってしまいました。いやもちろん、手間賃は払いますよ!
ベランダの鉄板が熱くなるから、スノコのようなものを並べたほうがいいとか、
駐車場は道路から1メートルくらい奥まらせないと、除雪車が来たときに車が出せなくなるとか、
こちらが気がつかなかったことを教えてもらえました。平日は嫁ちゃん経由の話がほとんどですが。
今日は久しぶりに、大工さんに直接お会いできました。
そこで先日変更してもらった、コンセントやLAN端子、スイッチの位置を確認していきました。
図面上では良かれと思っていても、現場を見たり、大工さんと話していると、再度考えてしまいますね。パントリーの固定棚の高さを相談して、なんとか決めました。
そこからさらに雑談をしているときに、「リビングの収納も悩んでるんですよねー。」と振ってみました。そしたら大工さんも「テレビボードとかですか?」と言って、リビングへ移動。
私「テレビボードは開放感がなくて、ロの字は好きじゃないんです。できれば、コの字かニの字にしたいんです。」
大工さん「じゃあ、開口部を突っ張れば大丈夫ですね。そういうのもありますから。」
私「そういうのは見たことないですね。吊り戸棚みたいになるといいんですけどね。」
大工さん「じゃあ、この辺に下地を入れておきますか。」
という感じで、テレビボードを置く予定の場所の上イコール吊り戸棚が来そうな位置に、下地を入れてもらえることになりました。しかも、大工さんのサービスです。ありがたい!
さらに調子に乗って書斎へ。コンセントの話から本棚の話へ持っていき、本棚を固定するための下地を作ってもらえることになりました。
大工さん「先生だから、本もたくさんあるでしょう。高さ180cmの本棚が多いから、その辺りにしておきましょう。」
なんて気前のいい方なのでしょう。「現場監督には秘密にしておいて。何か言われたら、知らないって答えて。」と笑っていました。
下地がどこに入っているか分からなくなりそうなので、壁が仕上がる前に写真を撮っておこうと思います。
そしたら大工さんが「撮っておきますよ。」だって。どこまで優しい人なんだ。
むしろ、家具を買ってきたときに固定するのもお任せしたいと思ってしまいました。いやもちろん、手間賃は払いますよ!




最近のコメント