学んだことの理解度 ― 2014/04/01
何の本に書かれていたか分からないのですが,iPodtouchやiPadのデータを整理していたら,発見したのでメモしておきます。
------------------
学んだことをどれくらい理解しているか。
聞いたことは10%
見たことは15%
聞いて見たときは20%
話し合ったときは40%
体験したときは80%
教えたときは90%
------------------
なるほどな,と思わせる数値ですね。
実際,このぐらいかもしれません。
山本五十六の名言を思い出しました。
------------------
やって見せて,言って聞かせて,やらせて見て,
ほめてやらねば,人は動かず。
話し合い,耳を傾け,承認し,任せてやらねば,人は育たず。
やっている,姿を感謝で見守って,信頼せねば,人は実らず。
------------------
教育とは,奥深いものです。
新年度が始まりました。
また,ボチボチがんばっていきます。
------------------
学んだことをどれくらい理解しているか。
聞いたことは10%
見たことは15%
聞いて見たときは20%
話し合ったときは40%
体験したときは80%
教えたときは90%
------------------
なるほどな,と思わせる数値ですね。
実際,このぐらいかもしれません。
山本五十六の名言を思い出しました。
------------------
やって見せて,言って聞かせて,やらせて見て,
ほめてやらねば,人は動かず。
話し合い,耳を傾け,承認し,任せてやらねば,人は育たず。
やっている,姿を感謝で見守って,信頼せねば,人は実らず。
------------------
教育とは,奥深いものです。
新年度が始まりました。
また,ボチボチがんばっていきます。
研修に申し込んで自分を奮わせる ― 2014/04/02
職員会議2日目。自分の分の仕事も無事に終わらせることができました。
会議のあと,その中で出されていた各種研修会に参加するかどうか悩みました。
今年も生徒指導主事なので,それにまつわる出張がいくつもあります。
今年は情報教育担当になったので,それ関係の研修・出張が増えます。
そこでさらに,自分から研修を増やすことがどうかと思ったわけです。
しかし,結果的には去年と同様に,いくつかの研修会に参加することにしました。
そうやって自分を追い込まないと,自分を成長させることができないと思ったからです。
去年のICT関係の研修で,ダイレクトに自分の実になるものは少なかったという感想を持っています。
それでも,研修に参加することによって,問題意識をもって考えたり,自分なりに行動したりすることができました。
最たるものはパワポ授業です。今年度もこれを推し進めていきたいと考えています。
そのヒントが直接的または内発的に得られることを期待します。
(一年間の研修の募集が,年度の初めだけというのも,悩ましい問題点ではありますがね。)
会議のあと,その中で出されていた各種研修会に参加するかどうか悩みました。
今年も生徒指導主事なので,それにまつわる出張がいくつもあります。
今年は情報教育担当になったので,それ関係の研修・出張が増えます。
そこでさらに,自分から研修を増やすことがどうかと思ったわけです。
しかし,結果的には去年と同様に,いくつかの研修会に参加することにしました。
そうやって自分を追い込まないと,自分を成長させることができないと思ったからです。
去年のICT関係の研修で,ダイレクトに自分の実になるものは少なかったという感想を持っています。
それでも,研修に参加することによって,問題意識をもって考えたり,自分なりに行動したりすることができました。
最たるものはパワポ授業です。今年度もこれを推し進めていきたいと考えています。
そのヒントが直接的または内発的に得られることを期待します。
(一年間の研修の募集が,年度の初めだけというのも,悩ましい問題点ではありますがね。)
学期ごとのスタート3日間 ― 2014/04/03

先生方と話をしていて気が付いたのですが,いわゆる「黄金の3日間」をご存知ない先生がいらっしゃいました。
自分の常識は,みんなの常識ではないということですね。
それでも,自分の指導力のレベルとは別に,知識として知っておいてもいいと思ったので,自分の考えを書いておきます。
(私自身はTOSSは知っている程度です。参考にはしていますが,傾倒はしていません。ですから,ここに書いてあることも,TOSSとしては違う!と言われるかもしれません。)
【黄金の3日間】
春休み明けの3日間。新年度の始まりです。
この3日間は,どの子も新しい学年への希望とやる気に満ちていて,先生の話をしっかり聞こうとします。
そこで,学級経営方針をきちんと伝えたり,係や当番,委員会などの仕組みとルールを作ったり,学級目標や学級スローガンを立てさせたりします。
先生自身もやる気がみなぎっているはずです。4日目にどれだけイライラしたり,怒ったりしないで済むか,この3日間に本気で取り組むといいです。
逆に言えば,4日目の生徒の失敗は,先生の失敗です。ルールや決まりを生徒全員に共通理解させ,共通実践させる必要があったのに,どこかで抜けてしまったのです。改めてフォローしましょう。
【白銀の3日間】
夏休み明けの3日間。一番長い2学期のスタートです。
この3日間は,生徒は夏休み明けでまったく本調子ではありません。1学期に指導した努力はなんだったの!?というくらい仕組みやルールを忘れています。
怒る必要はありません。当たり前なのです。学級という公共の場から,家庭という私的な場に生活の中心があったのです。ルールを忘れて当然です。
ですから,ルールを忘れているだけだと心に余裕をもって,「1学期にこう決めたよね?」と思い出させればいいだけです。
また,「もう慣れたと思うから,2学期からはこういう風に変えたいんだけど,できるよね?」とルールを変えるチャンスでもあります。
もちろん,ルールを覚えていて破った場合には,しっかり指導する必要があります。
【青銅の3日間】
冬休み明けの3日間。1年の始まり,年度の終わりです。
冬休み明けのルール忘れは,夏休み明けほどではありません。ずっと指導してきているので,ほとんどの生徒はルールを覚えているはずです。
反対に,まじめな生徒はだんだんと息切れしてくるころです。また,かしこい生徒は手を抜き始めるころです。
そこで,そういった生徒たちへの活力を与えるようにします。私はいつも「3学期は年度の終わり,まとめの学期だよ。そして,新年の始まり,上級生になる助走の学期だよ。」という話をしています。
そして,何度も学級目標を確認して,「何をどうやったら,目標を達成したって言えるの?自分たちで目標立てたんだよね?」と迫ります。
自分たちが4月のやる気がみなぎっていたときに立てた目標。この自分たちの印籠を自分たちの目の前に突き付けられて,生徒たちも発奮するようになります。
さらに,「つぎの学年に向けて,こういう風にルールを変えたいんだけど,がんばってね。」と言って,ルールを変えることもできます。
3日間で伝えられなかったルールは,「先生の指示が足りなかった。申し訳ない。こういうふうにしたいんだけど,いいかな。」と全員が聞いている状態で話をして,立て直します。
また,2学期,3学期のはじめにルールを変える場合も同じです。「君たちの成長を見ていて,こういうふうにルールを変えたいと思ったんだけど,よろしくね。」
中学生が相手ですから,きちんとした理由を説明します。大人として扱うのです。
「この方が,一人一人の負担が減る。」「日直の仕事が大変そうに見える。」「上級生には,こういうことが求められる。」というように,そうすることのメリットや意義をしっかりと話します。
生徒が同意して,納得してくれることが大切です。学期始めの3日間であれば,素直に聞いてくれます。
4日目以降になると,「先生,前はそんなこと言わなかった。」「このあいだと言っていることが違う。」などの反論や不満の声が出てきます。きちんと謝って,説明責任を果たすのが,大人として必要なことだと思います。
相手を子供扱いして,「いいから,こうするの!」というのでは,子供の成長を阻害してしまうように思います。
さて,今年度の学級経営方針を確認してみますか。
(まだまだ未熟者の考えですが,何か参考になれば幸いです。)
自分の常識は,みんなの常識ではないということですね。
それでも,自分の指導力のレベルとは別に,知識として知っておいてもいいと思ったので,自分の考えを書いておきます。
(私自身はTOSSは知っている程度です。参考にはしていますが,傾倒はしていません。ですから,ここに書いてあることも,TOSSとしては違う!と言われるかもしれません。)
【黄金の3日間】
春休み明けの3日間。新年度の始まりです。
この3日間は,どの子も新しい学年への希望とやる気に満ちていて,先生の話をしっかり聞こうとします。
そこで,学級経営方針をきちんと伝えたり,係や当番,委員会などの仕組みとルールを作ったり,学級目標や学級スローガンを立てさせたりします。
先生自身もやる気がみなぎっているはずです。4日目にどれだけイライラしたり,怒ったりしないで済むか,この3日間に本気で取り組むといいです。
逆に言えば,4日目の生徒の失敗は,先生の失敗です。ルールや決まりを生徒全員に共通理解させ,共通実践させる必要があったのに,どこかで抜けてしまったのです。改めてフォローしましょう。
【白銀の3日間】
夏休み明けの3日間。一番長い2学期のスタートです。
この3日間は,生徒は夏休み明けでまったく本調子ではありません。1学期に指導した努力はなんだったの!?というくらい仕組みやルールを忘れています。
怒る必要はありません。当たり前なのです。学級という公共の場から,家庭という私的な場に生活の中心があったのです。ルールを忘れて当然です。
ですから,ルールを忘れているだけだと心に余裕をもって,「1学期にこう決めたよね?」と思い出させればいいだけです。
また,「もう慣れたと思うから,2学期からはこういう風に変えたいんだけど,できるよね?」とルールを変えるチャンスでもあります。
もちろん,ルールを覚えていて破った場合には,しっかり指導する必要があります。
【青銅の3日間】
冬休み明けの3日間。1年の始まり,年度の終わりです。
冬休み明けのルール忘れは,夏休み明けほどではありません。ずっと指導してきているので,ほとんどの生徒はルールを覚えているはずです。
反対に,まじめな生徒はだんだんと息切れしてくるころです。また,かしこい生徒は手を抜き始めるころです。
そこで,そういった生徒たちへの活力を与えるようにします。私はいつも「3学期は年度の終わり,まとめの学期だよ。そして,新年の始まり,上級生になる助走の学期だよ。」という話をしています。
そして,何度も学級目標を確認して,「何をどうやったら,目標を達成したって言えるの?自分たちで目標立てたんだよね?」と迫ります。
自分たちが4月のやる気がみなぎっていたときに立てた目標。この自分たちの印籠を自分たちの目の前に突き付けられて,生徒たちも発奮するようになります。
さらに,「つぎの学年に向けて,こういう風にルールを変えたいんだけど,がんばってね。」と言って,ルールを変えることもできます。
3日間で伝えられなかったルールは,「先生の指示が足りなかった。申し訳ない。こういうふうにしたいんだけど,いいかな。」と全員が聞いている状態で話をして,立て直します。
また,2学期,3学期のはじめにルールを変える場合も同じです。「君たちの成長を見ていて,こういうふうにルールを変えたいと思ったんだけど,よろしくね。」
中学生が相手ですから,きちんとした理由を説明します。大人として扱うのです。
「この方が,一人一人の負担が減る。」「日直の仕事が大変そうに見える。」「上級生には,こういうことが求められる。」というように,そうすることのメリットや意義をしっかりと話します。
生徒が同意して,納得してくれることが大切です。学期始めの3日間であれば,素直に聞いてくれます。
4日目以降になると,「先生,前はそんなこと言わなかった。」「このあいだと言っていることが違う。」などの反論や不満の声が出てきます。きちんと謝って,説明責任を果たすのが,大人として必要なことだと思います。
相手を子供扱いして,「いいから,こうするの!」というのでは,子供の成長を阻害してしまうように思います。
さて,今年度の学級経営方針を確認してみますか。
(まだまだ未熟者の考えですが,何か参考になれば幸いです。)
風呂と娘ちゃんと私・・・ ― 2014/04/04
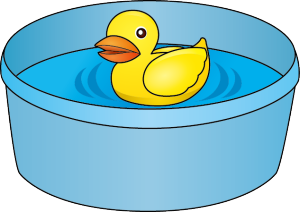
泣かれます。
お風呂に入れると,必ずといっていいほど泣かれてしまいます。
父親としては,けっこう切ない。
せまいお風呂のなかで,ギャン泣きされると,耳が痛いほどです。
家の中はもちろんですが,換気扇を通じて外にも聞こえているだろうなと思います。
お風呂上りに,嫁ちゃんに渡したとたんに泣き止むので,いっそう辛いものがあります。
いろいろ条件を変えながらやっているのですが,よく分かりません。
まだまだ新しい環境に娘ちゃんが慣れていないというのもあります。
前は実家で,お義父さんと嫁ちゃんが二人がかりで入れていました。
今は私が一人で入れています。顔も体も頭も一人でやっています。
首が据わっていないから,冷や冷やしながらやっていますが,それも良くないのかもしれません。
私の不安が,手や表情を通して伝わっているのかもしれませんね。
ネットで調べると,赤ちゃんに泣かれるお父さんは多いようで,自分だけではないんだと慰められました。
赤ちゃんはお風呂で泣くものだと割り切ってしまおう,と言っているサイトもありました。
しかし,実家では気持ちよくお風呂に入っていたのです。私もそうしてあげたい。
理科の実験と一緒ですね,トライ&エラーを繰り返します。
お風呂に入れると,必ずといっていいほど泣かれてしまいます。
父親としては,けっこう切ない。
せまいお風呂のなかで,ギャン泣きされると,耳が痛いほどです。
家の中はもちろんですが,換気扇を通じて外にも聞こえているだろうなと思います。
お風呂上りに,嫁ちゃんに渡したとたんに泣き止むので,いっそう辛いものがあります。
いろいろ条件を変えながらやっているのですが,よく分かりません。
まだまだ新しい環境に娘ちゃんが慣れていないというのもあります。
前は実家で,お義父さんと嫁ちゃんが二人がかりで入れていました。
今は私が一人で入れています。顔も体も頭も一人でやっています。
首が据わっていないから,冷や冷やしながらやっていますが,それも良くないのかもしれません。
私の不安が,手や表情を通して伝わっているのかもしれませんね。
ネットで調べると,赤ちゃんに泣かれるお父さんは多いようで,自分だけではないんだと慰められました。
赤ちゃんはお風呂で泣くものだと割り切ってしまおう,と言っているサイトもありました。
しかし,実家では気持ちよくお風呂に入っていたのです。私もそうしてあげたい。
理科の実験と一緒ですね,トライ&エラーを繰り返します。
「日本人はいませんでした」 ― 2014/04/06

最近,なんだか航空機の墜落や,船舶の沈没,大地震などの大規模な事故や災害が目立ちます。
気にしていなかっただけ?一つ気になりだすと,他の類似したニュースに対してもアンテナが立つからかな?
そんなニュースを観ていたら,嫁ちゃんが「日本人はいなかったらしいよ。」と一言。
それを聞いたら,イエモンの「日本人はいませんでした~♪」をつい口ずさんでしまいました。
嫁ちゃんもすかさず「イエモンでしょ?」とツッコミ。「なんか懐かしいよね~。」なんて話をしました。
ところが,嫁ちゃんは「この『日本人はいませんでした』の意味わかってる?」と聞いたら分かっていませんでした。
自分の常識はみんなの常識ではないシリーズか。
海外での大事故・大災害のニュースで,「日本人はいませんでした」と言うのは,
「日本人に被害者はいないので,旅行や仕事で海外に行っている家族や知人がいても,今のところは心配しないで大丈夫ですよ。
だから情報収集で忙しい外務省に電話したり,混乱している現地の大使館に電話したりしないでね。
国際電話の回線がパンクさせてしまったら,本当に電話を必要としている他の外国の方たちが困ってしまいますからね。」
という意味らしいです。
おそらく海外は海外で,自国の渡航者についての安否報道をしているのだと思います。(ここは想像ですが。)
とにかく,「日本人に被害者はいないから,必要以上に慌てないで」というところでしょう。
これを知ってしまうと,あの歌の印象はだいぶ変わってきますね。まぁ,イエモンが言いたいことも分かりますが。
イエモンの「JAM」という曲の一節ですが,本当に懐かしいですね。ちなみに,中島みゆきも似たような歌を歌っていたと思います。どちらも懐かしいな・・・。
気にしていなかっただけ?一つ気になりだすと,他の類似したニュースに対してもアンテナが立つからかな?
そんなニュースを観ていたら,嫁ちゃんが「日本人はいなかったらしいよ。」と一言。
それを聞いたら,イエモンの「日本人はいませんでした~♪」をつい口ずさんでしまいました。
嫁ちゃんもすかさず「イエモンでしょ?」とツッコミ。「なんか懐かしいよね~。」なんて話をしました。
ところが,嫁ちゃんは「この『日本人はいませんでした』の意味わかってる?」と聞いたら分かっていませんでした。
自分の常識はみんなの常識ではないシリーズか。
海外での大事故・大災害のニュースで,「日本人はいませんでした」と言うのは,
「日本人に被害者はいないので,旅行や仕事で海外に行っている家族や知人がいても,今のところは心配しないで大丈夫ですよ。
だから情報収集で忙しい外務省に電話したり,混乱している現地の大使館に電話したりしないでね。
国際電話の回線がパンクさせてしまったら,本当に電話を必要としている他の外国の方たちが困ってしまいますからね。」
という意味らしいです。
おそらく海外は海外で,自国の渡航者についての安否報道をしているのだと思います。(ここは想像ですが。)
とにかく,「日本人に被害者はいないから,必要以上に慌てないで」というところでしょう。
これを知ってしまうと,あの歌の印象はだいぶ変わってきますね。まぁ,イエモンが言いたいことも分かりますが。
イエモンの「JAM」という曲の一節ですが,本当に懐かしいですね。ちなみに,中島みゆきも似たような歌を歌っていたと思います。どちらも懐かしいな・・・。
手帳とスマホを併用・両立する方法 ― 2014/04/07

以前はiPadの「i手帳HD」でスケジュール管理をしていたときもあったのですが,結局,紙の手帳に戻ってきました。
あれから数ヶ月が経ちました。やはり,手書きのシステム手帳は馴染みます。
しかし,システム手帳(A5版)の大きさがネックになるときがあります。例えば外での活動中。あるいはトイレの中。手帳を持ち歩いていられない場所や状況は少なからずあります。
そんなときは,肌身離さず持ち歩いているスマホで予定が確認できたらいいな~と感じます。
だからといって,スマホですべての予定を管理できるほど,自分はスマホに一生懸命打ち込む気になれません。
周りの先生も生徒も,わたしが職員室や教室でスマホ片手に仕事をしていたら違和感を感じるでしょう。(iPadは黙認されていたけど…)
というわけで,システム手帳をメインにスケジュール管理,タスク管理をしつつ,スマホでも簡単にそれを参照できるようにしたいと思って,今まで,いろいろとスマホのアプリを試行錯誤しました。
その結果たどりついたのが,『Google Keep』です。
『Google Keep』を今さら紹介する必要はないかもしれませんが,Googleが開発した,『Evernote』や『Onenote』に対抗するようなクラウドメモアプリです。
テキストメモや画像・写真メモ,ボイスメモも可能です。正直,そんなに使い込んでいるわけではないので,実力がどこまでかは分からないのですが,当然ながらAndroidへの対応はピカイチのようです。
GoogleKeepはEvernoteやOnenoteと違って何がいいのかというと,スマホのウィジェットに画像を表示しておける点です。
たぶん,EvernoteやOnenoteではできない芸当です。(サードパーティーではあるかもしれませんが,見つけられませんでした。)
この機能を次のように使います。
まずはシステム手帳に一週間分のスケジュールやタスクを書きだします。
それをGoogleKeepの画像メモとして写真を撮ります。そうすれば,その写真がウィジェットに表示されるというわけです。
いちいち何かアプリを起動させたり,手で打ち込んだりといったことも必要ありません。撮れば自動的に表示されるからです。
手帳に追記したら,また撮り直しておけばいい。これで,手帳が手元になくても,いつでも手帳に書かれている内容をスマホで確認することができるようになります。
ちょっとした休憩のときに,今週の授業の予定を確認したいというのが一番多いパターンなので,こんな程度で十分です。さらに先の予定であれば,とっとと手帳を開いた方が早いです。
ただ,一週間分(平日5日分)のスケジュールが見渡せるように表示させる写真の撮り方には,練習が必要です^^;
ちなみに,最後の最後は紙の手帳をドキュメントスキャナで取り込んで,Evernoteに送り込む予定です。
Evernoteは,ライフログをメインとする記録のためのメモアプリとして今後も使っていきます。時系列に強いイメージだからです。
Onenoteはおそらく教材研究ノートとしての位置づけになると思います。こちらは系統性のあるノートアプリのイメージだからです。(ただ,今はまだWindowsタブレットを持っていないし,パワーポイントを使って教材研究を行っています。)
GoogleKeepは第三のメモアプリです。写真で記録するのが中心の,気軽な使い捨てメモのイメージです。
こんな感じで使い分けながら,手帳とスマホの併用・両立し始めています。
あれから数ヶ月が経ちました。やはり,手書きのシステム手帳は馴染みます。
しかし,システム手帳(A5版)の大きさがネックになるときがあります。例えば外での活動中。あるいはトイレの中。手帳を持ち歩いていられない場所や状況は少なからずあります。
そんなときは,肌身離さず持ち歩いているスマホで予定が確認できたらいいな~と感じます。
だからといって,スマホですべての予定を管理できるほど,自分はスマホに一生懸命打ち込む気になれません。
周りの先生も生徒も,わたしが職員室や教室でスマホ片手に仕事をしていたら違和感を感じるでしょう。(iPadは黙認されていたけど…)
というわけで,システム手帳をメインにスケジュール管理,タスク管理をしつつ,スマホでも簡単にそれを参照できるようにしたいと思って,今まで,いろいろとスマホのアプリを試行錯誤しました。
その結果たどりついたのが,『Google Keep』です。
『Google Keep』を今さら紹介する必要はないかもしれませんが,Googleが開発した,『Evernote』や『Onenote』に対抗するようなクラウドメモアプリです。
テキストメモや画像・写真メモ,ボイスメモも可能です。正直,そんなに使い込んでいるわけではないので,実力がどこまでかは分からないのですが,当然ながらAndroidへの対応はピカイチのようです。
GoogleKeepはEvernoteやOnenoteと違って何がいいのかというと,スマホのウィジェットに画像を表示しておける点です。
たぶん,EvernoteやOnenoteではできない芸当です。(サードパーティーではあるかもしれませんが,見つけられませんでした。)
この機能を次のように使います。
まずはシステム手帳に一週間分のスケジュールやタスクを書きだします。
それをGoogleKeepの画像メモとして写真を撮ります。そうすれば,その写真がウィジェットに表示されるというわけです。
いちいち何かアプリを起動させたり,手で打ち込んだりといったことも必要ありません。撮れば自動的に表示されるからです。
手帳に追記したら,また撮り直しておけばいい。これで,手帳が手元になくても,いつでも手帳に書かれている内容をスマホで確認することができるようになります。
ちょっとした休憩のときに,今週の授業の予定を確認したいというのが一番多いパターンなので,こんな程度で十分です。さらに先の予定であれば,とっとと手帳を開いた方が早いです。
ただ,一週間分(平日5日分)のスケジュールが見渡せるように表示させる写真の撮り方には,練習が必要です^^;
ちなみに,最後の最後は紙の手帳をドキュメントスキャナで取り込んで,Evernoteに送り込む予定です。
Evernoteは,ライフログをメインとする記録のためのメモアプリとして今後も使っていきます。時系列に強いイメージだからです。
Onenoteはおそらく教材研究ノートとしての位置づけになると思います。こちらは系統性のあるノートアプリのイメージだからです。(ただ,今はまだWindowsタブレットを持っていないし,パワーポイントを使って教材研究を行っています。)
GoogleKeepは第三のメモアプリです。写真で記録するのが中心の,気軽な使い捨てメモのイメージです。
こんな感じで使い分けながら,手帳とスマホの併用・両立し始めています。
教室にプロジェクターを置きたい ― 2014/04/08

と,言ったけれどダメだったという話です。
今年度は情報教育担当になりました。
他の校務は去年からの継続なので,単純に仕事が一つ増えた形です。
プリンターのインクとか,ホームページの更新とか,パソコンとかICT機器とか,扱う校務分掌です。
大本命は「ホームページの更新」なんだろうな,と思いますが,断然・断トツに他の仕事に時間を割かなければいけないので,ホームページは優先順位が低いです。
ホームページの更新をするためには,逆に校務分掌を減らしてほしかった。仕事増やされたのに,どうやって時間を捻出するんですか!?…と言いたい。(言えないw)
と,泣き言を思い浮かべつつ,(自分が情報教育担当だったらまずこれをやるな)と考えていたことを提案してみました。
それが,タイトルの「教室にプロジェクターを置きたい」です。
「各普通教室にプロジェクターと実物投影機を置いておきませんか?
職員室のロッカー内に置いておくのはもったいないし,いざ使いたいときに使いづらいと思います。
教科係の生徒に運ばせるのもリスクがありますし,設置の手間がかかります。
学級数が減って,プロジェクターと実物投影機が揃っているんです。」
と言ってみたのですが,『管理』の問題でダメでした。
周りの先生方にも根回しをして,意気揚々と提案しただけに,ショックでどうなんだろうな・・・?と思い悩んでしまいました。
教科によっては,先生によっては,賛同を得られたのですがね・・・。
使っていない先生,使ったことのない先生にとっては,ハードルが高い,関心がない,リスクが怖いことなんでしょうか。
職員室の奥から各教室へプロジェクターとスクリーンを生徒に運ばせる方が,リスクが高いと思うのですがね。
生徒が階段を踏み外してケガをしたら,誰が責任を取るのでしょうか?壊れたプロジェクターは,誰が弁償するのでしょうか?
教室のロッカーのなかにしまっておけば,使いたい先生はノートパソコンだけ持って行ってパッと設置ができます。
実物投影機で教科書や資料集を拡大するだけなら,パソコンさえいりません。
(旧式なので)ファンが止まるまでコンセントを抜くのを待つなんていう時間も必要なくなります。
教室内で生徒がプロジェクターを壊すほど騒いだり,イタズラしたりするような学校の状況ではないのですがね。
私自身は理科室でばかり授業をしていますし,理科室にはプロジェクターも大型テレビも常設しています。
できればコンセントも抜きたくないくらいです。(コンセントの抜き差しによる故障のリスクが怖い。)もちろんスクリーンも下したままですw
そんなわけで,失礼ですけど,私は困らないのです。
他の先生方がICTに触れる機会を減らしたなと思うのみです。
というわけで,普通教室でプロジェクターを当たり前のように使う授業は,また少し遠のきました。というか,私がここにいる間はおそらく不可能でしょうね。
今年度は情報教育担当になりました。
他の校務は去年からの継続なので,単純に仕事が一つ増えた形です。
プリンターのインクとか,ホームページの更新とか,パソコンとかICT機器とか,扱う校務分掌です。
大本命は「ホームページの更新」なんだろうな,と思いますが,断然・断トツに他の仕事に時間を割かなければいけないので,ホームページは優先順位が低いです。
ホームページの更新をするためには,逆に校務分掌を減らしてほしかった。仕事増やされたのに,どうやって時間を捻出するんですか!?…と言いたい。(言えないw)
と,泣き言を思い浮かべつつ,(自分が情報教育担当だったらまずこれをやるな)と考えていたことを提案してみました。
それが,タイトルの「教室にプロジェクターを置きたい」です。
「各普通教室にプロジェクターと実物投影機を置いておきませんか?
職員室のロッカー内に置いておくのはもったいないし,いざ使いたいときに使いづらいと思います。
教科係の生徒に運ばせるのもリスクがありますし,設置の手間がかかります。
学級数が減って,プロジェクターと実物投影機が揃っているんです。」
と言ってみたのですが,『管理』の問題でダメでした。
周りの先生方にも根回しをして,意気揚々と提案しただけに,ショックでどうなんだろうな・・・?と思い悩んでしまいました。
教科によっては,先生によっては,賛同を得られたのですがね・・・。
使っていない先生,使ったことのない先生にとっては,ハードルが高い,関心がない,リスクが怖いことなんでしょうか。
職員室の奥から各教室へプロジェクターとスクリーンを生徒に運ばせる方が,リスクが高いと思うのですがね。
生徒が階段を踏み外してケガをしたら,誰が責任を取るのでしょうか?壊れたプロジェクターは,誰が弁償するのでしょうか?
教室のロッカーのなかにしまっておけば,使いたい先生はノートパソコンだけ持って行ってパッと設置ができます。
実物投影機で教科書や資料集を拡大するだけなら,パソコンさえいりません。
(旧式なので)ファンが止まるまでコンセントを抜くのを待つなんていう時間も必要なくなります。
教室内で生徒がプロジェクターを壊すほど騒いだり,イタズラしたりするような学校の状況ではないのですがね。
私自身は理科室でばかり授業をしていますし,理科室にはプロジェクターも大型テレビも常設しています。
できればコンセントも抜きたくないくらいです。(コンセントの抜き差しによる故障のリスクが怖い。)もちろんスクリーンも下したままですw
そんなわけで,失礼ですけど,私は困らないのです。
他の先生方がICTに触れる機会を減らしたなと思うのみです。
というわけで,普通教室でプロジェクターを当たり前のように使う授業は,また少し遠のきました。というか,私がここにいる間はおそらく不可能でしょうね。
「心に火を」KIRIN FIREのCM ― 2014/04/12

以前から気になっていたのですが,たまたま機会があって検索してみました。
キリンの缶コーヒー「FIRE」のCMが好きです。カッコイイ。
江口洋介さんのセリフ
『父さんはホームランを打たない。ゴールネットも揺らさない。
でも仕事にはバントをする人が必要だ。パスを出す人が必要だ。
父さんは見えない仕事に誇りを感じている。』
なんて,男としてはグッとくるものがあります。
『人は誰でも心の中に 自分だけの火をもっている。』
とは,自分の口には出して言えないけど,人から言われると「そうだ!」と拳を握りたくなります。
そんなわけで,興味が湧いてFIREのHPを見てみたら,「365日,日替わりCM」というのをやっていました。
関東のみの放送なので,地方の私は今まで知りませんでした。
その内容を見てみると,心を熱くする偉人たちの名言が載っています。
たとえば,
『仕事に追い立てられてはならない。
自ら仕事を追い立てるのだ。』
(ベンジャミン・フランクリン)
『やっかいなのは,何も知らないことではない。
実際に知らないのに,知っていると思い込んでしまっていることだ。』
(マーク・トウェイン)
という感じです。これが毎日日替わりで掲載されています。誰の言葉なのかは紹介されていません。
まじめに調べてくださっている方がいて,ほかのサイトでは誰の言葉なのかも知ることができます。まとめサイトなんかが参考になると思います。
でもまずはここから 「KIRIN」のHP
http://www.kirin.co.jp/products/softdrink/fire/
今年は,朝早く来た子供たちが読んでくれるのを期待して,できるだけ放課後の黒板にメッセージを書いています。
そのネタの一つとして,この偉人たちの言葉は使えるかもしれません。
私は男なので,クラスで話すときもどうしても男としてのメッセージ色が強いなと感じています。それでも,もっと熱く語れたらカッコいいだろうなと思うこともあります。
いつか使えるだろうと思って,日ごろから,心に響く「ワオストーリー」を集めているのですが,これからは,心に火がともる言葉も集めていこうと思います。
キリンの缶コーヒー「FIRE」のCMが好きです。カッコイイ。
江口洋介さんのセリフ
『父さんはホームランを打たない。ゴールネットも揺らさない。
でも仕事にはバントをする人が必要だ。パスを出す人が必要だ。
父さんは見えない仕事に誇りを感じている。』
なんて,男としてはグッとくるものがあります。
『人は誰でも心の中に 自分だけの火をもっている。』
とは,自分の口には出して言えないけど,人から言われると「そうだ!」と拳を握りたくなります。
そんなわけで,興味が湧いてFIREのHPを見てみたら,「365日,日替わりCM」というのをやっていました。
関東のみの放送なので,地方の私は今まで知りませんでした。
その内容を見てみると,心を熱くする偉人たちの名言が載っています。
たとえば,
『仕事に追い立てられてはならない。
自ら仕事を追い立てるのだ。』
(ベンジャミン・フランクリン)
『やっかいなのは,何も知らないことではない。
実際に知らないのに,知っていると思い込んでしまっていることだ。』
(マーク・トウェイン)
という感じです。これが毎日日替わりで掲載されています。誰の言葉なのかは紹介されていません。
まじめに調べてくださっている方がいて,ほかのサイトでは誰の言葉なのかも知ることができます。まとめサイトなんかが参考になると思います。
でもまずはここから 「KIRIN」のHP
http://www.kirin.co.jp/products/softdrink/fire/
今年は,朝早く来た子供たちが読んでくれるのを期待して,できるだけ放課後の黒板にメッセージを書いています。
そのネタの一つとして,この偉人たちの言葉は使えるかもしれません。
私は男なので,クラスで話すときもどうしても男としてのメッセージ色が強いなと感じています。それでも,もっと熱く語れたらカッコいいだろうなと思うこともあります。
いつか使えるだろうと思って,日ごろから,心に響く「ワオストーリー」を集めているのですが,これからは,心に火がともる言葉も集めていこうと思います。
今からならWindowsタブレットでしょ? ― 2014/04/15

研修に行ってきました。内容は研修というより,連絡会に近いような内容でした。
予算の使い方とか,教育委員会の情報センターとかの話ばかりでした。
そんな中で講師の方が,
「うちの情報センターも,iPadとAndroidタブレットを購入して,実際に研究を進めていくことになりました。」
と,得意気におっしゃったので,ズッコケそうになりました。
(なんで今さら・・・)
本当にズレてますよね。今なら,Windowsタブレットでしょう。オフィス関係のソフトウェアなどの購入もしなくて済むし,互換性がどうのこうの悩む必要がないわけですから。
数年前にこれを言ったのなら,(すごーい)と思えたと思いますが,今となっては遅すぎる気がします。
たぶん,予算要望したときにはiPadが良かったのでしょうが,ようやく予算が認められたときには,Windowsタブレットが成熟していた,という感じでしょうか。
ま,早く現場でのiPadの使用を解禁していただきたい。
もう一つ話がありまして,情報漏えいに関連して,
「モバイルHDDを持ち歩いている先生がいますが,すべての情報を持ち歩く必要があるのですかね?」
だそうです。
あるから持ち歩いているんですよ。
デジカメのデータとか,何GBになると思っているんですか?卒業アルバム作るのに,どれだけの写真枚数が必要になると思っているんですか?
教材研究すれば,動画なども蓄積されます。それらはDVDではなくて,HDDに入っているから,必要なところをパッと見せられるんです。
モバイルHDDがダメで,USBメモリがOKな理由が分からない…。
むしろ,クラウドの使用を認めてほしい。そうすれば,USBメモリの紛失や盗難の不祥事も減るでしょうに・・・。
なんか,そんなモヤモヤばかりを感じつつも,反論しても無駄なので大人しく帰ってきました。
さて,仕事しよ・・・。
予算の使い方とか,教育委員会の情報センターとかの話ばかりでした。
そんな中で講師の方が,
「うちの情報センターも,iPadとAndroidタブレットを購入して,実際に研究を進めていくことになりました。」
と,得意気におっしゃったので,ズッコケそうになりました。
(なんで今さら・・・)
本当にズレてますよね。今なら,Windowsタブレットでしょう。オフィス関係のソフトウェアなどの購入もしなくて済むし,互換性がどうのこうの悩む必要がないわけですから。
数年前にこれを言ったのなら,(すごーい)と思えたと思いますが,今となっては遅すぎる気がします。
たぶん,予算要望したときにはiPadが良かったのでしょうが,ようやく予算が認められたときには,Windowsタブレットが成熟していた,という感じでしょうか。
ま,早く現場でのiPadの使用を解禁していただきたい。
もう一つ話がありまして,情報漏えいに関連して,
「モバイルHDDを持ち歩いている先生がいますが,すべての情報を持ち歩く必要があるのですかね?」
だそうです。
あるから持ち歩いているんですよ。
デジカメのデータとか,何GBになると思っているんですか?卒業アルバム作るのに,どれだけの写真枚数が必要になると思っているんですか?
教材研究すれば,動画なども蓄積されます。それらはDVDではなくて,HDDに入っているから,必要なところをパッと見せられるんです。
モバイルHDDがダメで,USBメモリがOKな理由が分からない…。
むしろ,クラウドの使用を認めてほしい。そうすれば,USBメモリの紛失や盗難の不祥事も減るでしょうに・・・。
なんか,そんなモヤモヤばかりを感じつつも,反論しても無駄なので大人しく帰ってきました。
さて,仕事しよ・・・。
書籍「ホームページ辞典 第5版」 ― 2014/04/16

出張の帰りに本屋さんに寄り道してきました。
出張先は駐車場がせまくて,かなり早く行かないと停められません。
じゃあ大多数の人はどうするかというと,近くのショッピングモールの大型駐車場に停めるわけです。
そして,ここのショッピングモールは無料で2時間まで停められますが,それを超えてしまうと,3000円の買い物をしないと割引の駐車券をもらえないのです。
みんな,ブーたれてますが,2時間以内に用務が終わることを祈りながら参加しています。
さて,本題ですが,そのショッピングモールのなかにある本屋さんで,「ホームページ辞典 第5版」という分厚い本を買ってきました。
いきさつはこうです。
昨年,ホームページビルダー18を購入しました。そして,どうにかこうにか,自分のサイトを構築して公開することができました。
しかし,半分以上がいわゆる「工事中」で,放置したままになっています。(イマドキ「工事中」っていう言い方も時代を感じますねw)
まぁそんなに言うほどのコンテンツがなかったためなのですが,そのコンテンツを提示するだけのプログラムの知識がないのも問題だと思っていました。
HTMLもCSSもJavaScriptも,どれも中途半端な知識しかないというのは問題なわけです。
だからといって,ホームページビルダーの使い方の本を見てみても,ほとんどがWordPressのことばかりで面白くありません。
むかしホームページを作っていた頃は,HTMLとJavaScriptの辞典を片手にやっていました。
というわけで,今回はそれにCSSを追加した本ということで,この辞典を購入したわけです。
この本は第5版ということで,シリーズとして長いです。定評があるということだと思います。
1冊で,HTMLとCSSとJavaScriptがすべて網羅されているというのはありがたいです。
IEとFirefoxの表示結果が載っているのも特徴的です。
HTML5ではなくHTML4.0.1なのが残念ですが,その違いを実感するころにはそれなりのレベルになるはずです。
というわけで,コンテンツの問題はさておき,テクニック(技術)についての勉強はやっていけそうな気がします。
それをやる時間を作らないといけないわけですが…。
出張先は駐車場がせまくて,かなり早く行かないと停められません。
じゃあ大多数の人はどうするかというと,近くのショッピングモールの大型駐車場に停めるわけです。
そして,ここのショッピングモールは無料で2時間まで停められますが,それを超えてしまうと,3000円の買い物をしないと割引の駐車券をもらえないのです。
みんな,ブーたれてますが,2時間以内に用務が終わることを祈りながら参加しています。
さて,本題ですが,そのショッピングモールのなかにある本屋さんで,「ホームページ辞典 第5版」という分厚い本を買ってきました。
いきさつはこうです。
昨年,ホームページビルダー18を購入しました。そして,どうにかこうにか,自分のサイトを構築して公開することができました。
しかし,半分以上がいわゆる「工事中」で,放置したままになっています。(イマドキ「工事中」っていう言い方も時代を感じますねw)
まぁそんなに言うほどのコンテンツがなかったためなのですが,そのコンテンツを提示するだけのプログラムの知識がないのも問題だと思っていました。
HTMLもCSSもJavaScriptも,どれも中途半端な知識しかないというのは問題なわけです。
だからといって,ホームページビルダーの使い方の本を見てみても,ほとんどがWordPressのことばかりで面白くありません。
むかしホームページを作っていた頃は,HTMLとJavaScriptの辞典を片手にやっていました。
というわけで,今回はそれにCSSを追加した本ということで,この辞典を購入したわけです。
この本は第5版ということで,シリーズとして長いです。定評があるということだと思います。
1冊で,HTMLとCSSとJavaScriptがすべて網羅されているというのはありがたいです。
IEとFirefoxの表示結果が載っているのも特徴的です。
HTML5ではなくHTML4.0.1なのが残念ですが,その違いを実感するころにはそれなりのレベルになるはずです。
というわけで,コンテンツの問題はさておき,テクニック(技術)についての勉強はやっていけそうな気がします。
それをやる時間を作らないといけないわけですが…。




最近のコメント