【読書】「はじめて講師を頼まれたら読む本」 ― 2019/10/31

中経出版、大谷由里子、2009年、1400円
ファシリテーターの資格を取ってから、何度か講師として仕事をしてきました。
震災関連の勉強も続けなくてはならないし、ファシリテーターとしてスキルを磨く勉強もしなくてはなりません。
今後、講師として年間数件の依頼をこなすにしても、自分が講師としてレベルアップするために必要なことがあるかもしれないと思ったので、読んでみました。
著者はもと吉本興業のマネージャーの方のようで、芸人さんたちのニュースでも話題になっていた契約書についても、少し触れられていました。
目次
はじめに
第一章 講師に必要な心構えは「志」! ~マインド編~
1 講師とは何か?
講師を頼まれたら、あなたの世界を広げるチャンス
「寝かさない講師」になろう
マイクとマインドがあれば世の中は変えられる
「かけてもらいたい言葉」という目標を持つ
2 目的を明確にする
まずは「何のため」に話すのかを考える
講演のゴールを決める
メッセージはとことん追求しよう
講師の役目は社会への恩返し
3 「志」を持つ
何を伝えるために呼ばれたのか
熱い「志」が「伝わる」工夫を生む
自分がやらなければ誰がやる!
「伝わる」から「伝える」へ
三種類の講師別・求められるもの
第二章 講師になったら知っておきたいスキル・テクニック ~実践編~
4 台本を作る
五分ネタをたくさん作る
不幸すぎる経験もネタになる
話がどんどん広がるネタ帳作り
「例え話」で聞き手は身を乗り出す
人の心は「挑戦」と「共感」で動く
失敗体験は共感をえやすい
成功体験は「スキル」に落とし込め
「離陸の瞬間」を語ると聞き手は「ハッ」とする
「事実を飛躍させ、誇張して話す」技術
5 メリハリをつける
最初の三分、「ツカミ」で勝負!
聞き手を安心させる「まず結論から」の鉄則
「思い」と「スキル」はワンセット
「へー」「ホー」と夢中にさせるコツ
五分ネタの中に起承転結を
クイズタイムで聞き手を引き込む
「語呂合わせ」で印象に残す
説得力に欠けるときは、「人の言葉を借りる」
講演の余韻はシメしだい
6 ブラッシュアップする
ほかの講師の話は必ず自分に生かす
アンテナを立てて、スキマ時間も情報収集
自分の姿をビデオ撮影してみる
やっぱり声は大きいほうがいい
「五つのS」を意識する
小道具を使って聞き手を引きつける
本番用で使える「3ポイント式アンチョコ」
「これが最後の公演」という気持ちで
7 前日までの準備
主催者の意図は、はずさない
事前打ち合わせでは、できる講師の必須事項
相手の情報を入手しておくと喜ばれる
早めに行って会場の下見をする
健康管理で穴をあけない
コスプレもアリ!衣装で聞き手を引きつける
講演前の「必要なものリスト」
未来につながるレジュメ作り
懇親会からうまく抜け出せる魔法の一言
8 当日、本番前にすること
あがるのは、当たり前のこと
ホワイトボードのペンは必ずインクが切れている
プロジェクターに頼りすぎない
9 本番中のテクニック
寝ている人は、いじり倒せ
楽しく話せば、楽しく聞いてもらえる
ツカミの三分、「笑わせる」には?
「うなずきくん」を見つける
質問タイムを引き締めるツボ
10 アクシデントに対処する
早めの行動があなたを救う
信頼は、台風からのプレゼント
時間通りに終わるにはちょっとしたコツがある
非常事態! 講演中にトイレに行くワザ
鳴った携帯電話は、「突っ込み→笑い」
「出ていってください」と言ってもよい
ホームとアウェイでは戦い方が変わる
第三章 指名される講師になるプロの技 ~ステップアップ編~
11 指名を増やす
半年後、一年後、三年後の自分をイメージする
プロ講師はつねに競争にさらされている
できる講師は自分で売り込まない
マネージャーを持てば、ぐんと仕事が広がる
仕事がどんどん増える「相手を立てる」コツ
悪いうわさはすぐに広まると心えよ
出会った証に、ちょっとしたおみやげを
12 自分ブランドを確立する
プロフィールはA4一枚
写真だけで魅力を伝えるポイント
アンケートは次の講演への大事な財産
顧客リストはこうして有効活用
自分の本は、講師の究極の名刺
プロ講師なら知っておきたい講演料の決め方
13 活動の幅を広げる
「受付シート」「決定シート」を作る
できる講師はエージェントとのつき合い方がうまい
プレスリリース一つで集客がちがう!
企業のトップ向けに講演できる講師になる
やっぱり自分でセミナーを開くのは魅力的
ホームページ、ブログ、メルマガの100%活用法
持てるものなら「自分のセミナールーム」
【自分の読書メモ】
p22 「目の前の人にどうなってほしいのか」「目の前の人にどうやったら伝わるのか」、技術や方法を学ぶ前に、まず大切なのは自分自身の「志」を明確にすること
p64 成功体験を「誰でもできるスキル」に落とし込んで話す。抽象的な話は自慢話になってしまう。具体的な誰でもできるスキルにすれば「私でもできそう」と感じてもらえる。
p78 スキルの流行
・アサーティブ ・コーチング ・NLP ・コミュニケーション ・ファシリテーション
・メンタルヘルス ・モチベーションマネジメント ・オフサイトミーティング
p104 5つのS(Story、Simple、Special、Speed、Smile)
ストーリー、シンプル、スペシャル、スピード、スマイル
起承転結がると納得して聞く。分かりやすく簡単な言葉で表現する。ここだけの話はお得感、満足感を生む。速さの調節を意識するとメリハリがつく。参加者が笑顔になるほど話が心に残る。
男女共同参画の例、数字も効果的
先進諸国の中で少子化を食い止めた国は、婚外子の出生率の高い国なんです。「夫の家事を促す」ことじゃない。
たとえば、スウェーデンでは56%、デンマークは44.9%、アメリカでは34%の人が婚外子なんです。日本は1.93%です。(読売新聞)
つまり、婚外子でも育てやすい環境があれば、「子供を産んでもいいか」と思う女性がいるということなんです。
p191 プロフィール原稿を作る。
自分の写真、プロフィール、講演テーマ、講演実績
p206,207 受付シート、決定シートをつくる
p217 ホームページ、ブログ、メルマガ100%活用
この辺は本当に実務レベルです。
プロフィール原稿は実際のものを自分で作りました。
もちろん講師の仕事だけで食べていけるとは思いませんし、本業はあくまで教師であり、ファシリテーターの活動は本業を生かした派生的な仕事です。
それでも、自分の所属している団体の活動について多くの人に知ってもらうことは、きっと社会貢献になると思うので、これからも続けていこうと思います。
ファシリテーターの資格を取ってから、何度か講師として仕事をしてきました。
震災関連の勉強も続けなくてはならないし、ファシリテーターとしてスキルを磨く勉強もしなくてはなりません。
今後、講師として年間数件の依頼をこなすにしても、自分が講師としてレベルアップするために必要なことがあるかもしれないと思ったので、読んでみました。
著者はもと吉本興業のマネージャーの方のようで、芸人さんたちのニュースでも話題になっていた契約書についても、少し触れられていました。
目次
はじめに
第一章 講師に必要な心構えは「志」! ~マインド編~
1 講師とは何か?
講師を頼まれたら、あなたの世界を広げるチャンス
「寝かさない講師」になろう
マイクとマインドがあれば世の中は変えられる
「かけてもらいたい言葉」という目標を持つ
2 目的を明確にする
まずは「何のため」に話すのかを考える
講演のゴールを決める
メッセージはとことん追求しよう
講師の役目は社会への恩返し
3 「志」を持つ
何を伝えるために呼ばれたのか
熱い「志」が「伝わる」工夫を生む
自分がやらなければ誰がやる!
「伝わる」から「伝える」へ
三種類の講師別・求められるもの
第二章 講師になったら知っておきたいスキル・テクニック ~実践編~
4 台本を作る
五分ネタをたくさん作る
不幸すぎる経験もネタになる
話がどんどん広がるネタ帳作り
「例え話」で聞き手は身を乗り出す
人の心は「挑戦」と「共感」で動く
失敗体験は共感をえやすい
成功体験は「スキル」に落とし込め
「離陸の瞬間」を語ると聞き手は「ハッ」とする
「事実を飛躍させ、誇張して話す」技術
5 メリハリをつける
最初の三分、「ツカミ」で勝負!
聞き手を安心させる「まず結論から」の鉄則
「思い」と「スキル」はワンセット
「へー」「ホー」と夢中にさせるコツ
五分ネタの中に起承転結を
クイズタイムで聞き手を引き込む
「語呂合わせ」で印象に残す
説得力に欠けるときは、「人の言葉を借りる」
講演の余韻はシメしだい
6 ブラッシュアップする
ほかの講師の話は必ず自分に生かす
アンテナを立てて、スキマ時間も情報収集
自分の姿をビデオ撮影してみる
やっぱり声は大きいほうがいい
「五つのS」を意識する
小道具を使って聞き手を引きつける
本番用で使える「3ポイント式アンチョコ」
「これが最後の公演」という気持ちで
7 前日までの準備
主催者の意図は、はずさない
事前打ち合わせでは、できる講師の必須事項
相手の情報を入手しておくと喜ばれる
早めに行って会場の下見をする
健康管理で穴をあけない
コスプレもアリ!衣装で聞き手を引きつける
講演前の「必要なものリスト」
未来につながるレジュメ作り
懇親会からうまく抜け出せる魔法の一言
8 当日、本番前にすること
あがるのは、当たり前のこと
ホワイトボードのペンは必ずインクが切れている
プロジェクターに頼りすぎない
9 本番中のテクニック
寝ている人は、いじり倒せ
楽しく話せば、楽しく聞いてもらえる
ツカミの三分、「笑わせる」には?
「うなずきくん」を見つける
質問タイムを引き締めるツボ
10 アクシデントに対処する
早めの行動があなたを救う
信頼は、台風からのプレゼント
時間通りに終わるにはちょっとしたコツがある
非常事態! 講演中にトイレに行くワザ
鳴った携帯電話は、「突っ込み→笑い」
「出ていってください」と言ってもよい
ホームとアウェイでは戦い方が変わる
第三章 指名される講師になるプロの技 ~ステップアップ編~
11 指名を増やす
半年後、一年後、三年後の自分をイメージする
プロ講師はつねに競争にさらされている
できる講師は自分で売り込まない
マネージャーを持てば、ぐんと仕事が広がる
仕事がどんどん増える「相手を立てる」コツ
悪いうわさはすぐに広まると心えよ
出会った証に、ちょっとしたおみやげを
12 自分ブランドを確立する
プロフィールはA4一枚
写真だけで魅力を伝えるポイント
アンケートは次の講演への大事な財産
顧客リストはこうして有効活用
自分の本は、講師の究極の名刺
プロ講師なら知っておきたい講演料の決め方
13 活動の幅を広げる
「受付シート」「決定シート」を作る
できる講師はエージェントとのつき合い方がうまい
プレスリリース一つで集客がちがう!
企業のトップ向けに講演できる講師になる
やっぱり自分でセミナーを開くのは魅力的
ホームページ、ブログ、メルマガの100%活用法
持てるものなら「自分のセミナールーム」
【自分の読書メモ】
p22 「目の前の人にどうなってほしいのか」「目の前の人にどうやったら伝わるのか」、技術や方法を学ぶ前に、まず大切なのは自分自身の「志」を明確にすること
p64 成功体験を「誰でもできるスキル」に落とし込んで話す。抽象的な話は自慢話になってしまう。具体的な誰でもできるスキルにすれば「私でもできそう」と感じてもらえる。
p78 スキルの流行
・アサーティブ ・コーチング ・NLP ・コミュニケーション ・ファシリテーション
・メンタルヘルス ・モチベーションマネジメント ・オフサイトミーティング
p104 5つのS(Story、Simple、Special、Speed、Smile)
ストーリー、シンプル、スペシャル、スピード、スマイル
起承転結がると納得して聞く。分かりやすく簡単な言葉で表現する。ここだけの話はお得感、満足感を生む。速さの調節を意識するとメリハリがつく。参加者が笑顔になるほど話が心に残る。
男女共同参画の例、数字も効果的
先進諸国の中で少子化を食い止めた国は、婚外子の出生率の高い国なんです。「夫の家事を促す」ことじゃない。
たとえば、スウェーデンでは56%、デンマークは44.9%、アメリカでは34%の人が婚外子なんです。日本は1.93%です。(読売新聞)
つまり、婚外子でも育てやすい環境があれば、「子供を産んでもいいか」と思う女性がいるということなんです。
p191 プロフィール原稿を作る。
自分の写真、プロフィール、講演テーマ、講演実績
p206,207 受付シート、決定シートをつくる
p217 ホームページ、ブログ、メルマガ100%活用
この辺は本当に実務レベルです。
プロフィール原稿は実際のものを自分で作りました。
もちろん講師の仕事だけで食べていけるとは思いませんし、本業はあくまで教師であり、ファシリテーターの活動は本業を生かした派生的な仕事です。
それでも、自分の所属している団体の活動について多くの人に知ってもらうことは、きっと社会貢献になると思うので、これからも続けていこうと思います。
【読書】超メモ術を読みました。 ― 2019/10/27

倉下忠憲さん、高畑正幸さんが監修しています。
このお二人はHACK系では非常に有名なので、きっとご存知だと思います。
お二人のやり方、考え方が凝縮されて、きれいにまとめられています。
目次
メモとアイデアの関係って?
PART1 アイデア発想のための7つの習慣とメモメソッド
【アイデア体質に近づくための7つの習慣】
01 日常からアイデアの種を拾い集める
02 位相の異なるインプットを心がける
03 アイデアの種を貯蔵する
04 アイデアの種を育てる
05 複数の異なる視点から眺める
06 新たな組み合わせを探す
07 アクティブな問題解決者となる
【アイデアを生み出すメモメソッド】
01 ユビキタスキャプチャー
02 コーネル式ノート
03 マインドマップ
04 マンダラート
05 アイデアトリガーカード
06 KJ法
07 アイデアマラソン
番外編 倉下流!とpっておきのメモ整理術
PART2 おすすめメモツール
文具王・高畑正幸が教えるメモツール活用
アイデアを生み出す なるほどメモ術
メモ帳・ノート編
ペン編
その他のもの
機器・文房具編etc.
5人に聞きました! アイデアを生み出すためのメモ術
【自分の感想】
PART1がメモ術についての考え方や取り組み方、基本的な技術を整理したものになっているので、ここさえ読めばOKな気がします。
もちろん、今までにメモ術・ノート術を学んできた方はほとんど知っている内容だと思います。
初めて興味をもつ方にとっては、シンプルに整理されていて分かりやすいと思います。
私は再確認という感じで読みました。
それ以外も読めば面白いです。ワクワクしてきます。
ただ、2015年の本なので、決して最新のやり方ではないと言われそうです。
本書の中ではEvernoteを情報整理したメモの最終ゴール地点として扱ったり、アナログとデジタルの併用のためのツールとして扱ったりしています。
しかし、最近のHACK系の雑誌・記事を読んでいると、EvernoteよりはGoogleDriveにシフトしているように思います。
その理由はおそらく、GoogleはPDF等も全文検索が可能だからです。
Evernoteのように、ノートブックとタグを使いこなして整理しようとして悪戦苦闘するくらいなら、
Googleにすべて入れておいてキーワードで一本釣りするほうがいい、というイメージですかね。
有料会員になればEvernoteも一本釣りはできるので、そこまでの差異は感じませんがどうなんでしょうか。
私自身は今でもEvernoteを使っていますが、使いこなしているかと言われるとはなはだ疑問です。
Windowsのエクスプローラ(ノートブックとして)とWord(ノートとして)で十分じゃないかと思うことはしばしばです。
GoogleDriveについて調べてみようかな。
去年、共同研究でファイル共有に使ったのですが、あの時もよく分からずに使っていたな…。
メモ術の話で始まり、クラウドサービスの話で終わった…。
このお二人はHACK系では非常に有名なので、きっとご存知だと思います。
お二人のやり方、考え方が凝縮されて、きれいにまとめられています。
目次
メモとアイデアの関係って?
PART1 アイデア発想のための7つの習慣とメモメソッド
【アイデア体質に近づくための7つの習慣】
01 日常からアイデアの種を拾い集める
02 位相の異なるインプットを心がける
03 アイデアの種を貯蔵する
04 アイデアの種を育てる
05 複数の異なる視点から眺める
06 新たな組み合わせを探す
07 アクティブな問題解決者となる
【アイデアを生み出すメモメソッド】
01 ユビキタスキャプチャー
02 コーネル式ノート
03 マインドマップ
04 マンダラート
05 アイデアトリガーカード
06 KJ法
07 アイデアマラソン
番外編 倉下流!とpっておきのメモ整理術
PART2 おすすめメモツール
文具王・高畑正幸が教えるメモツール活用
アイデアを生み出す なるほどメモ術
メモ帳・ノート編
ペン編
その他のもの
機器・文房具編etc.
5人に聞きました! アイデアを生み出すためのメモ術
【自分の感想】
PART1がメモ術についての考え方や取り組み方、基本的な技術を整理したものになっているので、ここさえ読めばOKな気がします。
もちろん、今までにメモ術・ノート術を学んできた方はほとんど知っている内容だと思います。
初めて興味をもつ方にとっては、シンプルに整理されていて分かりやすいと思います。
私は再確認という感じで読みました。
それ以外も読めば面白いです。ワクワクしてきます。
ただ、2015年の本なので、決して最新のやり方ではないと言われそうです。
本書の中ではEvernoteを情報整理したメモの最終ゴール地点として扱ったり、アナログとデジタルの併用のためのツールとして扱ったりしています。
しかし、最近のHACK系の雑誌・記事を読んでいると、EvernoteよりはGoogleDriveにシフトしているように思います。
その理由はおそらく、GoogleはPDF等も全文検索が可能だからです。
Evernoteのように、ノートブックとタグを使いこなして整理しようとして悪戦苦闘するくらいなら、
Googleにすべて入れておいてキーワードで一本釣りするほうがいい、というイメージですかね。
有料会員になればEvernoteも一本釣りはできるので、そこまでの差異は感じませんがどうなんでしょうか。
私自身は今でもEvernoteを使っていますが、使いこなしているかと言われるとはなはだ疑問です。
Windowsのエクスプローラ(ノートブックとして)とWord(ノートとして)で十分じゃないかと思うことはしばしばです。
GoogleDriveについて調べてみようかな。
去年、共同研究でファイル共有に使ったのですが、あの時もよく分からずに使っていたな…。
メモ術の話で始まり、クラウドサービスの話で終わった…。
【読書】「ファシリテーションスキル超入門」を読みました ― 2019/03/30

「『明日からリーダーやって』と言われた人のファシリテーションスキル超入門」
(草地真/ぱる出版)
という少々長いタイトルの本を読みました。
昨年から何回か大学に通って研修を受け、ファシリテーション技法を用いて、あるテーマについて講義を行うことができるようになりました。
テーマについては専門外でもあったので、理論的に難しい部分もありました。
しかし、自分自身の体験もあり、理解もしやすく、興味深く学ぶことができました。
そして内容が理解できたところで、自分は「ファシリテーションとは何ぞや?」ということを分かっていないことに気が付きました。
資格を取るためには、検定試験をクリアしなくてはいけません。
自分がやっていきたいと考えていたことを、具体的な実現できるチャンスです。
そんなわけで、ちょっと慌ててファシリテーションについての本を図書館で借りて読むことにしました。
この本はタイトル通り、ファシリテーションを言葉でしか聞いたことがない人間にとっては、とてもありがたいレベルの分かりやすさでした。
【目次】
1 ファシリテーションって何?
2 なぜ、ファシリテーションスキルが必要なの?
3 ファシリテーション型会議の進め方
4 ファシリテーションスキルが高まる9つのポイント
5 ファシリテーションスキルはいろんな場面で応用できる
6 ファシリテーションの究極は“当事者意識”を引き出すこと!!
【ファシリテーターに求められる9のスキル】
(1)場を作る力(雰囲気・進め方)
(2)全体を設計する力(場のデザイン力・プログラム力)
(3)先を読む力(パースペクティブ)、洞察力・直観力
(4)聴く力(傾聴力)、聞く力(質問力)
(5)伝える力…全体を巻き込む力
(6)引き出す力…自分は身を消して、チームの力を最大限
(7)書く(書き取る)力…記録力、ポストイット作戦、売れた理由・売れない理由
(8)まとめる力…論理力・図解力・構造化
(9)共有する力…わかち合い
【ファシリテーションの基本ステップ】
ステップ1 チェックイン → 場の設定
ステップ2 課題・テーマの共有
ステップ3 拡散
ステップ4 混沌
ステップ5 収束
ステップ6 共有
ステップ7 チェックアウト → 次のアクションにつなげる
(草地真/ぱる出版)
という少々長いタイトルの本を読みました。
昨年から何回か大学に通って研修を受け、ファシリテーション技法を用いて、あるテーマについて講義を行うことができるようになりました。
テーマについては専門外でもあったので、理論的に難しい部分もありました。
しかし、自分自身の体験もあり、理解もしやすく、興味深く学ぶことができました。
そして内容が理解できたところで、自分は「ファシリテーションとは何ぞや?」ということを分かっていないことに気が付きました。
資格を取るためには、検定試験をクリアしなくてはいけません。
自分がやっていきたいと考えていたことを、具体的な実現できるチャンスです。
そんなわけで、ちょっと慌ててファシリテーションについての本を図書館で借りて読むことにしました。
この本はタイトル通り、ファシリテーションを言葉でしか聞いたことがない人間にとっては、とてもありがたいレベルの分かりやすさでした。
【目次】
1 ファシリテーションって何?
2 なぜ、ファシリテーションスキルが必要なの?
3 ファシリテーション型会議の進め方
4 ファシリテーションスキルが高まる9つのポイント
5 ファシリテーションスキルはいろんな場面で応用できる
6 ファシリテーションの究極は“当事者意識”を引き出すこと!!
【ファシリテーターに求められる9のスキル】
(1)場を作る力(雰囲気・進め方)
(2)全体を設計する力(場のデザイン力・プログラム力)
(3)先を読む力(パースペクティブ)、洞察力・直観力
(4)聴く力(傾聴力)、聞く力(質問力)
(5)伝える力…全体を巻き込む力
(6)引き出す力…自分は身を消して、チームの力を最大限
(7)書く(書き取る)力…記録力、ポストイット作戦、売れた理由・売れない理由
(8)まとめる力…論理力・図解力・構造化
(9)共有する力…わかち合い
【ファシリテーションの基本ステップ】
ステップ1 チェックイン → 場の設定
ステップ2 課題・テーマの共有
ステップ3 拡散
ステップ4 混沌
ステップ5 収束
ステップ6 共有
ステップ7 チェックアウト → 次のアクションにつなげる
【読書】「<わかりやすさ>の勉強法」を読みました ― 2018/03/25
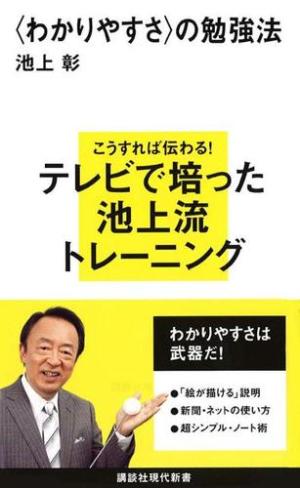
先日の新聞の話題から偶然の新聞ネタになりました。
池上彰さんの「分かりやすさの勉強法」という新書を見つけて、読んでみました。
2010年の本なので、東日本大震災の話題が入っていません。たまたまブックオフで108円という値段でしたが、古本とはいえ安すぎます。
池上さんの本は、FeBeでも『伝える力』などを購入して読んでいます。
テレビでもできるだけ見るようにしています。
授業力の向上に役立つヒントが見つかりそうだからです。多分に影響を受けています。
そんなわけで、池上さんが人に分かりやすく説明するために、普段からどのような勉強法をしているのかが分かります。
A4裏紙をメモ用紙として使うことや、クリアファイルに資料を貯めていくこと、クリアファイルで編集・整理する方法など、参考になるところがありました。
ストック情報とフロー情報の考え方と扱い方、新聞社の考え方の違い、スケジュール管理の方法なども知っておくといいなと思いました。
3部作のラストらしいので、いつか前の2冊を読むときがくるかもしれません。まぁ本屋さんで出会うのは至難でしょうけれど。。。
<目次>
第1章 テレビでプレゼンのヒントを学ぶ-テレビはプレゼンの勉強の宝庫だ
・綴じなければ、話の全体像が見える
・プレゼンテーションでも威力発揮
・テレビ出演でも威力発揮
・予習の程度がプレゼンの出来不出来を決定する
・キーワードを有効に活用しよう
・焦点の合わせ方が内容を左右する
・テレビは「わかりやすく伝える授業」の教室だ
第2章 話のキモ<中心テーマ>を見つけよう-伝えるべき中心テーマに
・気づけば、成功したも同然
・「自分は何がわからないか」を知ろう
・フロー情報とストック情報を使い分けよう
・話のキモとは「そもそもなぜ~なのか?」という疑問
・「検察審査会って、そもそもどうしてあるの?」
・問題意識を持ってストック情報にあたる
・常に根本的な疑問を持つようになった
・相手に話の地図を渡そう
・自分の中に湧いた素朴な疑問を大切に
・キモの部分をプレゼンの頭に持ってくる
・プレゼン原稿は、上司の突っ込み質問から書き始めてみる
・コラム1:話が枝葉に行きっぱなしにならないために
・コラム2:単純化しすぎてはいけない
第3章 プレゼン力を伸ばす-相手の頭の中に「絵」を描く
・話がうまいスタッフは「絵が描ける」
・絵を描ける説明とは
・具体的な言葉で「話のフック」をつくる
・「幼稚園と保育園の違い」を説明するとしたら
・伝達ゲームと考えよう
・自分の中で図解する
・待ち合わせ場所をどう説明しますか?
・何でも図にして考える
・民放の現場で鍛えられる
・「会社更生法」も具体的に「絵」に描ける
・思わぬ一般論から説明する手法もある
・コラム3:名前ネタはフックになる
・コラム4:「三分間」の感覚を身につけよう
第4章 新聞の読み方、ネットの使い方-じっくり熟読、記事を切り抜き
・生放送で新聞記事を解説する
・朝は新聞四紙に目を通す
・夜は八紙をじっくり読んでページを破る
・海外の新聞はメール配信で
・解説記事と署名記事に注目
・文章力をつけるには一面コラムの精読を
・つまらないコラムの理由を考える
・就職活動に日経新聞は必須か?
・読売新聞は外信面が充実
・書評欄、読書欄の充実度は朝日新聞
・記者同士の論争すらある毎日新聞
・日経新聞は商品面をチェック
・チーズの値段から意外な世界経済の流れが見える
・どうして私は紙の新聞にこだわるのか
・データとして手元にストックできる
・雑誌は拾い読みしてページを切る
・ネットは注意して活用する
・Gサーチや日経テレコンも
・NHKニュースを使う理由
・ひいきのブロガーを見つけよう
・コラム5:ベタ記事は隠れた宝石だ
第5章 クリアファイルで情報整理-持ち運べる“編集機”
・スクラップブックから試行錯誤
・新聞記事を切り抜かなくても
・持ち歩けるフロー情報ファイル
・ファイルは自然に枝分かれしていく
・フロー情報がストック情報に
・クリアファイル整理術にも欠点が
・自己流の編集力を
・クリアファイルは“編集樹”だ
第6章 本の読み方-本を「仕事の先輩」として活用する
・本は最強のストック情報
・ネットで参考文献をチェックする
・行きつけの書店をつくろう
・書店も売り場を“編集”している
・アマゾンの読書レビューの使い方
・新聞広告で売れ筋と新刊をチェック
・新聞に寄って書籍広告の内容は異なる
・ビジネス小説で楽しみながら学ぶ
・A4の裏紙を四つ折りにして本のメモに
・本は「まえがき」から読む
・本を読む時間をどうつくるか
・コラム6:「伝えること」は情報の「呼び水」になる
第7章 ノートのとり方、メモのとり方-アナログだって有効だ
・電子手帳は使わない
・手帳はスケジュール専用
・取材ノートは左右のページを使い分け
・ビジネスへも応用可能
・レポート用紙で再整理も
・取材旅行には大学ノート
・A4の裏紙メモも活用
第8章 わかりやすい文章を書くために-「わかりにくい説明」を見つけてみよう
・「子ども向け解説」はわかりやすいか?
・「国際金融システムが正常に機能」?
・世界史嫌いは教科書に問題があった
・専門家が陥りやすい失敗がある
・企業小説にはなぜ素人が登場するのか
・優れたブロガーの文章も参考になる
・理解していないと抽象的になってしまう
・「耳で聞いてわかる」表現を
第9章 聞き上手は伝え上手になれる-まずは相手の話を聞いてから
・相手の表情を見よう
・相手が話しやすくなるリアクションを
・声に出さずに表情で聞く方法もある
・聞き下手のタイプ1 準備した順番通りに聞く
・聞き下手のタイプ2 自分のストーリーに縛られる
・準備してきたメモは忘れよう
・田原総一郎さんは「準備したら捨てる」
・「いい質問ですねぇ」は「いい反応」を引き出す
・「相手を認める」聞き方
・質問してくれた相手を大事にする
第10章 時間を有効に使ってみよう-細切れ時間も利用次第
・「集中できた」経験を忘れずに
・細切れ時間の活用法
・満員電車の中では……
・新幹線の往復時間
勉強って何だろう-「終わりに」に代えて
池上彰さんの「分かりやすさの勉強法」という新書を見つけて、読んでみました。
2010年の本なので、東日本大震災の話題が入っていません。たまたまブックオフで108円という値段でしたが、古本とはいえ安すぎます。
池上さんの本は、FeBeでも『伝える力』などを購入して読んでいます。
テレビでもできるだけ見るようにしています。
授業力の向上に役立つヒントが見つかりそうだからです。多分に影響を受けています。
そんなわけで、池上さんが人に分かりやすく説明するために、普段からどのような勉強法をしているのかが分かります。
A4裏紙をメモ用紙として使うことや、クリアファイルに資料を貯めていくこと、クリアファイルで編集・整理する方法など、参考になるところがありました。
ストック情報とフロー情報の考え方と扱い方、新聞社の考え方の違い、スケジュール管理の方法なども知っておくといいなと思いました。
3部作のラストらしいので、いつか前の2冊を読むときがくるかもしれません。まぁ本屋さんで出会うのは至難でしょうけれど。。。
<目次>
第1章 テレビでプレゼンのヒントを学ぶ-テレビはプレゼンの勉強の宝庫だ
・綴じなければ、話の全体像が見える
・プレゼンテーションでも威力発揮
・テレビ出演でも威力発揮
・予習の程度がプレゼンの出来不出来を決定する
・キーワードを有効に活用しよう
・焦点の合わせ方が内容を左右する
・テレビは「わかりやすく伝える授業」の教室だ
第2章 話のキモ<中心テーマ>を見つけよう-伝えるべき中心テーマに
・気づけば、成功したも同然
・「自分は何がわからないか」を知ろう
・フロー情報とストック情報を使い分けよう
・話のキモとは「そもそもなぜ~なのか?」という疑問
・「検察審査会って、そもそもどうしてあるの?」
・問題意識を持ってストック情報にあたる
・常に根本的な疑問を持つようになった
・相手に話の地図を渡そう
・自分の中に湧いた素朴な疑問を大切に
・キモの部分をプレゼンの頭に持ってくる
・プレゼン原稿は、上司の突っ込み質問から書き始めてみる
・コラム1:話が枝葉に行きっぱなしにならないために
・コラム2:単純化しすぎてはいけない
第3章 プレゼン力を伸ばす-相手の頭の中に「絵」を描く
・話がうまいスタッフは「絵が描ける」
・絵を描ける説明とは
・具体的な言葉で「話のフック」をつくる
・「幼稚園と保育園の違い」を説明するとしたら
・伝達ゲームと考えよう
・自分の中で図解する
・待ち合わせ場所をどう説明しますか?
・何でも図にして考える
・民放の現場で鍛えられる
・「会社更生法」も具体的に「絵」に描ける
・思わぬ一般論から説明する手法もある
・コラム3:名前ネタはフックになる
・コラム4:「三分間」の感覚を身につけよう
第4章 新聞の読み方、ネットの使い方-じっくり熟読、記事を切り抜き
・生放送で新聞記事を解説する
・朝は新聞四紙に目を通す
・夜は八紙をじっくり読んでページを破る
・海外の新聞はメール配信で
・解説記事と署名記事に注目
・文章力をつけるには一面コラムの精読を
・つまらないコラムの理由を考える
・就職活動に日経新聞は必須か?
・読売新聞は外信面が充実
・書評欄、読書欄の充実度は朝日新聞
・記者同士の論争すらある毎日新聞
・日経新聞は商品面をチェック
・チーズの値段から意外な世界経済の流れが見える
・どうして私は紙の新聞にこだわるのか
・データとして手元にストックできる
・雑誌は拾い読みしてページを切る
・ネットは注意して活用する
・Gサーチや日経テレコンも
・NHKニュースを使う理由
・ひいきのブロガーを見つけよう
・コラム5:ベタ記事は隠れた宝石だ
第5章 クリアファイルで情報整理-持ち運べる“編集機”
・スクラップブックから試行錯誤
・新聞記事を切り抜かなくても
・持ち歩けるフロー情報ファイル
・ファイルは自然に枝分かれしていく
・フロー情報がストック情報に
・クリアファイル整理術にも欠点が
・自己流の編集力を
・クリアファイルは“編集樹”だ
第6章 本の読み方-本を「仕事の先輩」として活用する
・本は最強のストック情報
・ネットで参考文献をチェックする
・行きつけの書店をつくろう
・書店も売り場を“編集”している
・アマゾンの読書レビューの使い方
・新聞広告で売れ筋と新刊をチェック
・新聞に寄って書籍広告の内容は異なる
・ビジネス小説で楽しみながら学ぶ
・A4の裏紙を四つ折りにして本のメモに
・本は「まえがき」から読む
・本を読む時間をどうつくるか
・コラム6:「伝えること」は情報の「呼び水」になる
第7章 ノートのとり方、メモのとり方-アナログだって有効だ
・電子手帳は使わない
・手帳はスケジュール専用
・取材ノートは左右のページを使い分け
・ビジネスへも応用可能
・レポート用紙で再整理も
・取材旅行には大学ノート
・A4の裏紙メモも活用
第8章 わかりやすい文章を書くために-「わかりにくい説明」を見つけてみよう
・「子ども向け解説」はわかりやすいか?
・「国際金融システムが正常に機能」?
・世界史嫌いは教科書に問題があった
・専門家が陥りやすい失敗がある
・企業小説にはなぜ素人が登場するのか
・優れたブロガーの文章も参考になる
・理解していないと抽象的になってしまう
・「耳で聞いてわかる」表現を
第9章 聞き上手は伝え上手になれる-まずは相手の話を聞いてから
・相手の表情を見よう
・相手が話しやすくなるリアクションを
・声に出さずに表情で聞く方法もある
・聞き下手のタイプ1 準備した順番通りに聞く
・聞き下手のタイプ2 自分のストーリーに縛られる
・準備してきたメモは忘れよう
・田原総一郎さんは「準備したら捨てる」
・「いい質問ですねぇ」は「いい反応」を引き出す
・「相手を認める」聞き方
・質問してくれた相手を大事にする
第10章 時間を有効に使ってみよう-細切れ時間も利用次第
・「集中できた」経験を忘れずに
・細切れ時間の活用法
・満員電車の中では……
・新幹線の往復時間
勉強って何だろう-「終わりに」に代えて
新聞って安いんだな~ ― 2018/03/24

今朝、人事異動について新聞発表されるので、コンビニへ行って買ってきました。
コンビニのレジで支払うときに、「120円です。」と言われて、驚いてしました。
あれ?新聞ってこんなに安いんだなー、と。
我が家は新聞を取っていません。
今回のような特別なときだけ買ってきて眺めるだけで、毎日は必要としていません。
私に読む余裕がないこと、子供達が小さいこと、ネットとテレビで満足していること。
この辺が理由です。
しかし、この値段でこの情報量を考えると、すごいコストパフォーマンスです。
月3600円、年間43200円。どうでしょうね。合計すると高く感じてしまいますね、主なニュースはネットで無料で知ることができますからね。
もう少し子供達が大きくなって、落ち着いて新聞を広げて読めるくらいになったら、一誌くらい定期購読してもいいのかな?と感じました。
私の実家では、新聞をたくさん取っていました。
地方紙一誌、農家なので農業新聞一誌、投資もしているので経済紙一誌。
ちょっと忘れましたけど、少なくとも3誌。それ以外に一誌くらいあったように思います。
それを父親が一人で全部読むのです。
しかも広告スペースも含めて隅から隅まで読むのです。
読みきれる訳がありません。さらに質の悪いことに、読み終わらないと処分しないのです。
ですから、家のなかは新聞に溢れていました。
家族みんなが辟易していましたが、いくら言っても変わらない父でした。
密かに少しずつ処分しても気付かれないのだけは、幸いでした(幸い?)。
もしもスマホやパソコンでインターネットを使ってたら、どうなっていたのかな?
新聞には、そんな思い出があります。
さて、我が家はどうなるのかな?
【読書】『PDCA手帳術』を読みました。 ― 2018/03/17
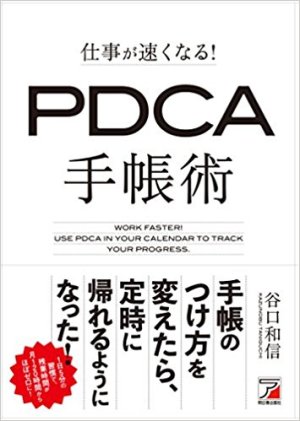
先日、『鬼束PDCA』を読んだからだと思いますが、立ち寄ったコンビニで目に入ったので、手に取ってちょっと立ち読みした後、購入してしまいました。
3日で読み終えた本です。(こんなに早く読める本は久しぶりかも)
実は内容がほとんど知っていることでした。
それでも、著者も最後に言っているように、知っているだけでは意味がなくて、実践しなければ仕方ないのです。
ですから、手帳を使い始める初心者の方や、私のようにPDCAを手帳で実践しようとしている人にはおすすめです。
さて、第1章~第5章までは手帳術愛好家(笑)としては、ほとんど知っていることなので飛ばします。
あ、「パーキンソンの第1法則」というのは、概念は知っていましたが法則としては知りませんでした。紹介しておきます。
「パーキンソンの第1法則」
…仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する。
確かに、もう終わらせてもいいのに、締め切りギリギリまで仕事を続けることってありますよね。
その与えられた時間というのを、自分の意志で「締め切り」として早めに設定すればいいのです。そしてそれを手帳で管理すれば、どんどん成果を挙げることができます。
子供たちが宿題が終わらないという理由の一つはコレですね。
ちなみに、第1があるなら続きもあるのかと調べてみました。ありました。
「パーキンソンの第2法則」
…支出の額は、収入の額に達するまで膨張する。
だそうです。なんか、膨張するって言い方が、エントロピーみたいですね。
いよいよ、第6章です。「振り返り」について悩んでいたので、目次から気になっていました。
第6章は、ログのとり方から振り返りの仕方について書かれています。
特に私としては、振り返りの項目についてなるほどと思いました。
【振り返りの項目】
① 今週の大きな出来事 TOP5
② 今週学んだこと
③ 今週やったことで誇れること
④ 今週やったことで、いちばん楽しかったこと
⑤ 今週やったことで特筆すべきこと、未来を楽にする仕事はなにか?
【翌週に向けて】
⑥ 先週からの課題
⑦ 増やしたいこと
⑧ 減らしたいこと
⑨ 何をするともっと楽しくなるか?
⑩ どうすればそれができるか?
これらについて、毎日のログから毎週、毎月、そして年末にレビューするようにするのです。
これらの項目について目新しかった訳ではありません。
次のページ(p220)で「振り返る項目は定期的に見直す」として、「振り返る内容に大してもPDCAを回す」ように提案しています。
ここが「なるほど!」でした。
今まで、振り返りは大事だと思っていたのですが、何について振り返ればいいのか考えこんでしまって、結果振り返れないということが多かったのですが、そんな不安は持たなくていいのです。
座右の銘「試してみることに失敗はない」がここでも生きてきます。
振り返りをやってみて、うまくいかない、しっくりこないとなれば変えればいいのです。変えてみてダメだったら戻せばいいのです。戻ったとしても、それはプラスマイナスゼロになるのではなく、学びがあったぶんプラスになるのです。
そんなわけで、まずは上記の項目で振り返りをしてみて、そこから少しずつ内容を変えていこうと思いました。
はい、思っただけではだめですね。実践・実行しなければ意味がありません。
『鬼束PDCA』と合わせて、PDCAの考え方を手帳やワークライフバランスに取り入れるには、タイムリーな本でした。
目次
はじめに
第1章 何のために手帳を使うのか?
01 何のために手帳を使うのか?
02 どんな手帳にしたいのか、コンセプトを決める
03 手帳でできることとメリット・デメリット
04 手帳やメモ・ノートは忘れるために使う
05 頭の中だけで考えない
第2章 手帳の基本
01 手帳のフォーマットとその特徴
02 手帳でできることと基本的な使い方
第3章 仕事が速くなるタスク管理術
01 すべての仕事を把握する
02 GTDでタスクと仕事を整理する
03 プロジェクトをタスクに分解する方法
04 なぜタスクリストだけでは上手くいかないのか?
05 所要時間は、自分で考えた時間の1・5倍見込む
06 自分締切で余裕を作る
07 締切から逆算してペース配分を決める
08 時間と品質のバランスをとる
09 仕事が速くなるタスクリストの作り方
第4章 仕事が速い人の手帳の使い方【基礎編】
01 手帳の使い方
02 手帳に予定を記入する
03 スケジュール管理は1か所で
04 重要なタスクはスケジュールといっしょに管理する
05 ウィークリーの時間軸での管理が必須
06 予定とメモが一覧できる週間レフト型がオススメ
07 マンスリーで全体を見て、ウィークリーでタスク管理
08 複数プロジェクトは「ガントチャート」で管理
09 手帳といっしょに使いたい便利グッズ
第5章 仕事が速い人の計画の立て方
01 仕事の速さは段取りで決まる
02 スケジュールで最初に決めるのは退社時間
03 仮の予定もどんどん入れる
04 理想的な1日の過ごし方を書いてみる
05 24時間の使い方を記録する
06 自分だけの時間割を作る
07 優先順位のつけ方
08 小さなタスクはまとめて処理
09 予備の時間(バッファ)を持つ
10 手帳は常に開いて机に置いておく
11 それでもやる気が出ないときは
第6章 仕事が速い人の改善方法
01 手帳に書くのは予定だけではない
02 行動結果をチェックする
03 自分の時間がどんな内訳か書き出す
04 仕事がはかどる時間帯を知る
05 得意な(疲れていても効率が落ちない)仕事を知る
06 好きで得意な仕事は要注意
07 イライラしたこと・感情的になったことを振り返る
08 明日の課題を書く
09 今日の課題ができたかどうか振り返る
10 今日1日に点数をつける
11 毎日・毎週・毎月読み返す
12 振り返る項目は定期的に見直す
13 何のためにライフログをとるのか?
おわりに
【読書】『鬼束PDCA』を読みました ― 2018/03/10
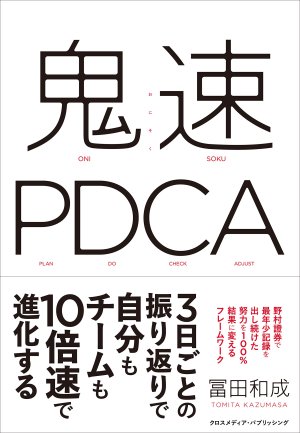
正直に申しますと、週次レビューが習慣化していません。
ゼロ秒思考メモで、そのときの考えるべきことを吐き出しています。(A4裏紙)
毎日書いているライフログの中に、吹き出しの形で「気付き」を書いています。(手書き)
ワークライフバランス日記として、仕事とプライベートについて日記を書き、その読み返しの中で気付いたことを、さらに四角で囲んで追記しています。(パソコン)
そういうことの積み重ねが成長だと思うのですが、それをまとめる機会がなかなか作れないのです。
そのため、気付き=成長の種が散乱しており、どこからも芽が出てこないように感じています。
この悩みを抱き始めてから、(別の言い方をすると、これはPDCAが回っていないのではないか?)と思うようになりました。
そして見つけた(以前から知ってはいた)本として、『鬼束PDCA』を読んでみることにしました。
ゼロ秒思考メモが習慣化してきたので、つぎのビジネス書としていいかなと思い、古本屋さんでゲットしました。
卒業式間際の忙しい合間になんとか読み終えて、今こうして書いています。
しかし、これを実践するのはなかなか気合が要ります。各種ツールはダウンロードしてみたので、手帳にこれを取り込む工夫を今は考えているところです。
私のシステム手帳は、スケジュール管理の「教師手帳(週間バーチカル)」と、日々の記録を時系列と思い付きで書いていく「ライフログノート」と、ある期間にわたって記録が必要になる「プロジェクトノート」から出来ています。
そんなわけで、『鬼束PDCA』を取り入れるのは「プロジェクトノート」のところだと思っているのですが、なかなかそこまで行きつかないんですね。
年度末に発生した「卒業生に3年間のスライドショーをDVDにしてプレゼントする」プロジェクトは、『鬼束PDCA』を少し意識したのですが、「WLB日記」でやってしまいました。
仕事は他から与えられてやるだけでなく、自分でプロジェクトとして立ち上げることもできます。
第2領域に取り組むには、このプロジェクト化が欠かせないということも分かっているのですが。。。
何か新しいプロジェクトを立ち上げたときに、また試してみようと思います。ものすごい成長ツールであることだけはよーく分かりましたから。
【目次】 を挙げておきます。目次を見ただけでも、内容が想像できますが、オリジナルの用語もあり、読まないと分からないかもしれません。
はじめに
1章 前進するフレームワークとしてのPDCA
PDCAこそ最強のビジネススキルである
企業・リーダーの価値もPDCA力で決まる
世間が抱くPDCAの6つの誤解
1 簡単だと思っている
2 管理職向けのフレームワークだと思っている
3 失敗するのは検証(C)が甘いからだと思っている
4 課題解決のためのフレームワークだと思っている
5 改善さえすれば終わっていいと思っている
6 大きな課題のときだけ回せばいいと思っている
PDCAのスケール感を意識せよ
証券マン時代に実践した鬼速PDCA
前に進むのがどんどん楽しくなる
鶏と卵の関係にあるPDCAと自信
鬼速PDCAとは何か
1 計画(PLAN)
2 実行(DO)
3 検証(CHECK)
4 調整(ADJUST)
2章 計画初級編:ギャップから導き出される「計画」
慎重さと大胆さのバランスが肝になる計画
ステップ1 ゴールを定量化する(KGIの設定)
1 期日を決める
2 定量化する
3 ゴールを適度に具体的なものにする
ステップ2 現状とのギャップを洗い出す
ステップ3 ギャップを埋める課題を考える
ステップ4 課題を優先度づけして3つに絞る
1 インパクト(効果)
2 時間
3 気軽さ
優先度づけのヒント
ステップ5 各課題をKPI化する
ステップ6 KPIを達成する解決案を考える
ステップ7 解決案を優先度づけする
ステップ8 計画を見える化する
上位PDCAを再確認する
ときに思考のリミッターを外す
鬼速クエスチョン 計画編
3章 計画応用編:仮説の精度を上げる「因数分解」
PDCAの速さと深さは因数分解で決まる
因数分解のメリット
1 課題の見落としを防ぐ
2 ボトルネックの発見がしやすい
3 KPI化しやすい
4 どんなゴールでも実現可能に思えてくる
5 PDCAが速く深く回る
ポイント1 抽象度を上げてから分解する
ポイント2 5段目まで深掘りする
ポイント3 1段目だけはMECEを徹底する
ポイント4 切り方に悩んだら「プロセス」で切る
ポイント5 簡単な課題は「質 × 量」で切る
ポイント6 とにかく文字化する
ポイント7 マインドマップで鍛える
活用のヒント1 紙よりもパソコン
活用のヒント2 PDCAのフレームは忘れる
活用のヒント3 時間がないなら時間を決めて行う
活用のヒント4 気になったら分解してみる
活用のヒント5 ワクワクしながらやる
4章 実行初級編:確実にやり遂げる「行動力」
解決案とDOとTODOの違い
実行できないケース1 計画自体が失敗している
実行できないケース2 タスクレベルまで落とし込まれていない
実行できないケース3 失敗することが恐い
ステップ1 解決案を「DO」に変換する
解決案が具体的か抽象的か
完結型のDOと継続型のDO
ステップ2 DOに優先順位をつけ、やることを絞る
ステップ3 DOを定量化する(「KDI」を設定する)
1 完結型のDOのKDI化
2 継続型のDOのKDI化
ステップ4 DOを「TODO」に落とし込む
ステップ5 TODOの進捗確認をしながら実行に移す
TODOを管理するコツ
おすすめのTODO管理アプリ
TODOの共有
定番のポストイットも活用
「人」に潜むリスクに気を配る
セルフトークでPDCAを促進
「終わらなくてもいい」という割り切りも重要
鬼速クエスチョン 実行編
5章 実行応用編:鬼速で動くための「タイムマネジメント」
なぜ、いつのまにか忙殺されるのか?
タイムマネジメントの3大原則
「捨てる」ために既存のDOの棚卸しをする
「入れかえ」のために重要・緊急マトリクスを使う
「時間圧縮」のためにルーチンを見直す
「重要・非緊急」領域を実行する方法
1 仕組み化し、日常生活に組み込む
2 強制的に「緊急領域」に移動する
6章 検証:正しい計画と実行の上に成り立つ「振り返り」
検証に失敗する2大パターン
1 検証をしない「やりっぱなし派」
2 検証しかしない「形から入る派」
ステップ1 KGIの達成率を確認する
ステップ2 KPIの達成率を確認する
ステップ3 KDIの達成率を確認する
ステップ4 できなかった要因を突き止める
KDIが計画通り推移していないとき
KPIが計画通り推移していないとき
KGIが計画通り推移していないとき
ステップ5 できた要因を突き止める
検証精度とスピードの関係
「気づき」があったらそれはC
考え抜いた結果のミスはOK
鬼速クエスチョン 検証編
7章 調整:検証結果を踏まえた「改善」と「伸長」
ADJUSTの体系的理解が難しいわけ
ステップ1 検証結果を踏まえた調整案を考える
ケース1 ゴールレベルの調整が必要そうなもの
ケース2 計画の大幅な見直しが迫られるもの
ケース3 解決案・DO・TODOレベルの調整が必要そうなもの
ケース4 調整不要
ステップ2 調整案に優先順位をつけ、やることを絞る
ステップ3 次のサイクルにつなげる
検証と調整フェーズでよく起こる間違い
1 新しいものに目移りしやすい(個人)
2 間違ったものばかりに目が行く(個人・組織)
3 意見の統一がはかれない(組織)
4 課題のたらい回し(組織)
5 プロセスの可視化が不十分(組織)
鬼速クエスチョン 調整編
8章 チームで実践する鬼速PDCA
PDCAを鬼速で回す必要条件
鬼速で課題解決するための「半週ミーティング」
3日ごとの前進度合いを可視化する「鬼速進捗管理シート」
知見を集積するための「なるほどシート」
非緊急領域を定着化させる「ルーチンチェックシート」
有志によるPDCAワークショップ
鬼速PDCAコーチング
鬼速クエスチョン コーチング編
おわりに
付録 鬼速PDCAツール
10分間PDCA記入例
【読書】「仕事ができる人はなぜデスクがきれいなのか」 ― 2017/08/13

ビジネスマンが「探し物」に充てる時間は、1日に30分もあるそうです。
そうすると1ヶ月で22時間、年間で132時間もかかっているそうです。
さらにこれを給料(お金)に換算すると…。と例が載っています。
ここまではよくある話ですね。私が取り上げるまでもないです。
この本の面白いところは、
単純に「デスクを徹底的にきれいにする、それを維持する」
というだけでなく、
それがどうして「仕事ができる人」につながるのか、
というところまで踏み込んだことでしょう。
例えば、
「仕事の状態」
・忙しい ・余裕がない ・追われている ・混乱 ・押しつぶされそう
↓↑
「デスクの状態」
・モノや書類が溢れている ・資料が散乱
・パソコンデータがグチャグチャ ・必要な物といらない物が混在
↓↑
「頭の中の状態」
・整理がつかない ・仕事の優先順位を見極められない
・すぐ混乱する ・問題解決できない
という悪循環を起こしているというのです。まさに1学期の私です。
やはり手っ取り早いのはデスクの片付けですね。
以下、自分で参考になったエッセンスだけを取り出しておきます。
【片付けの基本動作】
step1 外に出す
片付けたい場所の物を、とにかく全部1か所に出す
↓
step2 分ける
減らす基準を決めて、「要」「不要」に分ける
↓
step3 減らす
step2で「不要」とした物を減らす
↓
step4 しまう
手元に残った物を配置などを考えず、とにかく元の場所にしまう
なるほどと思ったのは、step4で工夫も何もなく、元の場所に戻すということです。
片付けが苦手な人は整理(物を減らす)を徹底して行ってから、整頓に入ることが大切だそうです。
また、デスク周りを細かく分割して、1か所ずつ片付けていくというのも大事だと思います。
【保管と保存は別である】
●保管する書類
特徴
・業務で日常使用するもの
・修正、追加、削除が可能
しまう場所
・オフィス内のデスクの引き出し、ロッカー、共用棚など
処分の目安
・プロジェクトや年度ごとにファイルを仕分けし、それぞれ保存に移すタイミングを決め、時期がきたら保存処分と処分書類とに分ける
●保存する書類
特徴
・現状のまま置いておくもの
・修正、追加、削除は不可
しまう場所
・オフィス外の倉庫、トランクルーム等またはロッカー等
処分の目安
・社内規定や法定期間に従って、一定期間(1年~10年くらい)を経てから処分する。永久保存書類は例外。
これが難しいんですよね。どれが保管で、どれが保存か、誰も教えてくれないのです。
書類を渡されて「綴じといて」なんて言われますが、どこに綴じるのか、いつか必要になるのか(なったことは1度もない)、まったくわからずに「はぁ」と受け取っています。
まぁそのときに聞けばいいんでしょうけど、実は渡した本人も分かっていないというのが本音でしょう(人に渡す=自分で管理しなくて済む)。
【正のスパイラル】
いつも時間に余裕がある
↓
片付ける時間がある
↓
いつも身の回りがスッキリ片付けている
↓
物を探す時間が最小限ですむ
↓
いつも時間に余裕がある
〇整理で常に「物」を分けることが、仕事で扱うさまざまな「事」の、何が重要で、何を後回しにすればいいかを、判断する訓練になる
〇外に出すことで、自分の頭にあることが客観視できますし、思考の堂々巡りから抜け出せ、より良いアイディアを生み出すきっかけになる
〇「しまう」を徹底して行うことは、目的遂行のために、あえて「無駄なことはやらない」という、毅然とした態度を身につける機会にもなる
〇「使ったらすぐしまう」を日々心掛けている人は、上司や周りの人からのとっさの依頼にも、すぐ対応できる人
「すぐにしまう」という行為が、ある意味、対応力の訓練になっている。
〇「物の置き場所をきちんと決められる」人は、頭の中もスッキリとクリアで、ほかに必要な物を入れなければいけない場合でも、それを受け入れられるキャパシティがある
〇片付けは「15分=1セット」。人は時間を区切ることで、判断能力が高まっていく。15秒の中で、ある判断を下すということを、ビジネスの日常の中で繰り返していけば、普段より集中して判断しようという気持ちが働いて、確実に判断能力はアップします。
じょうごが上にも下にも広がっている(砂時計みたいに)と、たくさんの情報がインプットされてきても、溢れることなく処理をして、さまざまなアウトプットをすることができます。
それがつまり「仕事ができる人」なわけです。
カバンやパソコン内の片付けについても載っています。
さて、私はこの本をもとにして、職場のデスク周りを片付けてみました。
特にデスクの上はひどいです。
教科書やファイルのうえに、生徒からの提出物などをついつい載せてしまうので、地層のようになっているのです。
そして教科書を引き出す時には、その上の地層を崩さないように無駄に慎重にやっています。
デスクの手前の引き出し(エリア5)は、毎年カオスになっています。
ここは入れやすいので生徒の個人情報など、出しっぱなしにしておけないもの、ほかの書類と混ざってはいけないものを、ついつい入れてしまうのです。
その時は「一時的に」なんて思っていますが、年度の終わりまで持ち越される「墓場」であることが多いのです。
またデスクの下の足元(エリア6)も、捨てよう捨てようと思いつつ、シュレッダーするのが面倒になって溜め込んだ、書類の吹き溜まりです。
本に書かれているように実践した結果、この3ヶ所をキレイにすることができました。
教科書の上は何もなくなりました。
手前の引き出しはなんと空になって、カギだけになりました。
足元エリアはゼロ秒思考で使うためのA4裏紙と、もしかしたら必要になるかもしれない書類だけになりました。
さて、1日15分の時間を見つけて、また片付けていこうと思います。
リバウンドさせないことが、これからの課題になるでしょう。
やっぱりできると嬉しいものですね。がんばります。
そうすると1ヶ月で22時間、年間で132時間もかかっているそうです。
さらにこれを給料(お金)に換算すると…。と例が載っています。
ここまではよくある話ですね。私が取り上げるまでもないです。
この本の面白いところは、
単純に「デスクを徹底的にきれいにする、それを維持する」
というだけでなく、
それがどうして「仕事ができる人」につながるのか、
というところまで踏み込んだことでしょう。
例えば、
「仕事の状態」
・忙しい ・余裕がない ・追われている ・混乱 ・押しつぶされそう
↓↑
「デスクの状態」
・モノや書類が溢れている ・資料が散乱
・パソコンデータがグチャグチャ ・必要な物といらない物が混在
↓↑
「頭の中の状態」
・整理がつかない ・仕事の優先順位を見極められない
・すぐ混乱する ・問題解決できない
という悪循環を起こしているというのです。まさに1学期の私です。
やはり手っ取り早いのはデスクの片付けですね。
以下、自分で参考になったエッセンスだけを取り出しておきます。
【片付けの基本動作】
step1 外に出す
片付けたい場所の物を、とにかく全部1か所に出す
↓
step2 分ける
減らす基準を決めて、「要」「不要」に分ける
↓
step3 減らす
step2で「不要」とした物を減らす
↓
step4 しまう
手元に残った物を配置などを考えず、とにかく元の場所にしまう
なるほどと思ったのは、step4で工夫も何もなく、元の場所に戻すということです。
片付けが苦手な人は整理(物を減らす)を徹底して行ってから、整頓に入ることが大切だそうです。
また、デスク周りを細かく分割して、1か所ずつ片付けていくというのも大事だと思います。
【保管と保存は別である】
●保管する書類
特徴
・業務で日常使用するもの
・修正、追加、削除が可能
しまう場所
・オフィス内のデスクの引き出し、ロッカー、共用棚など
処分の目安
・プロジェクトや年度ごとにファイルを仕分けし、それぞれ保存に移すタイミングを決め、時期がきたら保存処分と処分書類とに分ける
●保存する書類
特徴
・現状のまま置いておくもの
・修正、追加、削除は不可
しまう場所
・オフィス外の倉庫、トランクルーム等またはロッカー等
処分の目安
・社内規定や法定期間に従って、一定期間(1年~10年くらい)を経てから処分する。永久保存書類は例外。
これが難しいんですよね。どれが保管で、どれが保存か、誰も教えてくれないのです。
書類を渡されて「綴じといて」なんて言われますが、どこに綴じるのか、いつか必要になるのか(なったことは1度もない)、まったくわからずに「はぁ」と受け取っています。
まぁそのときに聞けばいいんでしょうけど、実は渡した本人も分かっていないというのが本音でしょう(人に渡す=自分で管理しなくて済む)。
【正のスパイラル】
いつも時間に余裕がある
↓
片付ける時間がある
↓
いつも身の回りがスッキリ片付けている
↓
物を探す時間が最小限ですむ
↓
いつも時間に余裕がある
〇整理で常に「物」を分けることが、仕事で扱うさまざまな「事」の、何が重要で、何を後回しにすればいいかを、判断する訓練になる
〇外に出すことで、自分の頭にあることが客観視できますし、思考の堂々巡りから抜け出せ、より良いアイディアを生み出すきっかけになる
〇「しまう」を徹底して行うことは、目的遂行のために、あえて「無駄なことはやらない」という、毅然とした態度を身につける機会にもなる
〇「使ったらすぐしまう」を日々心掛けている人は、上司や周りの人からのとっさの依頼にも、すぐ対応できる人
「すぐにしまう」という行為が、ある意味、対応力の訓練になっている。
〇「物の置き場所をきちんと決められる」人は、頭の中もスッキリとクリアで、ほかに必要な物を入れなければいけない場合でも、それを受け入れられるキャパシティがある
〇片付けは「15分=1セット」。人は時間を区切ることで、判断能力が高まっていく。15秒の中で、ある判断を下すということを、ビジネスの日常の中で繰り返していけば、普段より集中して判断しようという気持ちが働いて、確実に判断能力はアップします。
じょうごが上にも下にも広がっている(砂時計みたいに)と、たくさんの情報がインプットされてきても、溢れることなく処理をして、さまざまなアウトプットをすることができます。
それがつまり「仕事ができる人」なわけです。
カバンやパソコン内の片付けについても載っています。
さて、私はこの本をもとにして、職場のデスク周りを片付けてみました。
特にデスクの上はひどいです。
教科書やファイルのうえに、生徒からの提出物などをついつい載せてしまうので、地層のようになっているのです。
そして教科書を引き出す時には、その上の地層を崩さないように無駄に慎重にやっています。
デスクの手前の引き出し(エリア5)は、毎年カオスになっています。
ここは入れやすいので生徒の個人情報など、出しっぱなしにしておけないもの、ほかの書類と混ざってはいけないものを、ついつい入れてしまうのです。
その時は「一時的に」なんて思っていますが、年度の終わりまで持ち越される「墓場」であることが多いのです。
またデスクの下の足元(エリア6)も、捨てよう捨てようと思いつつ、シュレッダーするのが面倒になって溜め込んだ、書類の吹き溜まりです。
本に書かれているように実践した結果、この3ヶ所をキレイにすることができました。
教科書の上は何もなくなりました。
手前の引き出しはなんと空になって、カギだけになりました。
足元エリアはゼロ秒思考で使うためのA4裏紙と、もしかしたら必要になるかもしれない書類だけになりました。
さて、1日15分の時間を見つけて、また片付けていこうと思います。
リバウンドさせないことが、これからの課題になるでしょう。
やっぱりできると嬉しいものですね。がんばります。
【読書】仕事ハック、巡り巡って戻ってきた。 ― 2017/08/11

借りてきた本に、リズ・ダベンポートの「机の上はいらないモノが95%」がありました。
ビジネス書コーナーで見たときに、「コックピット」「管制塔プランナー」というキーワードが気になって借りてみました。
話は非常にコンパクトに詰め込まれていますが、どれもこれも見たことがあるなーと思いました。
気になって最後の出版年を見たら2008年。そして著者紹介に「気がつくと机がぐちゃぐちゃになっているあなたへ」が代表作とありました。
これは、私が仕事術を学ぼうと思ったとき、初めて手に取った本です。
あーやっぱりと思いました。管制塔プランナーの話も、U字型デスクも、どおりで聞いたことがあるわけです。
むしろここから私は手帳術にはまり、フランクリンプランナーを試したり、毎年ほぼ日手帳とEditを比べたり、あげくに教師手帳というオリジナルリフィルを編み出したりしたのです。
この本は、その前著をコンパクトにまとめたものだそうです。
ほぼ再読なので、内容はストンと落ちます。
この本に書かれている通りです。
ですから、あえて、自分の言葉でまとめてみます。
1 必要なものは自分の手元に、使う頻度にあわせてだんだん距離をとるようにする。
2 情報は一元管理。すべての予定やメモを一冊の手帳にまとめる。
3 書類はトレイで管理し、待機トレイを定期的に空にする。
4 自分が集中できる時間と場所を確保する。
5 1日の計画を立てて着実に実行し、先送りするものは確実に予定に組み込む。
6 そして定期的に点検する。(書類の95%はいらない。)
魔法の質問
Q1 「それを捨てたら困りますか?」
Q2 「過去6か月にそれを使いましたか?」または「この先6か月に使う予定がありますか?」
Q3 「同じものがほかで手に入りませんか?」
改めて、自分の手帳の使い方、デスク周りを見直したくなりました。
書類の整理に時間と手間を割いてみようと思います。
原点に立ち戻った気持ちにさえなりました。
【目次】
PART1 机の上にあるモノの95%はゴミ―デスクまわりの整理術
1 自分だけのコックピットをつくる
2 仕事を見渡す「管制塔」をつくる
3 ハンパ書類の集合場所をつくる
PART2 効率的なスケジュール管理のための簡単ルールー時間管理術
4 スケジュール管理を最適化する三つのルール
5 システムをルーティン化する
6 定期点検
ビジネス書コーナーで見たときに、「コックピット」「管制塔プランナー」というキーワードが気になって借りてみました。
話は非常にコンパクトに詰め込まれていますが、どれもこれも見たことがあるなーと思いました。
気になって最後の出版年を見たら2008年。そして著者紹介に「気がつくと机がぐちゃぐちゃになっているあなたへ」が代表作とありました。
これは、私が仕事術を学ぼうと思ったとき、初めて手に取った本です。
あーやっぱりと思いました。管制塔プランナーの話も、U字型デスクも、どおりで聞いたことがあるわけです。
むしろここから私は手帳術にはまり、フランクリンプランナーを試したり、毎年ほぼ日手帳とEditを比べたり、あげくに教師手帳というオリジナルリフィルを編み出したりしたのです。
この本は、その前著をコンパクトにまとめたものだそうです。
ほぼ再読なので、内容はストンと落ちます。
この本に書かれている通りです。
ですから、あえて、自分の言葉でまとめてみます。
1 必要なものは自分の手元に、使う頻度にあわせてだんだん距離をとるようにする。
2 情報は一元管理。すべての予定やメモを一冊の手帳にまとめる。
3 書類はトレイで管理し、待機トレイを定期的に空にする。
4 自分が集中できる時間と場所を確保する。
5 1日の計画を立てて着実に実行し、先送りするものは確実に予定に組み込む。
6 そして定期的に点検する。(書類の95%はいらない。)
魔法の質問
Q1 「それを捨てたら困りますか?」
Q2 「過去6か月にそれを使いましたか?」または「この先6か月に使う予定がありますか?」
Q3 「同じものがほかで手に入りませんか?」
改めて、自分の手帳の使い方、デスク周りを見直したくなりました。
書類の整理に時間と手間を割いてみようと思います。
原点に立ち戻った気持ちにさえなりました。
【目次】
PART1 机の上にあるモノの95%はゴミ―デスクまわりの整理術
1 自分だけのコックピットをつくる
2 仕事を見渡す「管制塔」をつくる
3 ハンパ書類の集合場所をつくる
PART2 効率的なスケジュール管理のための簡単ルールー時間管理術
4 スケジュール管理を最適化する三つのルール
5 システムをルーティン化する
6 定期点検
【図書館】ビジネス書を読んで仕事を立て直す ― 2017/08/09

今年度は経験者研修2という大きな仕事が入っています。
そのために、先日管理職に指導を受けたように、今までの仕事の仕方が通用しなくなってきています。
一学期はギリギリ乗りきりましたが、二学期は・・・
生徒会役員選挙、文化祭、中教研(県大会、二次研)、
三者面談、進路事務、放射線教育講座、PTA広報の発行
パッと思い付くだけでもこれだけの仕事があります。
その合間に自分で経験者研修2の研究授業をあと3回やらなくてはなりません。
冬休みはそれをまとめて論文にするなんて仕事もあります。
そんなわけで、自分の仕事を立て直すべくあれこれやっていくことにします。
まずは、学校のデスク回りを整理整頓しました。
100均で買ってきたファイルボックスを使ったり、積み上げていた紙類をしまったりしました。
終わったとは言えませんが、少しスッキリ。
つぎに書斎。
こちらもパソコン横の作業スペースにごちゃごちゃしていた荷物を片付けました。
久しぶりに机が見えました。ちょっとスッキリ。
しかし、毎回これで終わってしまうから、すぐにリバウンドするんですよね。
今年度で異動を希望していることもあって、今からいらないものを処分していきたいなーと思いました。
そんな折、夏休みの研修中に、久しぶりに図書館に行くことができました。
で、ビジネス書のコーナーで5冊の本を借りてきました。
これを参考に、今まで以上に効率的かつ持続的な仕事術を身に付けようと思います。
【図書館で借りてきた本】
「サクッと1分間 整理・ファイリング術」
桃井 透/ぱる出版(2011)
「仕事ができる人はなぜデスクがきれいなのか」
小松 易/マガジンハウス(2010)
「机の上はいらないモノが95%」
リズ・ダベンポート/草思社(2008)
「結果を出している人が必ずやっている手帳フル活用術」
永岡書店(2010)
「仕事日記をつけよう」
海保博之/WAVE出版(2012)
そのために、先日管理職に指導を受けたように、今までの仕事の仕方が通用しなくなってきています。
一学期はギリギリ乗りきりましたが、二学期は・・・
生徒会役員選挙、文化祭、中教研(県大会、二次研)、
三者面談、進路事務、放射線教育講座、PTA広報の発行
パッと思い付くだけでもこれだけの仕事があります。
その合間に自分で経験者研修2の研究授業をあと3回やらなくてはなりません。
冬休みはそれをまとめて論文にするなんて仕事もあります。
そんなわけで、自分の仕事を立て直すべくあれこれやっていくことにします。
まずは、学校のデスク回りを整理整頓しました。
100均で買ってきたファイルボックスを使ったり、積み上げていた紙類をしまったりしました。
終わったとは言えませんが、少しスッキリ。
つぎに書斎。
こちらもパソコン横の作業スペースにごちゃごちゃしていた荷物を片付けました。
久しぶりに机が見えました。ちょっとスッキリ。
しかし、毎回これで終わってしまうから、すぐにリバウンドするんですよね。
今年度で異動を希望していることもあって、今からいらないものを処分していきたいなーと思いました。
そんな折、夏休みの研修中に、久しぶりに図書館に行くことができました。
で、ビジネス書のコーナーで5冊の本を借りてきました。
これを参考に、今まで以上に効率的かつ持続的な仕事術を身に付けようと思います。
【図書館で借りてきた本】
「サクッと1分間 整理・ファイリング術」
桃井 透/ぱる出版(2011)
「仕事ができる人はなぜデスクがきれいなのか」
小松 易/マガジンハウス(2010)
「机の上はいらないモノが95%」
リズ・ダベンポート/草思社(2008)
「結果を出している人が必ずやっている手帳フル活用術」
永岡書店(2010)
「仕事日記をつけよう」
海保博之/WAVE出版(2012)




最近のコメント